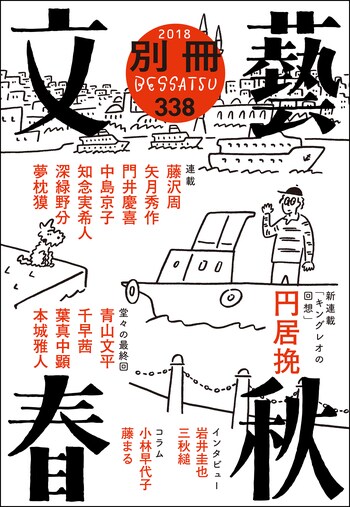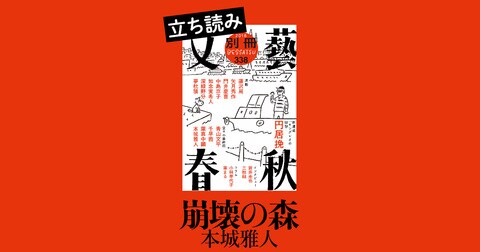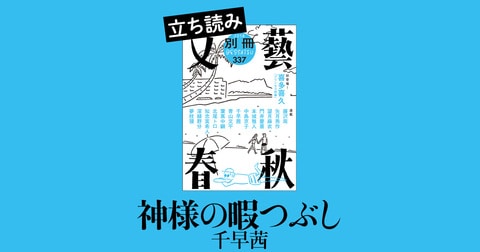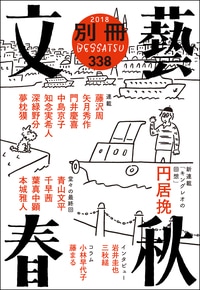
――藤子
そうして目を覚ますと、ちびちび日本酒を飲む里見が「雪」と窓の外を指した。
暗闇に、ほつ、ほつ、と発光する生き物のように雪が降っていた。窓ガラスにぶつかっては儚く溶け消える。
ふいにわかった。
私は変わったんじゃない。
変えられたのだと思いたいのだ。傷つけられたのだと。今はもう傷しか残っていないから、何度も何度も自分でかさぶたをはがし、痛みと見えない血が流れるのを感じて、あのひとのつけた傷を確認していたいのだ。
そんなものを後生大事に抱えている私のもとへ、あのひとが帰ってくるだろうか。
あのひとが惹かれるのは一瞬なのに。闇に吸い込まれ消えていくこの雪のような。
――人間はありものだ。いつか消える。
山形へ向かう電車で口にしていた言葉と、窓の外を見たまなざしを思いだす。視線の先には海があった。刻一刻と姿を変える空と海が。
もう、あの目は私を追ってはいない。
座布団に顔を突っ伏す。くたびれた布に鼻を押しあて、あのひとの古い蝋燭のような、けして良いとはいえない匂いを探し、薄れかかっていることに涙が込みあげる。
里見がまた本に目を落とす気配がした。
それでもまだ、ここにいれば、と思っていた。ここには廣瀬写真館がある。もう色の変わった野菜くずしか浮いていない濁った鍋の汁を捨てられないように、かすかな繋がりにすがっていた。