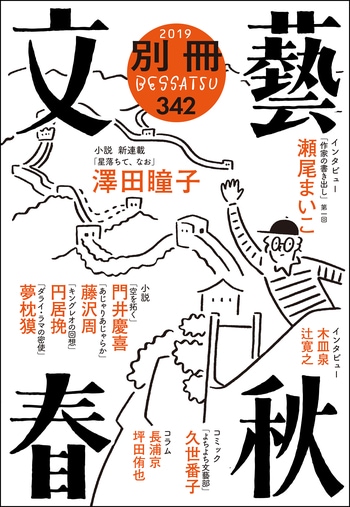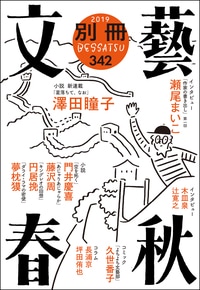
じじ、と音を立てて揺れた行燈の灯に、とよはぼんやりと顔を上げた。しみが目立つ画室の壁に伸び上がる己の巨大な影は、まるで自分を飲み込もうとしているかのようだ。
油が切れるはずはない。なみなみと溢れんばかりに油を注いだのは、まだ昨日の朝ではないか。そう思いつつ行燈をのぞき込めば、芦ノ葉に蛇籠を描いた黄瀬戸の皿はなかば乾き、とよが身じろぎしただけで灯がかき消えそうな有様だ。
改めて考えれば、それも当然だ。昨夜は父である暁斎の通夜がこの根岸の画室で営まれたため、家じゅうの行燈は夜通し点りっぱなしだった。それにもかかわらず今朝、油を足すことを思い至らなかった迂闊に、とよは自分が動顛しているのだとようやく気付いた。
「おとよさん、油の買い置きはありますか。夜とはいえ、まだ宵の口です。足りなければ、油屋を叩き起こしてきますよ」
部屋の隅にちんまりと正座をしていた鹿島清兵衛が、敏捷に腰を浮かす。掃除が行き届かぬせいで部屋の隅に丸まっていた綿埃が、その拍子に清兵衛の裾に子猫のようにまとわりついた。
養子とはいえ、東京では知らぬ者のおらぬ酒問屋・鹿島屋の八代目。新川の下り酒屋百軒余りを取り仕切る大店の主の割に、清兵衛は普段から妙なところに気が回る。
昨年の末より臥せっていた暁斎の命が旦夕に迫ったと知るや、商いを放り出して真っ先に駆けつけてきたのも清兵衛だし、その臨終の後、すぐさま店から百円もの大金を持ってこさせ、「これを葬礼のかかりに」と差し出したのも彼だ。
とよからすれば、如何に父の弟子とはいえ、二つしか年の変わらぬ清兵衛に何も彼も世話になるのは、気が引ける。だが清兵衛は尻ごみする河鍋家の者たちにはお構いなしに、葬儀の支度から僧侶の手配まで、一切をほぼ一人で取り仕切ってくれた。