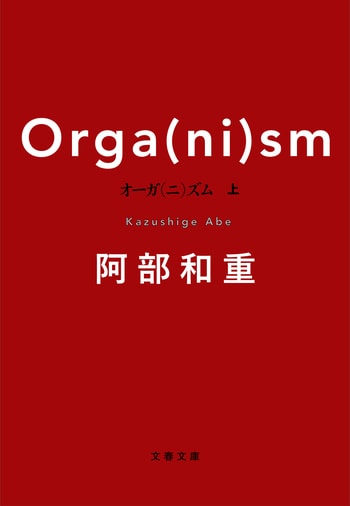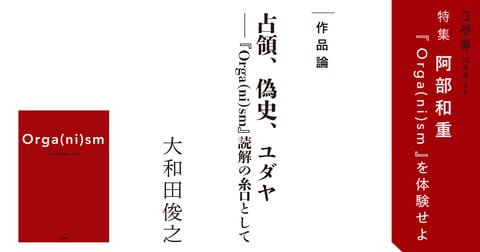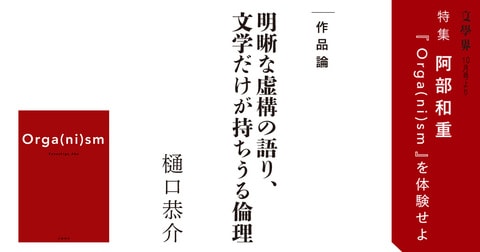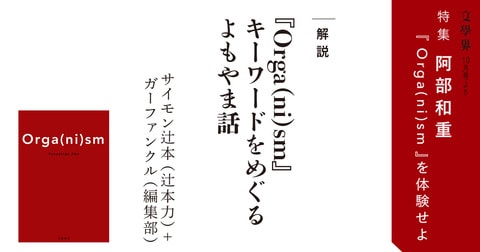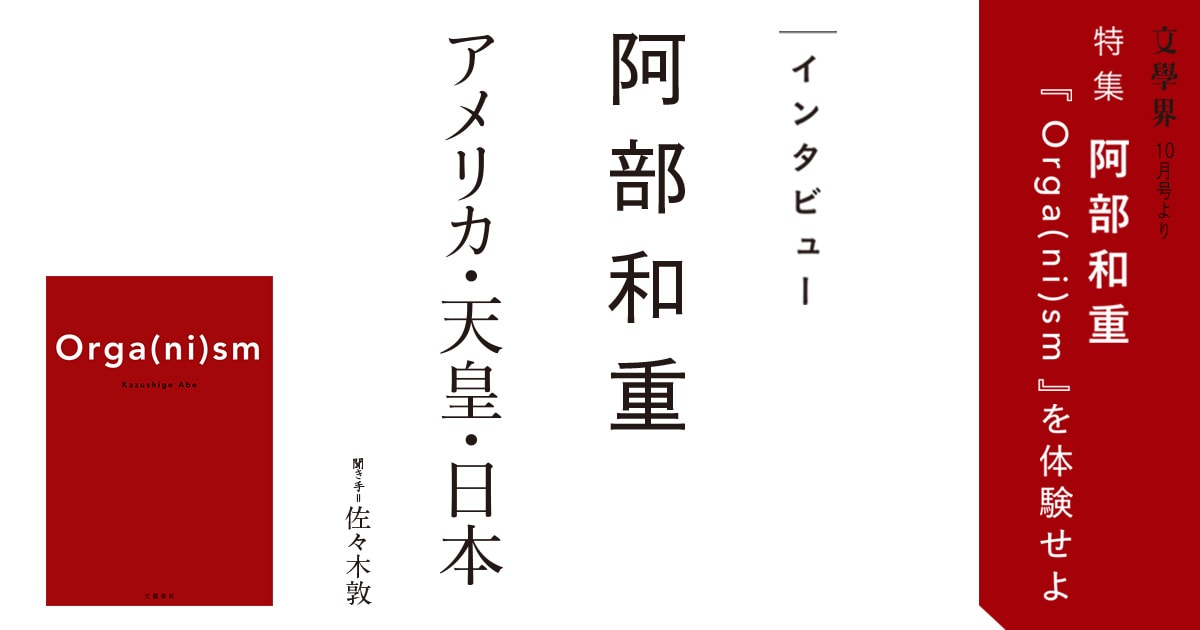
- 2019.09.24
- インタビュー・対談
<阿部和重 ロング・インタビュー> アメリカ・天皇・日本 聞き手=佐々木敦 #1
文學界10月号 特集 阿部和重『Orga(ni)sm』を体験せよ
出典 : #文學界
『シンセミア』連載開始から二十年、『ピストルズ』刊行から九年。
神町(じんまち)トリロジーの完結篇にして、数々の謎が仕掛けられたエンターテインメント巨篇『Orga(ni)sm[オーガ(ニ)ズム]』がついにヴェールを脱ぐ。
二〇一四年、日本の首都となった神町を舞台に展開する、作家「阿部和重」とその息子・映記(えいき)が巻き込まれたCIAと菖蒲(あやめ)家の対立、そして日米関係の行方は――。
私小説/メタフィクション/現代文学がアップデートされる瞬間を目撃せよ!
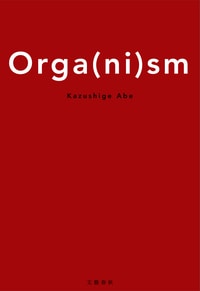
不可視のものに手が届く感覚
――神町トリロジーの第三作目となる『Orga(ni)sm[オーガ(ニ)ズム]』の完結、おめでとうございます。阿部さんに作品に即したインタビューをするのは、六年くらい前、『ピストルズ』が文庫化された時が最後です(のちにcakesに掲載)。そのインタビューでは神町サーガほか、当時刊行されていた阿部さんのほとんど全作品に触れつつ、まだその時点では書かれていなかった三部作の第三作目についても少しお話をうかがいました。
阿部 共著もふくめると、伊坂幸太郎さんとの合作『キャプテンサンダーボルト』でもお世話になっていますし、佐々木さんには節目節目でインタビューをしていただいています。
――のちほど『シンセミア』『ピストルズ』と連なるトリロジー全体についてもうかがいますが、まずは『Orga(ni)sm』の話から。連載が文學界で始まったのは二〇一六年の秋です。前作『ピストルズ』は二〇一〇年に本になっているので、そこから第三部が始まるまでに六年が経っています。その間にも神町サーガ以外の長篇を書いたり短篇集を出したりされていますが、『Orga(ni)sm』をこの時期に開始したのは、どのような事情があったのでしょうか。
阿部 いくつかの事情が重なった結果です。
まず前提条件として、もともと第三作目は、前作『ピストルズ』のある意味で主人公である菖蒲(あやめ)みずきと、第一作『シンセミア』の最後に登場する田宮光明、この二人のキャラクターがかかわりあうことで生まれる物語になるというプランがありました。
その二人は、小学校の教師と児童として出会うことになる。田宮光明は二〇〇一年生まれなので二人にはそこそこ年齢差があり、さらに出会う場が学校ということになると、それが起こりうる二〇一三年くらいまでは待たなければいけないことになります。
――なるほど。
阿部 もちろんフィクションなので、二〇一三年を迎える前に話を書くこともできた。実際にこれまでも、たとえば『ニッポニアニッポン』では刊行時よりちょっと先の近未来の出来事を作中で書いていたりするので。しかし同時に、二〇一三年の現実の社会状況を作中にダイレクトに取り込みたいというアイデアもありました。どちらかというとそのことのほうが執筆時期を決めたといえます。
――実際の二〇一三年がくるまで待つ必要があったと。
阿部 たとえば、これもわりとはやい段階から、『Orga(ni)sm』はアメリカの大統領来日を物語中に組み込みたいと考えていました。作中ではバラク・オバマが国賓として日本にやって来るのですが、現実にもオバマは二〇一四年に来日しています。現実の出来事を作中に取り込むというのはそういうことですね。ですから、二〇一三年時点でのアメリカの政権がどういう状況かとか、その近辺に大統領来日の予定はあるのかとか、現実の状況がわかっていたほうがより緻密な物語を構成できる。それらの事情が重なり、まず二〇一三年が過ぎるまではこの作品を始動できないという確信がありました。
――いきなり話が核心に入っています。第二作『ピストルズ』は、基本的には二〇〇六年の秋に起きる出来事なんですよね。しかし最後のシーンは、二〇一三年二月時点の語りで終わっている。いま阿部さんがいったことを踏まえれば、『ピストルズ』を書き終わった時にすでに三作目の構想があり、そのため二〇一三年二月と記していたということですか。
阿部 そのとおりです。
――じゃあ『ピストルズ』刊行の二〇一〇年時点で、この後三年は待たなきゃいけないことは決まっていたんですね。
阿部 決まっていました。『ピストルズ』を、小学校で二人が出会う二ヵ月前にあたる二〇一三年二月の日付で書かれたレポートのかたちで存在させ、ということはつまり、その時点ですでに二〇一三年の神町がどういう状況になっているかもある程度決めておく必要があった。かなりの部分が、少なくとも『ピストルズ』が終わった時点では固まっていました。
――したがって、三部作を書くのを待っている期間に別の作品を書くことも可能だったということですね。
阿部和重という小説家は、作品を書く前に入念な下準備をし、どういう作品にするのかをさまざまなレベルで考え抜いてから書き始めるということを、本人も何度も公言されていますし、それを実践してもいる。一方で、それでもやっぱり現実の中で小説を書くとなると、作者にはどうしようもない現実の動き、作家の外側にある歴史や社会の変化に作品が巻き込まれてしまう部分がある。したがって、最初に構想していたものと実際できあがるものの間には当然ズレが生じるわけじゃないですか。ズレとはネガティブな意味ではなく、むしろいいことだったりもすると思うんですが、そのズレはいったいどういう次元で『Orga(ni)sm』の中に入り込んでいったのか。
興味深いのは、いまのお話だと『ピストルズ』の最後には二〇一三年二月という日付が出てきて、さっき言及した『ピストルズ』文庫化のインタビューの際にも、阿部さんは「(三作目は)二〇一三年の話になるんじゃないか」といっているんです。それはほとんど実現されているんだけど、でも一年ズレていますよね。『Orga(ni)sm』は二〇一四年三月から四月の話になっている。それは、オバマが日本に来たのが二〇一四年四月だからですか?
阿部 それが最大の理由です。オバマ来日からまた微調整していって、最初に立てたプランを組み替えていった。いま佐々木さんに整理していただいたように、確かに僕は、長篇でも短篇でも、七~八割は事前に内容を固めた上で書き進めていって仕上げる方法を常にしています。この三部作も第一部『シンセミア』を書きながら第二部、第三部を構想していました。
一方でこれも僕の特徴で、現実の日付や史実、その時々の出来事を作中に取り込みながら物語を構築する書き方をしている。当然、現実が反映されることで、考えていた物語や作品の形式が変わらざるをえない部分が出てくる。そのせめぎあいの中でいつも書いています。つまり可能なかぎり緻密な設計図を事前に用意することを志向しながらも、変動的な要素が入りこむ余地がないところまで組み立ててしまうわけにもいかない。そんな矛盾する状態で書き進めることになるのです。
――偶発的事態に備えておく部分がないといけないですもんね。バッファというか。
阿部 最初からそういうやり方を志向していたわけではありません。第一部『シンセミア』の連載スタートが一九九九年ですから、この三部作は完結までにちょうど二十年かかっています。最初に自分が立てていたプランが、現実のいろんな出来事により変化を強いられるやり方に、二十年かけて慣らされていったというのが正確かもしれません。
これは得がたい経験でした。二十年の歳月をかけて先ほど言ったような矛盾状態に身を置きながらひとつの企画に取り組んできたことで、まだ文学というジャンルの中で未開拓だった土地に足を踏みいれられたのではないか、という感触が自分なりにある。有言実行じゃないですけれども、『シンセミア』を発表した時点で「三部作にする」と宣言してしまったのは、結果的によかったと思っています。
有機体としてのトリロジー
――お話を整理すると、阿部さんは完璧主義者で、ある種の閉じた世界を、精巧に緻密に作り上げようとする志向がある。もう一方で、自分にはどうにもならない現実とか歴史に対応していく姿勢もある。これはわかりやすく分類するとフィクションとドキュメントということになりますが、その二つは、作家のあり方として本来まったく別の志向だと思うんですよね。両方がどちらも強いかたちで一人の中にあるのが、阿部和重という作家のかなり変わったところで、その方法論をある時期から自覚的にやられてきた。
阿部 そういう二つのタイプの作風が自分の中でわりとすんなり接続してくれたのは、やっぱり映画の影響があると思う。もともと僕は映画を勉強していて、映画を撮りたいという志向性があったわけですけれども。
――映画ってどうしても現実が入ってきますものね。
阿部 いくら物語としてシナリオを緻密に組み立てても、さあ現場で撮ろうとなった時に、否が応でも現実に合わせざるをえないクリエーションが映画です。その二方向がごく当たり前に製作の現場にある状態が、自然なこととして自分の中にあったといえるかもしれない。
そこから話をつなげると、『Orga(ni)sm』には主人公の一人といっていい人物として作家の「阿部和重」が登場します。これは典型的な「巻き込まれ型」キャラクターです。作中の「阿部和重」が、さまざまな事態に巻き込まれながらいろんな体験をするかたちで物語が進展する。実際の僕も、事前に組み立てた物語を書き進めながら、現実のさまざまな出来事に巻き込まれながら物語を変形させていく。この二つは重なっているんじゃないか。
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。