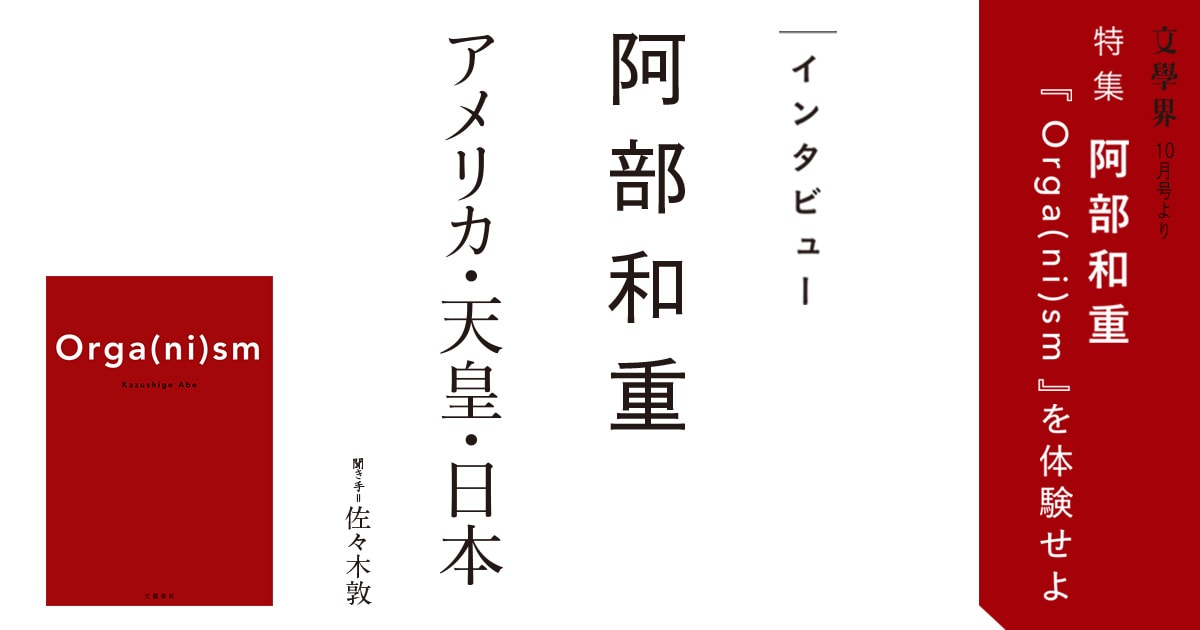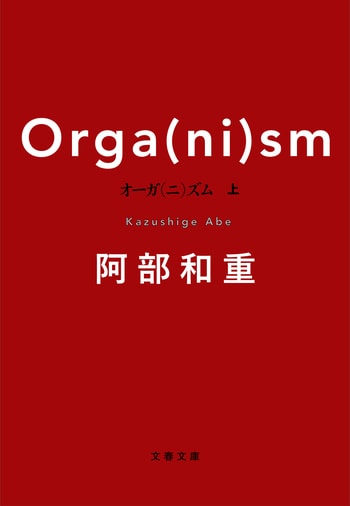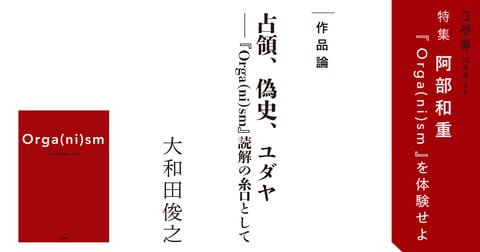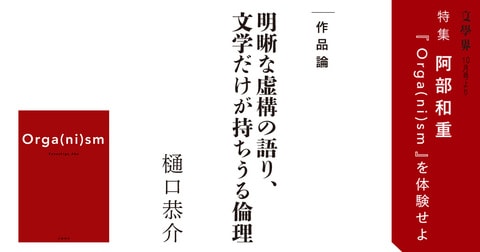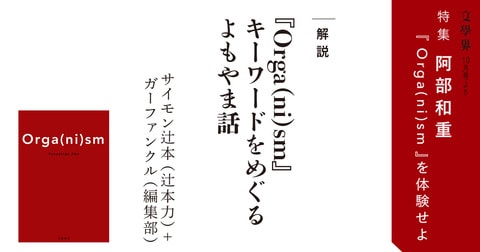『シンセミア』連載開始から二十年、『ピストルズ』刊行から九年。
神町(じんまち)トリロジーの完結篇にして、数々の謎が仕掛けられたエンターテインメント巨篇『Orga(ni)sm[オーガ(ニ)ズム]』がついにヴェールを脱ぐ。
二〇一四年、日本の首都となった神町を舞台に展開する、作家「阿部和重」とその息子・映記(えいき)が巻き込まれたCIAと菖蒲(あやめ)家の対立、そして日米関係の行方は――。
私小説/メタフィクション/現代文学がアップデートされる瞬間を目撃せよ!
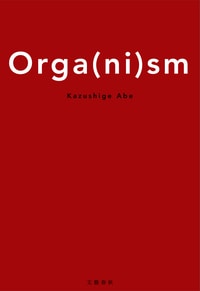
人権問題としての天皇制
――連載が完結したのは二〇一九年五月刊の文學界六月号です。実は僕は今年の春「すばる」に「私的平成文学クロニクル」という小論を書きました。平成の三十一年間を、一年に一作ずつ代表的な小説を選んで論じていく内容です。それを書くにあたって、文學界に『Orga(ni)sm』の完成予定を問い合わせたんです。なぜなら『Orga(ni)sm』が平成のうちに終わるのではというある種の確信を僕は持っていたんですよ。だから平成三十一年の最後の作品を『Orga(ni)sm』にすれば収まりがいいと思ったんですね。
阿部 それはありがたいですし、申し訳なかったです(笑)。
――阿部和重という人はそういうことをやる人だという思い込みがあったので。結果的には、掲載がもうひと月早ければ平成のうちに終わっていたんですよね。
阿部 執筆自体は平成中に終わっていたのですが。
――黒人大統領の誕生や東日本大震災と同様、平成が令和になるのもある時期まではわかっていなかったわけじゃないですか。二〇一九年五月に改元が行われることは一年くらい前に周知されていましたが、これについて何か意識されていたことはありましたか。
阿部 特に思い入れや考えはありませんでした。一方で、この三部作は日米関係と同時に、天皇制をどのようにとらえるかがテーマの一つでした。『シンセミア』では天皇家と相似関係にある田宮家が崩壊する過程が描かれている。『ピストルズ』は国家の中で特殊性を引き受けた存在として菖蒲家が設定されている。それら二つの物語を引き継いで、天皇制の物語をどのような結末に至らしめるかが『Orga(ni)sm』の重要なテーマとしてあったのは確かです。実は今作では、いわゆる皇室とか天皇制についてはほとんど触れていません。直接的に触れていないのだけれども、自分の中ではテーマの結末は決まっていて、物語全体がその方向に向かっていき、むしろ触れないことで最終的な一行が際立つということをやりたかったんです。ネタバレになってしまうので多くは語れないのですが、天皇制は終わらせるべきだということがわりとはっきり書かれてあります。
――本書の、驚くべき結末に関する部分ですね。
阿部 その一行に、これまで三部作を通じ天皇制の物語を書いてきた全部を結び付けたかった。以前、高橋源一郎さんが文芸誌の対談で「阿部さんは、日本は女性天皇でいいのではないかと戦略的に書いている」とおっしゃっていましたが、それは誤解です。というのも、『ピストルズ』の物語は菖蒲家の伝統を終わらせるという方向に進んでいるので。
――そうか。秘術継承者のみずき自身もそう考えていると確かに書かれていました。女性天皇は誕生しているけれどそこがゴールではなく、すでに『ピストルズ』の時点で天皇制廃止が最終的な結論なんですね。
阿部 はっきりと「女性天皇であっても終わらせるべきだ」というのが僕の考えです。なぜ終わらせるべきか、それも『ピストルズ』で書いたつもりなんですけれども、つまりこれは人権侵害であるから。アメリカの話ともつながりますし、沖縄についてもおなじことが言えますが、要するに皇室には全国民が汚れ仕事を押しつけているようなものであって、同時に自由も奪っているわけです。それはやっぱりまずいだろうという考えがありました。ただ声高にそう主張するのではなく、最後にさらっと一行だけ言及して終わらせる書き方が、クールでいいんじゃないかなと。
――読みながら、『Orga(ni)sm』は前二作に比べ天皇の要素が薄いなと思っていたんです。天皇の問題はいわゆる万世一系の問題で、もっと一般化すると再生産、リプロダクションの問題ですよね。映記くんという息子が出てくることにその問題が接続されているのかなと最初は思っていました。でも最後まで読めば、これはやっぱり天皇制の物語だったとわかる。
阿部 天皇制に関する僕の主張は、菖蒲家に伝わる一子相伝の秘術「アヤメメソッド」がどのように扱われているかに着目していただくとわかりやすいかもしれません。菖蒲家はそういったいわゆる万世一系とつながる物語や伝統を破壊して、アヤメメソッドをばらまき、普及させようとする。
――みんながその秘術を使えるようにしてしまうことで無化するわけですね。
ボウイ、プリンス、ベルトルッチ
――小説の最後の方の話をもうちょっとだけ。終わり間際に、サイモンとガーファンクルの歌詞が出てきます。
阿部 「America」という曲ですね。
――有名な歌ですけど、思ったのは、阿部さんはこれまでいろんなかたちでデヴィッド・ボウイとプリンスへの愛を表明していますよね。曲名をタイトルにした小説も書かれている。そのデヴィッド・ボウイとプリンスは二〇一六年に相次いで亡くなっている。
阿部 そうなんですよね。
――二〇一六年一月にボウイが亡くなり、四月にプリンスが亡くなって、十月に連載が始まる。『Orga(ni)sm』には、阿部さんにとって特権的な二人のミュージシャンへの追悼が流れこんでいるんじゃないかと推察されます。そこで気づいたのは、「America」をデヴィッド・ボウイがカバーしているんです。
阿部 ええっ、それは知らなかった!
――しかも、9.11の同時多発テロを受けてニューヨークで行われたチャリティ・ライブで歌っている。
阿部 そうなんですか。イエスによるカバーは知っていましたが……。
――では、それは偶然なのですね。二〇一六年の連載開始は、さまざまな偶然や事情によってそうなったとのことでしたが、ボウイとプリンスがもういないということは結構重要だったんじゃないですか。
阿部 二〇一六年に訃報が立て続けにあり、しかも完結篇の視点人物が「阿部和重」なので、余計にその時々の思いが反映されているところはありますね。はっきり追悼とわかるように書いている箇所もあります。さらにいうと、映画監督のベルナルド・ベルトルッチも連載中の二〇一八年に亡くなっていて、あからさまにベルトルッチ作品を下敷きにして書いている場面もあります。
――阿部さんのツイッターにも、ここのところ追悼の投稿が多い印象がありました。私淑してきた人たちが相次いで亡くなっていく。つまるところ、われわれも年を取ってきたということなのかもしれません……。
文学、この特異な創作形式
――これまで神町サーガは、フォークナーや中上健次の小説を、モデルあるいは仮想敵にしていると捉えられることが多かったと思います。
阿部 乗り越えるべき対象であったのは間違いないですね。
――でも大きく違う部分がある。フォークナーのヨクナパトーファや中上の路地は、やっぱり作家が世界を自分で作っている意識が強いんですよね。とにかく閉鎖的に、稠密に作られている。対して阿部さんは、今日のインタビューでもおっしゃっているように、自分が現実の世界や歴史の中に受動的にいざるをえないことに、ものすごく意識的です。いいかえれば、自分が書いたことで文学の境界が拡張したり変質したりする作用に、ずっと意識を向けられてきたと思うんです。抽象的な質問になりますが、文学というものに対してどういう思いを持ってらっしゃいますか。
阿部 土地の問題の物語化の手つきにおいて、フォークナーや中上健次の作品と僕の小説とはたしかに違います。たとえば中上健次は、生地を聖地として描きつつ、日本の近代文学の中で培われた小説作法を継承した作家です。対して不作法な自分はそれ以後に小説を書く立場として、逆に神町という土地の「何もなさ」を前面に出して物語化していく方法が可能なのではないかと思ったんですね。そういう意味では、フォークナー、中上がいたからこそ自分の作風は生まれたともいえる。
文学についてのご質問ですが、僕はいわゆる文学の教育をまともに受けていない状態でデビューし、もう二十五年くらい、文学とは何かを自分なりに考えながら手探りで書いてきました。わかってきたのは、文学は技術革新によって形式性や表現がガラッと変わるという経験がほとんどなかったジャンルであり、その意味ですごく特異な創作形式だということです。
音楽でも映画でも美術でも、ほとんどの表現は、必ず何らかの技術革新を経てその時代の特徴を生み出しています。しかし小説に関しては、基本的には文字しか扱わないというジャンルの特徴によって、技術革新が入り込む余地がない。だから、あるタイミングで何かが大きく変わるということがない。もちろんその時代ごとに、たとえばヌーボーロマンのような、際立った特徴を持った作風が生まれてはいます。しかし、例えば九〇年代に情報技術革命によって他ジャンルで一気に表現の幅が広がったような変化は、文学に関してはごく小さくしか認められない。
そんな中、デジタル化はもしかしたら、文学が技術革新によって形式的変化を経験できたかもしれない、ほぼ唯一のチャンスだったんじゃないかと思います。というのも、僕は九七年からパソコンで書くようになり、同時にインターネットを使うようにもなりました。ちょうどネット環境がすごく充実したのが二〇〇〇年ぐらいですよね。そのあたりでいまの自分の書き方が確立された感触がある。個人的にはあの時に何か文学というものの作り方が変わった、変えられた可能性があったと思うんですが、その変化がきちんと指摘されるぐらいかたちになっているかというと、それはよくわかりません。もしかしたら、みんなパスティーシュがうまくなったとか、せいぜいその程度のものなのかもしれない。
蓮實さんからの受け売りになりますが、文学というのは定まった形式的な規範が、あるようでない。何をやってもいいとは常にいわれているし、逆に定まっていないからこそ、参入障壁が非常に低い。国語教育を受けている人だったら、散文は誰でも書けます。何であれ散文を「これは小説です」と差し出せば、小説として読まれてしまう。何も定まったものがないからこそ、「もう文学は終わっているし、何も書くことがない」と百年以上前からいわれながら、いまに至るまで続いているジャンルなんです。