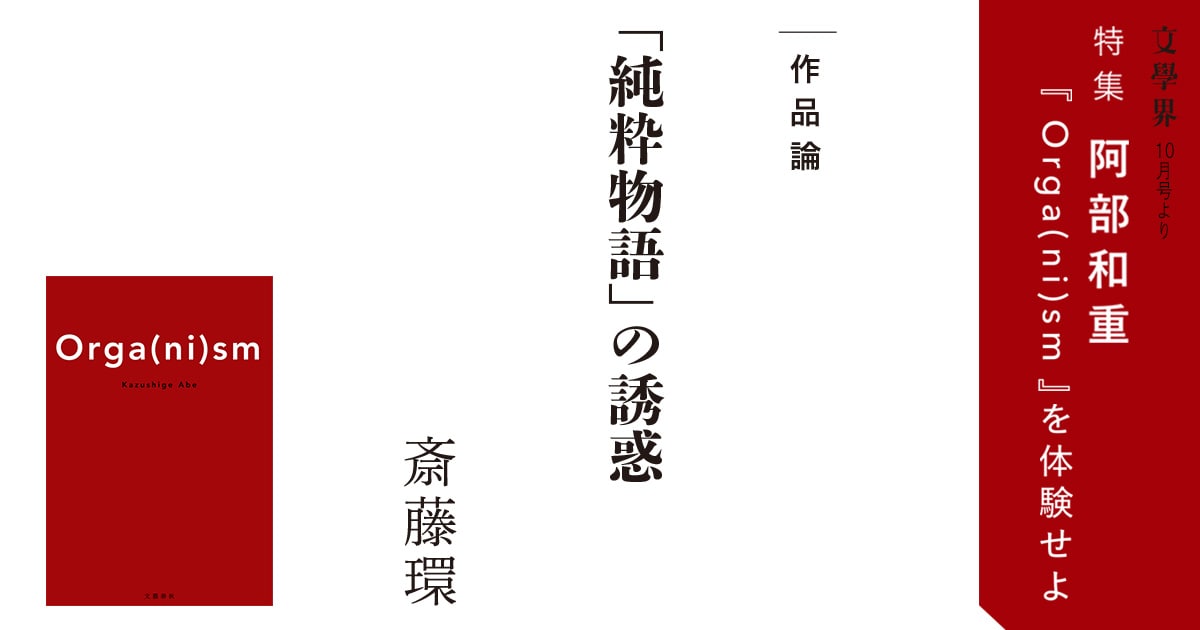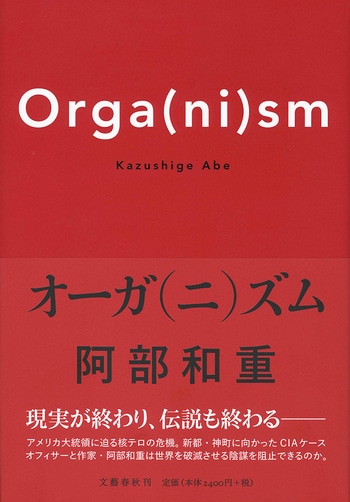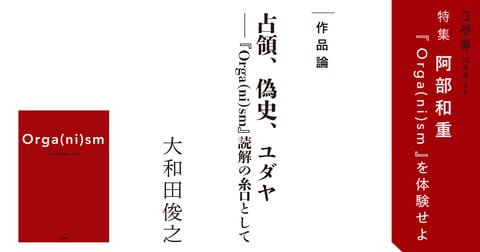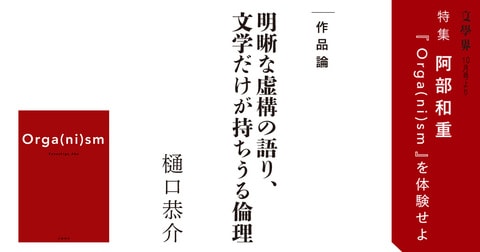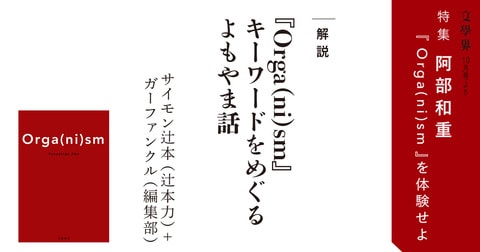精神分析家は言うだろう。それは故郷という土地の「固有の身体性」を抑圧することで、自らの出自=無意識の欲望を否認しているだけではないか、と。むしろそのような否認の身振りこそが、作家自身の固有の身体性への憧憬の位置を指し示しているではないか、と。しかし、あえて言えばそうした定型的な分析は、阿部作品の読解に際しては意味をなさない。分析の当否に関わらず、それでは何も言ったことにならないのである。
この点については、阿部自身の重要な証言があるので引用しよう。
「フィクションにおけるリアリティというのは一体何かというと、フィクションを組み立てること自体がそもそも不自然な行為であるので、その不自然さを人目にさらすような表現形式上の限界点を、フィクションをつくり込むことによって際立たせるということが、結果、まがいものとしてのフィクションのリアリティを示すことにつながる」(前掲対談)
私はくだんの対談で、ここで阿部の言う「フィクションの不自然さ」を自然に引き戻そうとする要素として(阿部には嫌がられつつも)「作家汁」という言葉を繰り返している。どれほど隠蔽しようとしても作品の随所から滲み出してしまう作家自身の無意識、身体性、固有性といった要素をそのように呼んだのである。文学史上最も作家汁に禁欲的であった作家は三島由紀夫であろうが、それが『英霊の聲』や自決といった固有性の暴発に帰結したことを思えば、一般に作家汁の抑制はリスクを孕むであろう。
「作家汁」が発露するルートは複数ある。ひとつは「文体」において。文体は最も素朴な意味で作家の身体性を担うからだ。ふたつめは「キャラの自律性」である。逆説的なようではあるが、自律性を帯びたキャラは基本的には作家の分身であり、その自律性が紡ぐ物語において作家の無意識が投影される。みっつめは「物語構造の自律性」である。中上健次の「紀州サーガ」がそうであったように、物語そのものも成長するかのように自律的な変容を遂げていく。こちらの場合、やや特異なのは、作家の無意識のみならず、そこに社会性や時代性までもが反映されてしまうという点だ。
しかるに「神町サーガ」で阿部がとったのは、およそ文学史上誰も試みたことのないような、気宇壮大な戦略だった。その戦略は、どこを目指したのか。以上述べてきたような作家汁(=自然)による「汚染」を可能な限り抑圧しつつ「フィクションの不自然さ」を徹底的に研ぎ澄まし、どこにも着地せずに浮遊し続ける「純粋物語」のための空間を創設すること、これである。
この視点から改めて本作を辿り直すと、阿部和重の巧緻を極めた戦略が見えてくる。ならば、それはいかなる企みであったか。以下に列挙してみよう。
・「神町サーガ」三部作を形式として解離させること。すなわち設定や人物は継承されるが、視点と文体を徹底的に断絶させること。
・キャラクターを立てつつも、いっさいの自律性を与えないこと。例えば本作では、物語が進行してもキャラクター間の関係性はほとんど変わらない。語りの多くを回想が占めており「実はこうだった」という事実が判明した場合でも、関係性は遡行的にしか変化しない。結果、キャラクターは物語のプロセスにほとんど介入できない。すなわち、キャラクターと物語の解離である。
・故郷である「神町」をアヤメメソッドの力を借りて首都に改造すること。それは、魔法でかぼちゃを馬車に変える行為にも似て、本作においてもっとも苛烈な解離的操作となった。この改造は、土地の土着性と固有性をほとんど根こそぎにしてしまう。痛みも叫びもともなわずに。
・もっとも巧妙だったのは、作家本人を「キャラ化」してしまった点である。先述した通り、本作における作家・阿部和重の扱いはひどいものだ。ただし、それは良くある作家の自己言及的な自虐ごっこではない。自身を物語中における「いじられキャラ」として設定し、家族構成や作品歴などの事実関係をほどよく混入することで、漫画やアニメのキャラのように輪郭のはっきりした「阿部和重」というキャラが爆誕したのである。このことが何を意味するか。いまや「阿部和重」は、複製と増殖が可能なキャラという存在に変換されたのだ。言い換えるなら、この操作によって「阿部和重」の固有性までもが記号化されたのである。この操作によって「キャラとしての阿部和重」は、作者としての阿部和重から完全に解離された存在となった。本作がエンターテインメントの文体を採用したのは、それがこうした「キャラ化」にとって最適の環境を提供するからにほかならない。
かくして阿部は、「意味」や「物語」を少しも損なうことなく、前人未到とも言える巨大な「純粋物語」を構築した。あえて「純粋小説」と呼ばないのは、この手法がほぼそのままの形で映像作品にも応用可能であるからだ。いかなる象徴性を孕むこともないその物語には、どこからも作家汁が滲み出す隙間がないように、完璧な表面処理がほどこされている。その意味で本シリーズは、「神町サーガ」ならぬ「神町プロジェクト」と呼ばれるべきだろう。
いまや私には『Orga(ni)sm』という謎めいたタイトルも、このように響く。「あなたがフィクションから得ている快楽(オーガズム)は、物語という有機的な組織体(オルガニズム)の効果にすぎないのだ」と。神町プロジェクトの成果によって、物語は象徴性と固有性の重力圏からゆっくりと離脱しつつある。そこから拓かれるのは間違いなく「純文学」(文字通りの意味で)の新たな地平にほかならない。