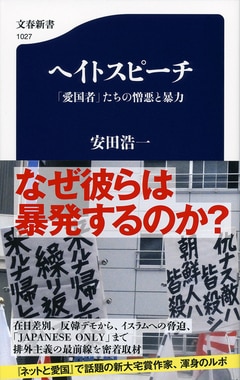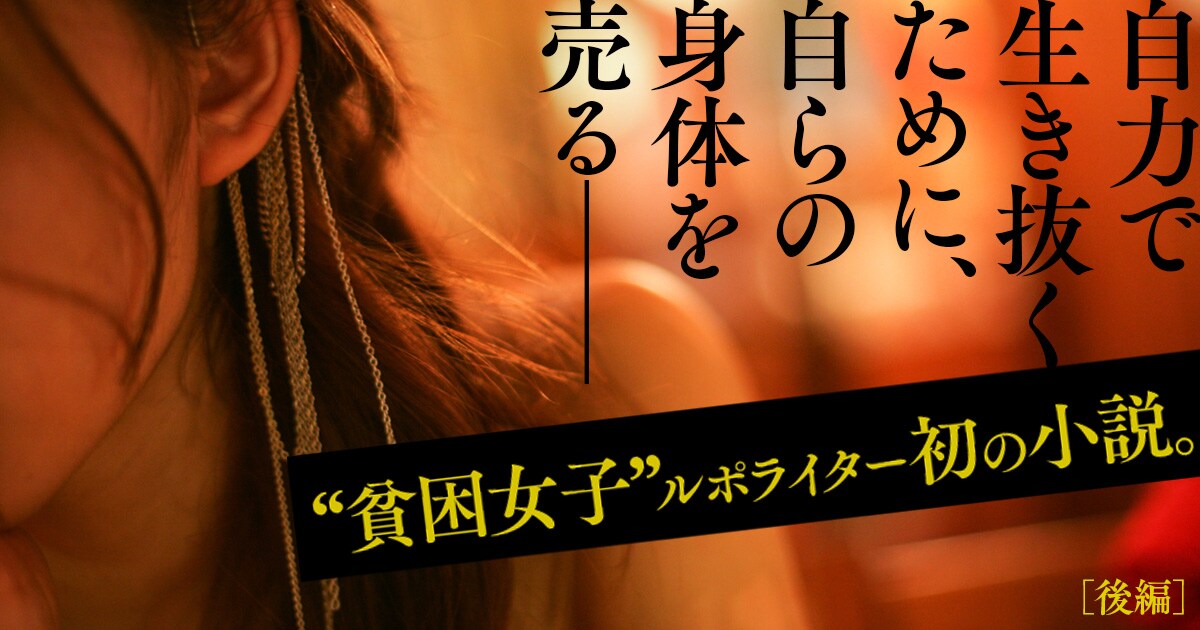
単純な善意や常識的な理屈は邪魔でしかなかった

本書はあくまで小説。ひとりの少女の半生を物語化していく中、当然里奈本人や周囲の人々の「現在」に不都合が起きないよう、事実を改変して書いたり、それまで僕が取材してきた無関係の実在人物や事件を里奈の人生に配してみたりはしている。
けれども、彼女の発するメッセージは一貫して、改変する余地がないほどに強いものだった。
「売春による稼ぎで居所不定の生活を送る未成年の少女」は、本来保護とか支援とか、児童福祉の対象なのだが、そうした文脈で自分たちが被害者扱いされることに、19歳の里奈は激しい抵抗感を示した。
それはやはり第一に、そうして自力で生きる少女らが、たとえ自らの性を切り売りし搾取されようとも、たとえ時には暴力の被害など恐ろしい経験をすることになっても、「自分の力」で生きていることを誇りに思い、その場で得られる自由とパワーの中に、それぞれ十代の少女なりの青春を味わっていたからだ。
少女らの生きる世界の眩しさと逞しさを前に、単純な善意や常識的な理屈は邪魔でしかないのだと改めて思い知った。少女らからすれば、たとえどんなに劣悪な環境であっても、自分の力で奪い取った自由を誰にも侵されたくないのだ。
もちろんその後の人生のリスクを考えれば、彼女たちが何らかの支援に繋がるべき存在だということは曲げられない。けれど、福祉や支援や制度みたいな四角張った「漢字2文字」と彼女らの間になぜ斥力があるのかは、改めて痛いほどに学ばせてもらった。
こちらもおすすめ
プレゼント
-
『圧勝の創業経営』
ただいまこちらの本をプレゼントしております。奮ってご応募ください。
応募締切 2025/07/26 00:00 終了 賞品 『圧勝の創業経営』5名様 ※プレゼントの応募には、本の話メールマガジンの登録が必要です。