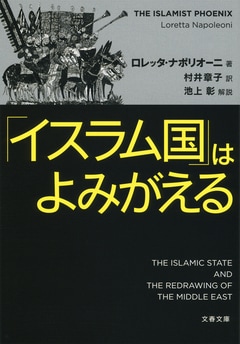「ロマの青年の魂の彷徨を描いたあの映画のように、今回は私にとっての『ジプシーのとき』に挑戦してみたかった。と同時に、クストリッツァは悲劇的な題材を扱いつつも、ドリフのコントかと思うような、コメディータッチの描き方もしますよね(笑)。今回、テーマは重いので、同じように全体は喜劇的に、と考えて書いていきました」
印象的なのが、作中に何度も登場する「石」の数々だ。たとえば、須藤がウェブオークションで七百円で買ったという石ころ。なんとこれは、宮内さんの実体験だという。
「鉱石が好きなんですが、ウェブオークションを見ていたときに、作中に出てくるように『父が河原で拾って大切に磨いていた石です』といったような石が出品されていた。これは自分が買わねばならないと謎の義務感にかられて購入したのでした(笑)。いま漠然と振り返ると、すべての行為に意義が問われ、余白がおしつぶされてしまうような世界に抗いたかったのかなあと。それに、誰かが買わないとその石は、そのままただの石として処分されてしまう。それがなんだか歯がゆかった」
現代において見過ごされているものへと、手を伸ばす。それはまさに、須藤が竹内の消息をたどる本作の道筋と重なる。宮内さん自身もフィリピンへ単身赴き、取材を行った。

「ただ過去に目を向けるだけではなく、現代のフィリピンを見てみたかった。二〇五〇年まで人口ボーナス期が続くとされる未来の経済大国ですから、どんな変化の最中にあるんだろう、と。これは私がよくいうことなのですが、視野を広くするために海外に行くのではなくて、視野を『狭める』ために行くんです。文献を通じて必要以上に知ってしまったものの、その広がった枝葉を剪定するようなことですね。作中の台詞にも、現地で強く印象に残った言葉が使われていたりします」
過去も現在も、情報だけは溢れている。そんな中、「自分にとって新たなアプローチで走り切った」と宮内さんが語る一冊は、私たちの日々の肌感覚を軽やかに揺さぶってくれるはずだ。
みやうち・ゆうすけ 一九七九年、東京都生まれ。九二年までニューヨーク在住。早稲田大学第一文学部卒業。二〇一〇年に「盤上の夜」が第一回創元SF短編賞・山田正紀賞を受賞。一二年、単行本デビュー作『盤上の夜』が直木賞候補となり、同年、日本SF大賞を受賞。一三年、(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞受賞。同年、『ヨハネスブルグの天使たち』で日本SF大賞特別賞受賞。一七年、『彼女がエスパーだったころ』で吉川英治文学新人賞、『カブールの園』で三島由紀夫賞受賞。一八年、『あとは野となれ大和撫子』で第四九回星雲賞受賞。