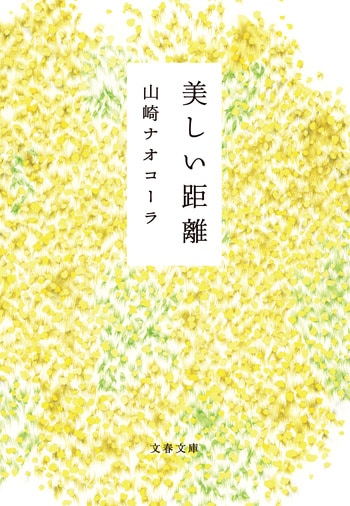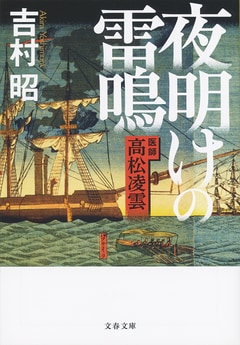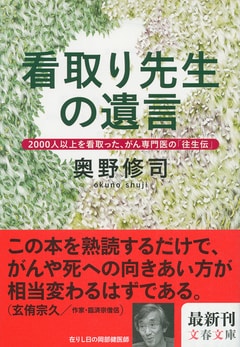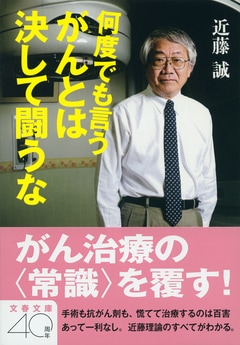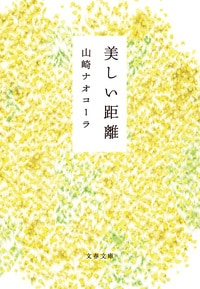
病と死を扱えば、家族や近しい者たちのうちに完結させてしまいがちな物語を、社会とつなげているのも、この小説の素晴らしさだ。
〈仕事は死ぬまで忘れるつもりないし。というか、死んだあとも、仕事のことは考えるから。あのさ、死ぬ人って、死ぬ直前や死んだあとに家族のことを考えている、ってみんなから思われがちだよね? ほら、幽霊とかさ。ご先祖様的な奴って、家族にこだわってる感じあるじゃない? 仕事のことは死ぬ直前や死んだあとは考えなくなるって思われがちなのは、なんでだろう?〉
十三年間、サンドウィッチ屋さんを営んできて、病床でもノートに新しい商品のアイデアを書き溜め、仕事関係の見舞客とその話に興じる妻にとっての、社会人としての世界との関わりがどんなに大事なものであるのかも、作者はきちんと描いていく。妻の思いをよく知る夫は、だから、〈配偶者というのは、相手を独占できる者ではなくて、相手の社会を信じる者のことなのだ〉と考え、葬儀にあたっても、自分が勤めている会社からの手伝いの申し出は断り、妻の友人知人に受付などをお願いする。「父の娘」でもなければ、「夫の妻」でもない。大学を出て以来、社会人としての人生を大切にしてきたパートナーの固有性に、語り手はこだわるのだ。
そんな、常に妻の気持ちを慮り、世間が押しつけてくる物語を慎重に吟味し拒絶することができる、理知的で思いやり深い夫が唯一エゴを垣間見せる場面が、わたしは好きだ。