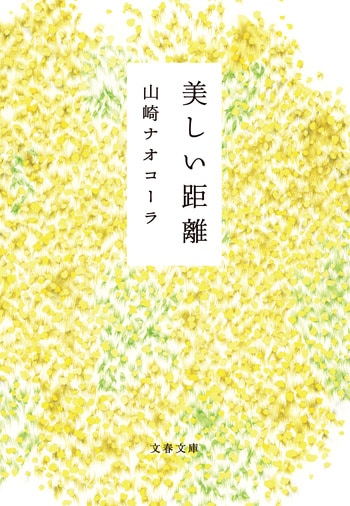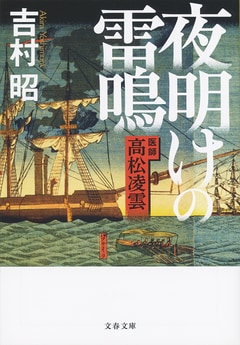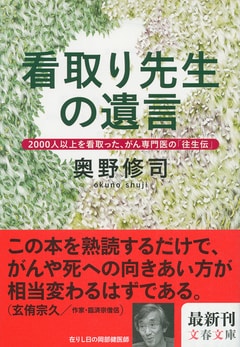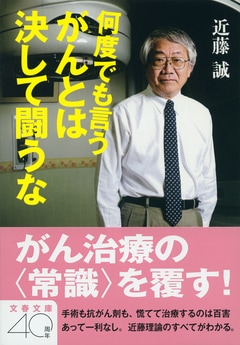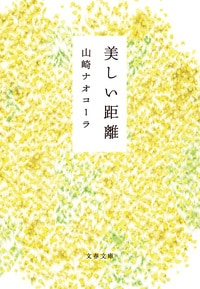
〈こんな風に、こまごまと妻の世話をしていると、横隔膜の裏の裏辺りからふつふつと喜びが湧いてくる。妻にとっては苦しく恥ずかしい時期かもしれないが、こちらにとっての今は、幸せな時間だ。こんな日々がずっと続けばいいのに、とつい願ってしまう。このままずっと、病院で看病をしながら、永遠の時間を過ごせたら良いのに〉
妻が拒否している延命治療をめぐっての医師とのやりとりの中、〈死の瞬間を、大事な時間のように捉えたくない。死の瞬間なんて重要視していない、それのために見舞いに来ているのではない、今のこの瞬間のために見舞っているのだ、と医者にもみんなにも声高に訴えたい〉と心の中で叫ぶ夫が夢見る〈永遠の時間〉を、一体誰が責められるというのだろう。
また、もしかすると、語り手にとっての義父が、妻とは友だち親子である義母とちがって見舞いに来ないことを不審に思う読者がいるかもしれないが、わたしはこの父親の不在についても、書かれていないからこそ胸が締めつけられた。妻の父は、冷たいんじゃない。堪えられないのだ、一人娘が衰えていく姿を見るのが。それがわかっているから、妻は見舞いに来た母親に〈ありがとう、いそがしい中。それじゃ、よろしく伝えてね〉と、「わたしは大丈夫だよ」という気持ちを伝言しているのだ。小説は書かれた言葉だけで成り立っているのではない。書かれていないことにも語らせる力を持った小説こそが、いい小説なのだと、わたしは思う。