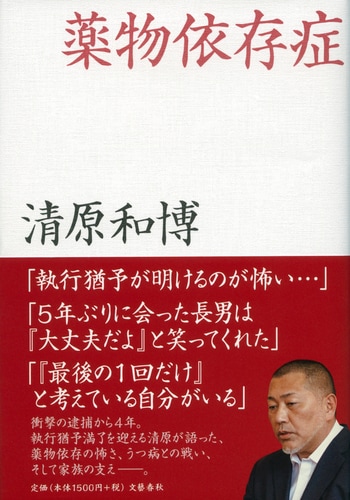薬物依存症――。
この病には特効薬がない。時間によって封じ込めることもできない。
この病の前では意志の力も無力だ。
つまり終わりがない。
そういう意味では6月15日の朝がやってきたとしても何も変わりはしないのだ。
それが清原を憂うつにさせていた。

踏み出すことを怖れる清原に問いかけてみた。
『その怖れや葛藤(かっとう)をそのまま吐き出してもらえませんか』
清原は驚いたような顔をしていた。
『何が自分を苦しめてきたのか。わずかながらでも自分を再生させたものがあったとすれば、それは何だったのか。そして今なお、この先も怖れるものとは何なのか。ひとりの薬物依存症患者として、綺麗事ではなく、この4年の現実を語ってもらえませんか』
事実、清原から発せられるものとして、ありのままの苦悩や葛藤を超えるメッセージはないような気がした。
清原はうつむいたきりだった。
黙ったまましばらく何かをじっと考えていた。
どのくらい時間が経っただろうか。
清原は長い沈黙の末にようやく視線を上げると、小さく頷(うなず)いた。
(『薬物依存症』より抜粋)