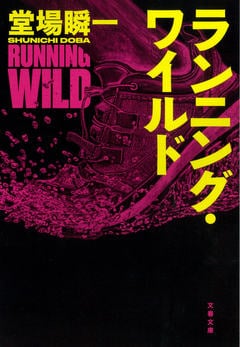その畠山が、病室でひかるに引退の決意を告げる場面がある。
……絶対に泣いてはいけないと思った。自分が泣くわけにはいかない。(中略)彼は一ヶ月かけて、少しずつ現実を受け入れていったのだろう。(中略)彼は一人で、それをやりきったのだから、ひかるが泣くわけにはいかない……。
たまらなかった。
ボクシングとの決別がどれほど苦悩と痛みを必要としたか、教え子のボクシングに賭ける情熱の烈しさを誰よりも承知していたひかるには、わかる。だからこそ、彼女はただ黙って受け止める。そこに慰めや励ましの言葉は、一言もない。そうやって尊厳を守りきった畠山の尊厳を、ひかるは守る。この関係性が……尊い。
本書を読むまで、私の中にはいまだ、あの唐突で残酷な終幕への無念が消えずにいた。あり得たかもしれない“世界”に挑む畠山の姿を時折想像しては、気持ちは塞いだ。何より、見る者を搔き立てるような彼の熱い戦いをまだまだ見たかった。だが、「彼は一人で、それをやりきったのだから」というひかるの言葉を目にしたとき、二人が過酷な現実を決死の思いで受け入れた事実が、その重さが胸に迫ってきた。病室を出て一人になったひかるが、どんな思いでとぼとぼと廊下を歩いて行ったのか。丸めた後ろ姿が見えるようだった。ああ、受け入れる時だ、となぜか自然に思えた。次の瞬間、涙が落ちた。泣けなかったひかるのかわりに、泣いた。
ひかると畠山。二人には言葉での対話は必要なかったのかもしれない。二人はいつのときも弱音も辛さも共有しなかった。こぼすことさえしない。互いの戦う姿勢に、触発され勇気を得ることで、挫けそうになる心を立て直し、前を向いた。絶妙な距離を保ち守り続ける彼らの間には、最後まで甘えも馴れ馴れしさも生まれない。それでいて誰よりも深く理解し、お互いを尊重しあった。
だが不器用でやせ我慢の二人ゆえ、口にできなかった胸の内はきっとあった。その伝えるべきなのに伝えられなかった思いを、著者は推し量り、掬い上げ、丁寧に、誠実に紡いでいく。そうして新たな命を吹き込まれ、再現されたこの作品によって、二人の六年間は改めて幸福な完結をみたのではないか。そう思う。そしてそれは著者の二人に対する誠意と敬意、そして真心があってこそだった、とも思う。
ひかるは自分が報われようとは思っていなかった。畠山の努力が報われることだけを願い、無心に格闘し続けた。その“愛と拳闘”を最もわかっていたのも、畠山だった。
あんたって……強いね。と呟くひかるに、「自分は、その強さを、トレーナーに教わったんで」と畠山は答える。
今はただ、心地よい余韻だけが胸に広がっている。