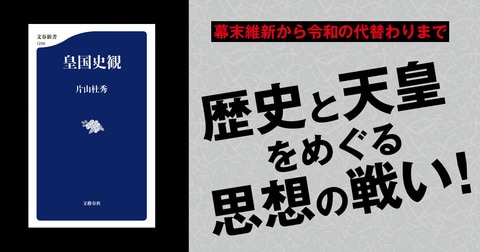さて、本書の内容に入ることにしよう。
日本人が心に思っているけれど、心理的抑圧があって容易には言挙げできないことと言えば、二つのタブーについてしかない。
アメリカと天皇制である。 (「『安倍訪米』を前にした内外からのコメント」)
この一節は、本書の内容と、かつそのモチーフを端的に語っているだろう。「アメリカと天皇制」、そして、そのいずれの考察にも、現行憲法と自民党改憲草案が被って来ざるを得ないというのが、著者が本書で描いている透視図である。
日本人にとって「心理的抑圧があって容易には言挙げできない」二つのタブーを、いま何故論じなければならないのか。それはいずれもが、改憲への危惧と密接につながっているからに他ならない。本書のライトモチーフと言うべきだろう。
著者は私より少し若いが、ほぼ同世代である。天皇制へのスタンスの取り方もとてもよく似ている。「私の周囲には、天皇に対する素朴な崇敬の念を口にする人はほとんどいませんでした。私もそういう環境の中で育ちましたから、当然のように『現代社会に太古の遺物みたいな天皇制があるのは不自然だ。何より立憲民主制と天皇制が両立するはずがない』と思っていました」と述べるところは、私の若い頃の思いとまったく同じである。
著者はそこから「それからだんだん年を取り、他の国々の統治システムについて知り、自分自身も政治的なことにかかわるようになってくると、話はそれほど簡単ではないと思うようになり」、どの国も世俗的権威のほかに「霊的権威」の存在を必須のものとしていることに気づいてゆく。
原理的に両立しないはずの「立憲民主制」と「天皇制」。この「両立しがたい二つの原理が併存している国の方が政体として安定しており、暮らしやすい」というのが、当面の著者の結論であろう。
単一原理で統治される「一枚岩」の政体は、二原理が拮抗している政体よりも息苦しく、抑圧的で、そしてしばしば脆弱です。それよりは中心が二つある「楕円的」な仕組みの方が生命力も復元力も強い。日本の場合は、その一つの焦点として天皇制がある。これは一つの政治的発明だ。そう考えるようになってから僕は天皇主義者に変わったのです。 (「私が天皇主義者になったわけ」)
ここで言う二つの中心とは、霊的権威者として「祭祀にかかわる天皇」と、現世的権威者として「軍事にかかわる世俗権力者」である。両者が互いに拮抗し、葛藤しているあいだはシステムが安定的で風通しがいいが、一方が他方を併呑すると、社会は硬直化し息苦しくなる。すなわち戦前、戦中の状態である。
著者が「私が天皇主義者になったわけ」という挑戦的なタイトルで『月刊日本』のインタビューに応じたのは、平成の天皇が二〇一六年八月に発表した「おことば」に、「天皇制の歴史の中でも画期的な」意味を見いだしたからである。
先に著者自身の言葉を紹介したが、「天皇制」について論じるのは、いわゆる知識人にとっては長くタブーであった。昭和から平成の期間を通じて、なお、天皇制を正面から論じたり、それを肯定する論調は、知識人にあるまじきこととして頭から否定されることが多かった。
内田樹という思想家が、インタビューで「私が天皇主義者になったわけ」を語るという、そのこと自体が大きな事件でもあった。多くの読者が驚いたはずである。それはもちろん内田樹のゆるぎない自信、自恃のなせる業でもあっただろうが、一方で、無責任にタブーとしてその問題を論議の外に置いておく、日本の「知識人」たちに対する警鐘でもあり、論じるべきことを誰かが正面から論じなければならないという、責任感でもあっただろう。