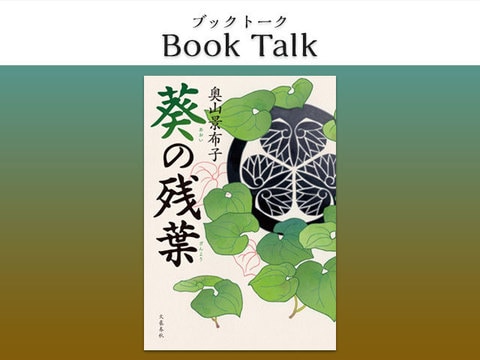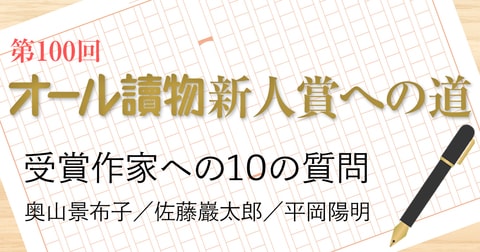乱世を生きる人々の陰影を描く

「最初に書いた短篇『乳を裂く女』は、10年以上も前のものになります。室町幕府の第8代将軍・足利義政の乳母、今参局(いままいりのつぼね)が切腹したと知ったのがきっかけです。当時は決して名誉な死に方でもなかったのに、なぜ切腹を選んだのか、興味を覚えました。執筆当時は、室町時代を舞台にした作品も少なく、読者にも馴染みの薄い時代でしたが、次第に書かれることも増えてきて、この時代の小説を一冊の本として出す勇気が出ました」
本書に収められた6篇は、乱世を生きる人々の陰影を描く。
「応仁の乱で世の中が荒れても、文化は円熟している。それが両立できた時代ということで、意外に人間というのは強いものなのだと、この本で書いたどの人物からも感じました」
中でもすでに「強い女性」としてのイメージが固まっている義政の正室・日野富子の描き方には、奥山さんの筆致がいっそう光る。
「この時代に、女性でお金を稼ぐことの強みを知っていて、やりたいことをやった人です。でも、自分の娘には、それを伝授はしていないんですね」
代わりに、富子から商売の手ほどきを受けるのは、最初は富子を親の仇として狙った少女である。「春を売る女」では彼女の視点から、悪女と言われた富子の別の側面が見える。
意外な顔を見せるのは富子だけではない。苛烈な施政で最後には惨殺された第6代将軍の足利義教(よしのり)や、その息子であり、銀閣寺を遺した義政。毀誉褒貶のある人物たちではあるが、奥山さんはそこに魅力を感じるという。
「権力者の孤独に、興味を惹かれることが多くて。生まれた時から、上に立つことを定められた人の抱える苦悩を想像し、その立場になってみると、彼らも自分なりに生きようとした結果だと思うんですよね。籤引きで将軍に選ばれた義教のやるせなさや、周囲からいろいろ言われて思うようには政をできなかった義政が、自分の美しいと思う景色を凝縮した世界を作ろうとした気持ちもわかる気がするんです」
史実と丹念に向き合う作業を奥山さんは「時代を外す」と表現する。目指すのは、史実の奥底に潜む物語を浮かび上がらせることだ。
「史料にあたり、取材をして、自分の書きたい出来事や人が見えてくると、“時代を外せた”と思うんですね。外した史実の部分が腑に落ちてはじめて、書きたいことが書けるし、外したパーツが物語の厚みになる。今作でもそれができて、書いてきた小説を諦めなくてよかった、間違っていなかったと思える作品になりました」