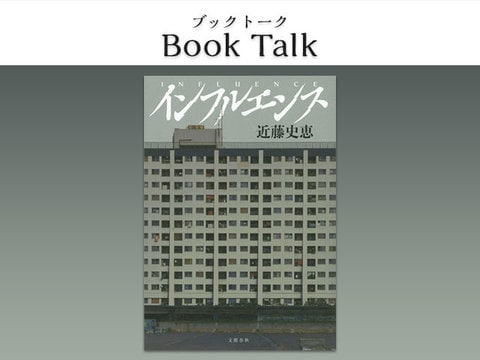さすがに殺人事件はなかったが、加減を間違えば、死に至ったかもしれない暴力的ないじめを、沢山見せつけられてきた。授業がヤジと暴力で崩壊し続け、竹刀を持ったジャージ姿の威圧的な教師たちが勢力を増していったのも同じ。悲惨な事故死もあった。目をそらしてやりすごすしかなかった。生きのびるために。
だれも助けてあげられないということは、だれも自分のことを助けてくれないと同じこと。作品の中で三人の少女たちがかわるがわる口にする絶望は、長い間記憶の底に沈めて来たけれど、まさに私自身が味わって来たものだ。
あれから校内暴力は消失したけれど、いじめはより陰湿化して蔓延し、子どもの自殺も定期的に起きている。思春期に窮地に立たされた友人を助けられず、知らんふりをしなければならなかったという経験を持つ人は、今も多いはずだ。
だれも助けてくれないという気持ちは、年月を経て、誰かに助けてほしかったし、躓いた友達を助けたかったという気持ちに変わっていく。大人になった私たちは、助けを求めてしかるべき場にむけて声をあげることができるようになり、手助けできるようにもなる。現実に助けられること、変えられることは思ったよりもずっと僅かで、女性が傷つけられずに生きることの困難さにも気づかされていくのだけれど。
だからこそ、この作品の「次こそは何をおいてもどんなことをしてもあなたを助ける」という誓いと行動に、涙が止まらなくなる。私だけでなく多くの人の心に突き刺さると確信している。
作者の近藤史恵氏がこの小説の主人公たちと(私とも)同世代であることは知っていたけれど、実際に作中のような公立中学に通っていたのかどうかは、そう重要なことではない。彼女は以前にもロードレースをリアルに観戦したこともロードバイクに乗ったこともないのに、自転車競技を舞台にした名作『サクリファイス』や『エデン』などをものしていらっしゃる。力のある作家というものは、そういうものなのである。
インフルエンスというタイトルについて考える。「影響」と縮めてしまうとピンとこないのだが、「影が響く」と開くとしっくりハマる。三人の女たちがそれぞれの影を踏み合う絵が浮かぶ。友情と呼ぶには仄暗いけれど、離れていても、なにがあっても、ひとりではない。本を開けば、彼女たちがあなたの中に潜み蹲る少女にまっすぐ降りてきて、手を差し伸べてくれるはず。