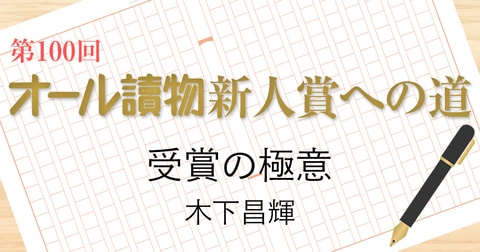木下昌輝氏の歴史小説『宇喜多の楽土』は、この秀家の生涯を取り扱う。関ヶ原の敗戦によって、関係史料の多くが散逸を免れなかったらしく、大名宇喜多氏の内情や秀家の動向にはなお不明点が少なくない。そうした情報の乏しさが、秀家その人への接近を阻んでいる。この二十年ほどで宇喜多氏の実証研究は飛躍的に進んだが、秀家のひととなりは、いまだ遠く霞んでいて、正確に捕捉するような段階にはない。
その風貌を伝える肖像すら伝来がない。元禄年間(一六八八~一七〇四)に彫られた木像の温顔に、かろうじて生前の秀家を知る人々の、何らかの証言が活かされている可能性がうかがえる程度である。昭和後期以後に流布した著名な肖像(岡山城蔵)は、二十世紀の想像に過ぎない。
そうした史料的制約にこそ、創作家の腕の見せ所が生まれるのではなかろうか。秀家の様々な可能性を、いかに創作の世界に蘇らせるのか。絢爛たる前半生と暗澹たる後半生という対比から、類型的な悲劇を紡ぐことはそう難しくあるまい。
「八郎殿の器量は、金将の一歩手前だそうだ」。本書の秀吉は、養女の豪姫の月旦(げったん)として、このような言葉を幼い秀家にかけている。大名としての秀家は結局、「と金」に化けることなく終わったのかもしれない。関ヶ原の敗戦がその政治生命を絶った時、数え年二十九である。その無念を思えば際限がない。
しかし、本書の読後感は思いのほか、さわやかである。血の気の多い時代を描きながら、淡彩的な雰囲気が漂い、秀家の人物像にも枯淡な味わいがある。
ことに没落後の描写に着目したい。「八丈島の暮らしは貧しいが、なにかが足りないということはない。秀家には十分だ」。木下氏の造形した秀家は、過去への執着をほとんど断って、流罪人という境遇を穏やかに受け容れている。だが、それだけではない。「腑抜けの大将」と嘲られたことに対して、秀家の思いであろう、「最初からそのように生きることができれば、どれほど楽だったろうか」という一文が添えてある。みずからは「腑抜けの大将」ではなかった、という自負であろうか。
八丈島に流された秀家には、様々な伝承が残されている。だが、別の機会に指摘したように、その逸話の一部には、語られる時代が降るにつれ、悲劇性を加えて、秀家の境遇をなるだけ惨憺(さんたん)たるものに強調する傾向がある(拙著『論集 加賀藩前田家と八丈島宇喜多一類』桂書房)。
たとえば、大道寺友山(だいどうじゆうざん)(一六三九~一七三〇)の著作「落穂集(おちぼしゅう)」には、若き日に聞いた次のような伝説が書き留められている。いわく、八丈島の秀家が、免罪のうえ「日本の地」に戻り、旧臣花房氏のもとで白米を腹いっぱい食べて死にたいと常々語っていた。それを哀れんだ花房氏が、秀家のために白米を八丈島へ送ってやったという。