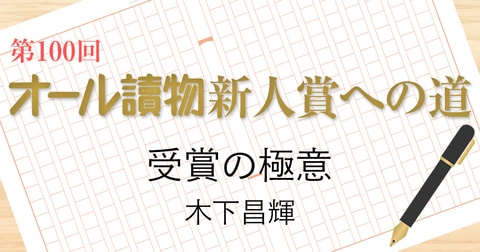この真偽不明の逸話は、寛政三年(一七九一)成立の「南方海島志(なんぽうかいとうし)」にも引き継がれるが、白米を食べたいという言葉は、八丈島において人々から嘲弄(ちょうろう)され、なぶられ、憎まれた秀家が、その艱難(かんなん)のあまりに放ったことになっている。
このように近世の人々は、秀家の無念を勝手に憶測、あるいは増幅して語り継いでいったらしいが、現代に生きる我々も無意識のうちにその陥穽(かんせい)にはまっている恐れはなかろうか。人生のおよそ三分の二を絶海の孤島に過ごした貴種は、なるほど恨みをのんで無念のうちに果てていったのであろうと。
秀家の子孫(らしき人物)をして、徳川幕府への復讐こそ「宇喜多一党に与えられた使命」と語らしめる以下の作品は、そういう想像をたくましくした一例であろう。市川右太衛門(うたえもん)主演・佐々木康監督「旗本退屈男 謎の幽霊島」(東映京都、一九六〇年公開)に、月形(つきがた)龍之介扮するところの宇喜多「ヒデクニ」(漢字表記は不明。映画終盤までは「伴夢斎」を名乗る)が登場する。むろん月形は敵役として「何代重ねた執念か知らぬが」と、右太衛門の早乙女主水之介(さおとめもんどのすけ)に斬り殺されてしまう。個人的には月形の配役と、この敵役が拝む秀家らしき人物の木像に関心が向くのだが、ここで重視すべきは、結束(けっそく)信二の脚本に織り込まれた秀家(やその子孫)の無念や怨恨である。プログラムピクチャーの描写にふさわしく、類型的といえようか。一般大衆のイメージも、かくやと思わせる。
だが、木下氏による秀家の造形はそういう通俗的な想像を許さない。みずからを襲う転変をありのままに受容する。逆境にあっても理性を失わない秀家のしなやかさが、本書には説得力をもって描かれている。
苦難と不幸とは似て非なるものである。秀家の後半生は、確かに苦難の歳月というべきであろう。秀家が築こうとした「楽土」も霧消した。だが、誤読を恐れずにいえば、不幸ではなかったという気息が、木下氏の文章からは伝わってくる。
「ちいさな戦国乱世を、宇喜多家はかかえているようなものだ」。大名当主として未熟な秀家が、領国支配や有力家臣の統制に苦慮した様子を、木下氏はこのように例えている。惣国(そうこく)検地(領国全域の検地)にともなう家臣団の混乱が、宇喜多騒動に向かってゆく描写も手際が良い。
文禄三年(一五九四)に断行をみた惣国検地によって、宇喜多領内における土地の所有権が大名当主、すなわち秀家に一元化された。家臣たち独自の土地支配を否定したうえ、知行地の変更や分散を強いて、秀家の権力は飛躍的に高まった。