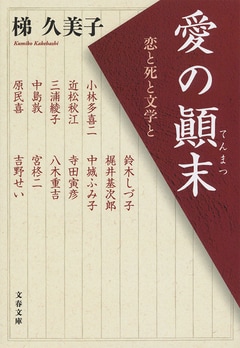その問いとは何か。本書のプロローグの終わりに、それは端的に記されている。
誰を殺すべきか。
誰を生かすべきか。
もしくは誰も殺すべきではないのか。
この三行だけを読めば、「誰も殺すべきではない」と皆が思うだろう。だが話はそう簡単ではない。私たちの社会では、産むか産まないかという命の選択が行われてきたし、いまも行われている。その選択のための検査はますます進歩し、異常があったら中絶することを前提とした出生前診断を受ける人は増え続けているのだ。
*
本書のすぐれた点の一つに、誤診によってダウン症の子を生んだ母親の体験を相対化し、より深く考えるために、医療や法律の面でも広く深い取材を行っていることがある。
そうか、こういう視点もあるのか、と思ったのは、羊水検査を受けて行われる、中期中絶と呼ばれる手術を行う医療者を取材した章である。
中期中絶は人工死産であり、まったくの分娩の形をとって行われるという。それを行う医療者は疲弊し、強いストレスを抱えることになる。言われてみれば当然のことだが、出生前診断と命の選択というテーマを考えるとき、そこまで考えが及んだことが私にはなかった。
この章に、看護師の発案で、中期中絶する母親のために、病院が布や型紙を用意するようになった話が出てくる。赤ちゃんの産着を作るためである。すると、母親のほとんどが、入院期間中に産着を縫うのだという。
〈自分が葬ることを決断した命。それでもせめて何かしてあげたいと思う母親の複雑な思い〉と著者は書く。
そう、複雑なのだ。当事者ではない者の予想をこえて、人の心は複雑である。そのことを突きつけられる思いがした。
取材によって、それまでわからなかったことがわかり、少しずつ、起こったことの輪郭が見えてくる。読者はその過程をともにすることになる。だが、出来のいいストーリーとして構築された読み物(ノンフィクションの書き手はつねに、今自分が書いているものがそうなる誘惑と戦わなくてはならない)のように、カタルシスが訪れることはない。著者とともに事情を知れば知るほど、人の話に耳を傾ければ傾けるほど、問題は複雑さを増し、読者は考えなければならないことが増えていく。本書が読者に与えるのは、理解が深まるにつれて問いが大きくなるという経験なのである。
多くの当事者に、著者は話を聞きに行く。
ダウン症の子を引き取り、里親として育てている女性は、十八歳になって本人が承諾すれば養子縁組をしたいという。家族の一員として暮らし、外でじろじろ見る人に「かわいいでしょう?」と堂々と言えるという彼女だが、もし実子だったらそういうわけにはいかないだろうと話す。障害のある子を生んだのは自分ではないという事実があるからこそ、愛情をかけることができるというのだ。
生まれてから数日しか生きられないことから、ほぼ百パーセントの妊婦が中絶を選ぶ無脳症。この疾患があることがわかっていて出産した女性は、短い時間でもわが子に会えて幸せだったと語る。だが著者にこうも言うのだ。
「この選択ができたのは、どうやっても助かる見込みがない命だったからです」
重い障害を負って生き続ける可能性がある状況だったら、産む決断ができなかったかもしれないという。