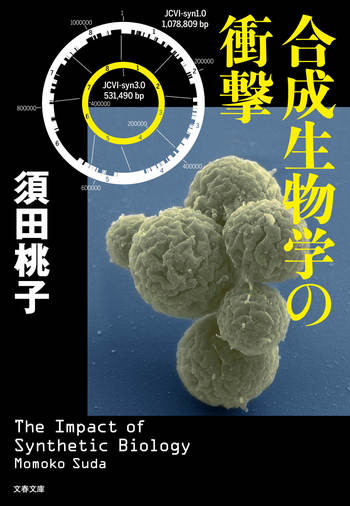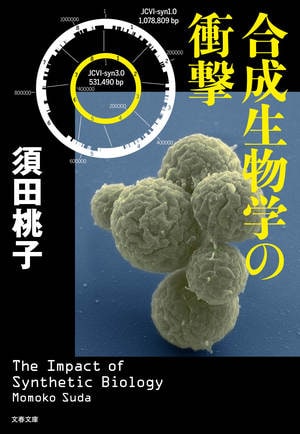
これに関して、須田氏が遺伝子ドライブ研究の先駆者、ケビン・エスベルトにおこなったインタビューは実に印象深い。彼は当初、国防総省からの研究費は受けないと明言していたのだが、その方針を翻し、DARPAのプログラムに応募した。その理由を問われたエスベルトは、自身の変節を「倫理的な選択」だとし、「(遺伝子ドライブ研究に)防衛予算を使えば、その分、爆弾やミサイルへの投資を少なくできる」と述べたという。須田氏も言うように、詭弁に思える。詭弁であるがゆえに、かえって人間くさい。
当たり前のことだが、科学者とて生身の人間だ。ときに妥協と言い訳をしながらアカデミアを生き抜こうとしている。好奇心と同様に、欲望や保身、虚栄心や嫉妬から逃れられないという点でも、市井の人々と何ら変わるところはない。私は科学の世界に物語を見いだす者として、そんな彼らに惹きつけられる。彼らの人間くささこそが科学を生み出し、そこにダイナミズムを与えてきたと信じている。しかし、そうであるからこそ、科学者の理性にすべてを負わせるのは危険なのだ。
結局のところ、「怪物」を暴走させないためには、社会全体の理性を総動員するしかないのだろう。私たちは、この知識と技術の先には何があるのかと、科学者に問い続けなければならない。科学者は、そこに想像力を尽くして人々に伝え続けなければならない。その誠実さを持たない科学者は、いずれ自分の首を絞めることになるだろう。人々の信頼なくして、科学に自由はない。
須田氏が第八、九章で提起する第三の問題は、さらに根源的だ。そもそも人間が、生命の進化を操っていいのか。ホモ・サピエンスという種だけのために、他の種のゲノムを書き換えたり、新たな種を作り出したりする権利はあるのだろうか、という問いである。さらに合成生物学は、我々人間の生殖の原理をも大きく変え得る。優れた遺伝子ばかりを与えられたデザイナーベビー。生物学的な親なくして生み出される人間。臓器を提供するためだけに作られる生命体──。
今の我々にとっては、タブーとも思えることばかりだ。しかし、社会の規範が科学の流れを押しとどめたことは、かつてなかったのではないか。逆に、新たな知識や技術が人々の倫理や規範を変えるということは、これまでにも起こってきた。農耕の始まりが食料の備蓄を可能にし、平等が尊ばれていた社会に貧富の差が生まれたように。産業革命が人々に無限の消費をうながし、それを悪とする価値観が消えてしまったように。
合成生物学の大きな流れによって、私たちはまた何かを得て、何かを失うのだろう。ただし今度の変革は、生物としての人類のあり方を根底から覆す苛烈なものになる。全世界が持ち得るすべての理性を発揮し、傲慢さと向き合わなければならない。可能な限り合意を形成し、流れのスピードと方向をどうにかコントロールしなければならない。さもなくば我々は皆激流に飲み込まれ、後には何も残らないということになるのではないか。
冒頭で紹介したカール・セーガンは、地球外知的生命探査に尽力したことでも知られている。作家としての顔も持ち、異星人との接触を描いたSF小説『コンタクト』はハリウッドで映画化もされた。人類をちっぽけで無知なものと強く意識していたセーガンは、宇宙のどこかにいる「大いなる知性」に教えを請いたいという切なる願いを、その小説に込めたのだろう。
高度に発達した地球外知的文明は、生命の本質に関わるこうした試練を幾度となく乗り越えてきたに違いない。ならば私も彼らに訊いてみたい思いである。私たちが向かう先には、いったい何が待っているのですか、と。
〈参考文献〉カール・セーガン『惑星へ』朝日新聞社、一九九六年