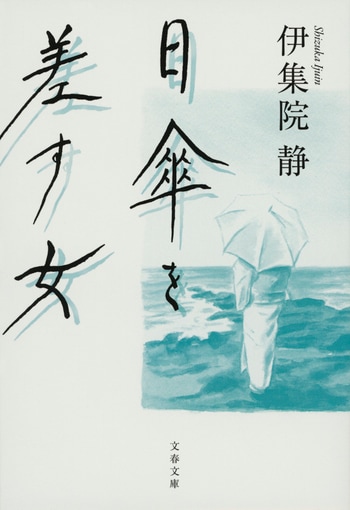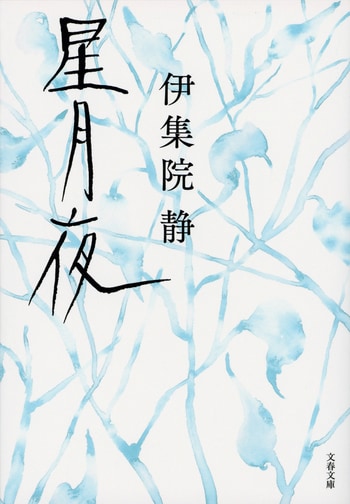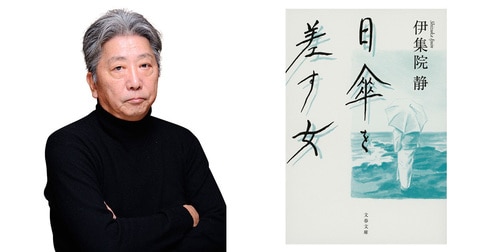一方で、草刈は「人間は生まれて来た時から悪いことをしようと生きる人は一人もいない」という警察官だった父親の教えを引く。「その人が罪を犯した状況を見ると、そこに社会の悪というものに巻き込まれたり、手を染めざるを得なかったりする事情がある。警察官が糾(ただ)すのはその悪の根なんだ、罪人を捕えるのが最後の目的じゃないんだ」というのだ。
ミステリでは、たとえ社会派ミステリでも問題提起を強くするだけで、罪人を捕まえることで小説としてのカタルシスを覚えさせる傾向にあるが、文芸ミステリにはそのカタルシスはなく、社会の悪や悪の根に囚われた者たちの足掻きや苦悩や悲しみを前面に打ち出す。ジャンルとしての推理小説なら、最後に浮上する真犯人の心理に深く踏み込み、サイコロジカル・スリラーへと傾斜するのが普通だが、作者はあえて示唆程度におさめる。前半と中盤に伏線がはられているからであり、屋上屋を架すことを避けたのだろう。日傘を差す女性のイメージが何度となく出てくるが(そのうちのひとつはもちろんクロード・モネの絵でもある)、そこに成熟した美しさと同時に狂気も宿していることは、一読した読者ならわかるだろう。充分にイメージが象徴化され、読者の脳裏に焼きついている。
それにしても、やるせない結末である。こうなるのだろうとは予想はしていても、まさかそこまではしないのではないかと考えていたのだけれど、やはりむごい現実を見せてくれる。『星月夜』の解説でもふれたことだが、作者は逃げずにあえて残酷な状況を提示する。なぜなら人間は「哀しみを抱いて生きる」からである。
それは刑事草刈にもいえる。本書は連続殺人事件を追及する警察捜査小説だが、同時に草刈の苦い過去を掘りおこす物語ともいえる。花柳界に身を沈めた女性とのひそやかな愛の終わりが、よみがえってくるからだ。事件の関係者が目撃する日傘を差す女は、そのまま草刈が過去に付き合った芸子の姿と重なり、芸子がとった行為と同じことを草刈もしようとする。それが罪の贖いになると思ったからだが、それが出来なかった。この罪の意識と悔恨にみちた眼差しをもつ刑事だからこそ、あらがえない運命、ふりかかる不幸をとめようとする者たちの犠牲的精神を深く受け止めて、事件はよりいっそう悲劇性を増すことになる。
この草刈の設定も効果的だが、やはり人間関係や犯罪の動機などを追及しながらも、その背景に目を向けているからだろう。普通のミステリなら、犯人探し(フーダニット)や動機探し(ホワイダニット)に腐心するだろう。それは現代に生きる人間の犯罪として現代人への遡及力を持つけれど、作者の意図はそこにない。温床になった戦後の翳りの多い風俗を浮き彫りにして、そこに至るまでの彼らの出身と環境などを丹念に拾い上げて、戦後の日本社会の縮図を提示している。
大事なのは、人物たちの輪郭ではなく、それぞれがもつ内面、心象風景なのである。つまり、その人間の根底にある心象風景を形作る時代と、生まれ育った地域の自然と風土だ。だからこそ作者は、草刈たちを関係者たちが生まれ育った町へと赴かせる。事件をひもとく新しい情報や知識を求めてのことだが、それ以上に被害者たちが生きて育った場所を描きとる。和歌山と青森の町の住民たちが何度も口にする貧しさ、そこから逃れるための新たな仕事の数々は辛く、厳しい。決して人に誇れるものではないにしろ、必死に生きていく。生きていかざるをえない(人がどう見ようともその姿は尊い)。にもかかわらず、理不尽な運命に翻弄されて、社会の悪や悪の根にからめとられてしまうのだ。
そのような人々の怒り、悲しみ、あるいは奢りと蹉跌が、つややかな風景とともに、読者の身に迫ってくる。地域は限定されているけれど、まるで心の奥に眠る原風景のようにもよみがえってくる。この小説が豊かなのは、切々たる人間模様が、日本の原風景のなかで鮮やかにうつしとられているからである。シリーズ第三弾を期待したいものだ。