「あの戦争」の最大の英雄にして悲劇の人の真実を、半藤さんが熱をこめて語る。役所広司さんが五十六役となり、映画化もされた名作です。今回は一部抜粋して公開!
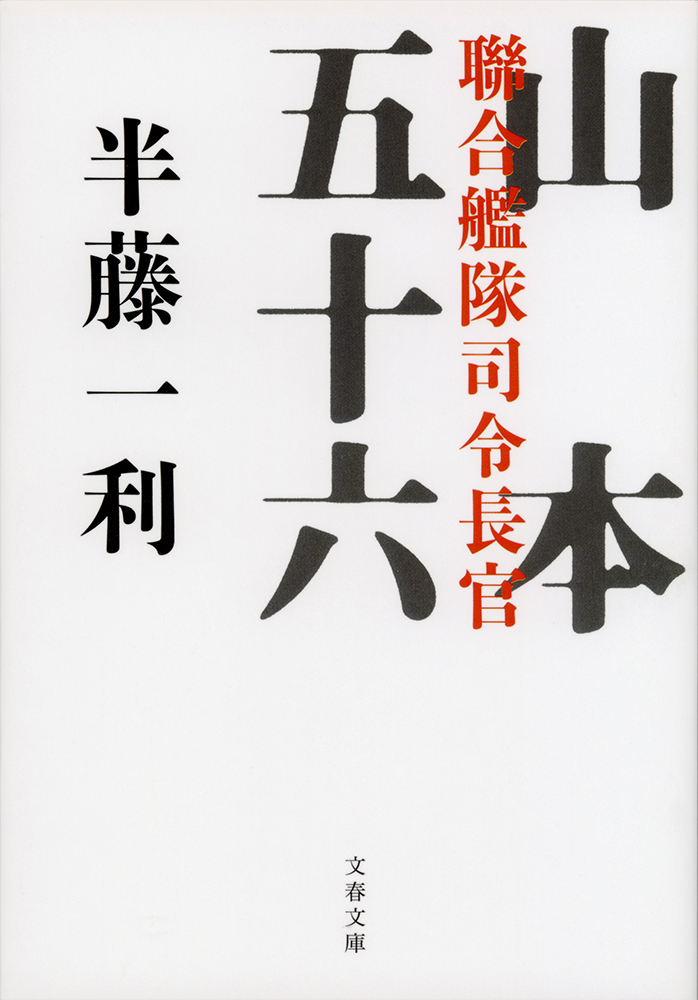
東京・朝のラジオ放送
その日、月曜日、JOAK(現NHK)のラジオ放送は平常どおり午前六時二十分からの朝のニュースではじめられました。香港のイギリス軍が緊急に総動員令をかけたことを伝えただけで、真珠湾攻撃もマレー半島上陸作戦も、はじまったばかりの香港作戦についても、チラリとも触れられていません。六時半から天気予報。が、ここで異変が起きます。突然いつもの天気予報は中止され、レコード音楽が流れたのです。この日から気象管制が全国的に布(し)かれたためとは、まだ国民のだれひとり知りません。
六時四十分から早稲田大学教授伊藤康安の講話「武士道の話─澤庵の『不動智神妙録』」が予定どおり放送されます。伊藤の話が終わって、午前七時の“時報”が流れると、いきなり「しばらくお待ち下さい」とアナウンスされました。どうしたのかといぶかる耳に入ってきたのは、館野(たての)守男アナウンサーの、「臨時ニュースを申上げます。臨時ニュースを申上げます」との声。
かれは抑えきれない興奮をそのままマイクにぶつけました。
「大本営陸海軍部午前六時発表──帝国陸海軍は本八日未明、西太平洋において米英軍と戦闘状態に入れり」
館野は神経をはらってこの短い原稿を二度読んだのちに、「なお今後重大な放送があるかもしれませんから、聴取者の皆様にはどうかラジオのスイッチをお切りにならないようお願いします」と結びました。そのあと七時四分からいつものようにラジオ体操、それが終わった十八分にふたたび「大本営陸海軍部午前六時発表」の臨時ニュースが放送されたのです。
いつもは朗らかなラジオ体操のメロディも、その朝は勇壮な軍艦マーチと愛国行進曲、それから、
〽敵は幾万ありとても
すべて烏合の勢なるぞ
…………
の曲であったように、当時小学五年生であったわたくしはかすかに記憶しています。その朝は、佐渡沖と八丈島南方にあった低気圧は北へ移動し、日本列島はすっきりとした快晴でした。
東京は霜柱の立つほどに冷えこみのきびしい朝を迎えています。寒気を防いで表戸を閉めたまま、どの家もラジオのボリュームをいっぱいにあげ、しきりに奏でられる勇壮な音楽を外に流している。臨時ニュースは七時四十一分、八時三十分、九時三十分……とひっきりなしに対米英開戦の報を送りつづけます。そして都心にはもう鈴を鳴らして新聞社の号外が走りだしていました。吐く息の白さを忘れさせるような奇妙に熱っぽい興奮が、一気に国民全体を包みこんでいました。これは力強くも非合理な感動のほとばしりでした。
あの日の朝、多くの日本人が感激したことを記さなければなりません。わたくしは、ほとんどの大人たちが興奮して晴々とした顔をしていたことを覚えています。評論家の小林秀雄は「大戦争が丁度いい時に始ってくれたという気持なのだ」といい、評論家の亀井勝一郎は「勝利は、日本民族にとって実に長いあいだの夢であったと思う。……維新以来我ら祖先の抱いた無念の思いを、一挙にして晴すべきときが来た」と書き、作家の横光利一は「戦いはついに始まった。そして大勝した。祖先を神だと信じた民族が勝った」と感動の文字を記しました。
この人たちにしてなおこの感ありで、少なくとも日本人のすべてが同様の、気も遠くなるような痛快感を抱いた。この戦争は尊王攘夷の決戦だと思ったのです。
元海軍大将で待従長でもあった鈴木貫太郎は、表情を暗くして夫人に言いました。
「これで、この戦争に勝っても負けても日本は四等国になりさがる。なんということか」

名をも命も
旗艦「長門」では、参謀とともに朝食のテーブルについたときも、いぜんとして、山本長官の顔は晴れようとはしていません。戦いの第一日目の、はじめての食事はいつもとおなじです。ご飯、みそ汁、漬けものの小皿、目玉焼き、のり。戦勝ムードが自然に横溢するなかでは、変わりばえのしない食事でも、味は格別だったはずです。幕僚たちの間の小声の会話もはずみましたが、長官はついに一言も口をきかずにそそくさと食事を終えました。
席を離れるとき、「政務参謀、ちょっと」と、手招いて、長官の公室に入りました。入室した藤井中佐に山本さんは言いました。
「何度も言ったから、君はよくわかっていると思うが、最後通告を手渡す時機と攻撃実施時刻との差を、中央では三十分つめたとのことだが、外務省のほうの手筈は大丈夫なんだろうね。いままでの電報では、攻撃部隊は予定どおりやっていると思うが」
藤井はやや硬い表情となります。三十分つめたことの影響はほんとうになかったのか。山本長官は静かに語をつぐ。
「どこかに手違いがあって、この攻撃が無通告の騙し討ちとなった、というようなことがあっては、申しわけが立たない。急ぐことはないが、気にとめて調査しておいてくれ給え」
藤井参謀は「よくわかりました」と答え、長官公室から出ました。周囲の浮き立つような雰囲気のなかで、長官の冷静すぎるほどの落ち着きが、若い参謀にはむしろ奇妙に映るのです。しかも、何度おなじことを聞いたら納得できるというのか、と。
山本さんは長官公室にあって静かなときをすごしています。幕僚たちもそれをかき乱さない戦前からの習慣を守っていました。食後の一刻に、山本さんは多くの手紙を書くのを例としていました。すべて毛筆書きです。その朝も机にむかってゆっくり墨をすり、筆をとりました。そして半紙に「述志」とまず一行を記しました。
「此度は大詔を奉じて堂々の出陣なれば生死共に超然たることは難からざるべし
ただ此戦は未曾有の大戦にして いろいろ曲折もあるべく 名を惜み己を潔くせむの私心ありては とても此大任は成し遂げ得まじとよくよく覚悟せり
されば
大君の御楯とたたに思ふ身は
名をも命も惜しまさらなむ
昭和十六年十二月八日
山本五十六」
名をも命も惜しまぬと書きました。五十六さんのハワイ作戦とは、部下の海軍精鋭に支えられていたと同時に、いわば名も命も惜しまぬという自己犠牲の精神に根本をおいた最後の手段だったのです。作戦が成ろうが成るまいが、覚悟はひとしかった。あえていえば「必敗の精神」で虎穴に躍(おど)りこんだ。そしていまは、勝利を喜ぶというよりも、悲しんでいたのかもしれません。
あとに、己を待ちうけているのは「死」──それだけである、と。
南雲忠一の帰還命令
午前八時すぎ、「長門」の作戦室には、全幕僚が参集し、機動部隊からのくわしい報告のくる前に、それまでの戦況説明をうけ、司令部としての戦果の判定を行ないました。おおよその判断としては、真珠湾にいた戦艦をすべて撃沈ないし、大破したということになる。しかし、ひとつの艦を二機の攻撃機が視認して、二隻をやっつけたように報告してくる場合があると、ある幕僚が補足して説明しました。
若い幕僚は、作戦に直接参加ならずという切歯扼腕(せっしやくわん)の気味もあって、ひかえめな戦果判定には納得しなかった。冷静派のほうもそれにひっぱられて数字はどんどん大きくなっていきます。しかし、報告によって判断を求められた山本長官は、
「少し低い目にしておくほうがよい」
といい、幕僚の判定の約六割をとりあえずの戦果としました。
ハワイ沖にある各空母では、おなじころ、格納庫内では被弾機が大いそぎで修理されていました。無傷の飛行機には銃弾が補充され、爆弾が搭載されていきます。戦果をより徹底的にすべく、当然つぎなる攻撃隊の発進はあるものと、将兵のほとんどは思っています。
各艦から報告をうけ「赤城」の司令部は、無傷の百七十九機に、修理して使用可能の八十六機を加え、二百六十五機の攻撃隊を発進させうることを確認しました。いぜん大兵力でした。
空母「蒼龍(そうりゅう)」にあった第二航空戦隊司令官山口多聞(たもん)少将は、いつまで待ってもなんの命令もないのにイライラして、南雲司令部に決意をうながすように信号を送りました。
「第二撃準備完了」
麾下の空母は、ともに搭載五十七機のうち「蒼龍」の三十機、「飛龍」の四十三機が健在なのです。艦橋に立つ山口は唇をかみしめながら「赤城」を見やっています。
日本時間の午前八時十五分(ハワイ時間午後零時四十五分)、小雨が降りだしました。「赤城」からは、いぜんとしてなんの応答もありません。航空参謀が「もっと強く、はっきりと意見具申すべきです。やりましょうか」といったとき、山口少将は首をふって、だれにいうともなくつぶやきました。
「南雲さんはやらないよ」
そうです、その南雲は司令長官室で、ひとり沈思をつづけています。脳裏では永野総長の「空母を沈めないように」という指示が明滅していたのかもしれません。
時計が日本時間午前九時を過ぎたとき、ハワイ北方海上ではひとつの決断がくだされようとしていました。空母「赤城」の士官室で、第二撃はあるものと思いこんでいる淵田中佐が、ひとしきり自慢話に花を咲かせたのち、腹がへっては戦ができぬと、ぼた餅をひとつ頰張ったときでした。艦内高声令達器が、
「戦闘機だけを残し、他の飛行機を格納庫に収容せよ」
と、司令部の命令を伝えました。血気の将兵たちがいったいどうしたことかと訝(いぶか)しく思う余地も与えないように、機動部隊全艦の舳(へさき)は北に向きだしました。
「第三戦速二十六節(ノット)に増速、北上す」
南雲長官が、草鹿参謀長の進言もあって、ついに決断を下したのです。南雲の結論はこうでした。
「所期の戦果は達したものと認める。第二回攻撃を行なっても、大きな戦果は期待しえないであろう。よって帰還する」
覚悟していた味方空母の喪失は一隻もない、そして望外な戦果をあげた以上、敵基地航空兵力の攻撃圏内にいつまでもとどまっていることはないと。
こうして午前九時三十五分(日本時間)、機動部隊は真珠湾の真北百九十浬まで接近したあと、いっせいに回頭、高速で去っていきました。
アメリカ側の死者は最終的に二千四百三人(うち民間人六十八人)にのぼりました。戦艦四隻が沈み、同四隻が大破着底。現地で修理可能なのはわずか二隻でした。軽巡三隻、駆逐艦三隻、補助艦三隻が撃沈または大破されました。標的艦ユタも沈没。飛行機の喪失は海軍百四機、陸軍百二十八機でした。
対する日本側の損害は、艦載機二十九機、特殊潜航艇五隻だけでした。
栄光の日は急ぎ足で去っていきます。日没も近くなって東京の気温は急速におちていきます。六十二歳の作家永井荷風は、この日の朝に、小説『浮沈(うきしずみ)』を蒲団のなかで書きました。大戦争のはじまったいま、まったく発表のあてのなくなったことを知りながら、原稿を書きついでいましたが、夕暮れちかくなって町に出ます。その日記にはこう記されています。
「日米開戦の号外出づ。帰途、銀座食堂にて食事中、燈火管制となる。街頭商店の灯は追々に消え行きしが、電車自動車は灯を消さず、省線は如何にや。余が乗りたる電車、乗客雑沓せるが中に、黄色い声を張上げて演舌をなすものあり」
この日ばかりは、駅頭の夕刊(九日付)はすっかり売り切れました。戦争は新聞のよき栄養剤で、人びとは一枚の新聞に頭を寄せ合って、むさぼり読みました。昨日までなにかと不平不満をいっていたのも忘れ、だれもが真から愛国者のつもりになったのです。日本中が“捷報(しょうほう)到る”で有頂天でした。
そうした熱狂のなかにも冷めた人もいます。ちょうど新宿の映画館の昭和館では、アメリカ映画「スミス都へ行く」を上映していました。アメリカの民主主義のすばらしさを描いたこの映画の観客が、なんと、その夜十人ほどいたというではありませんか。
夜の「長門」作戦室
午後九時を迎えようとするとき、太平洋上の「長門」の作戦室では激論が戦わされていました。機動部隊による真珠湾再攻撃案が、黒島参謀によって強硬に主張されていたのです。これに宇垣参謀長が猛反対しました。
「機動部隊はもはや戦場からずいぶん離れてしまった。一杯一杯のところで作戦を終えて離脱しようとしているものを、もう一度立ち上がらせるためには、これを怒らすよりほかに方法はない。統帥の根源は人格である。そんな非人間的な命令を出すことが、どうしてできるものか」
ほかの参謀もこもごも口をはさむ。
「われわれは軍人です。武人として、この戦機を逸することこそ、どうしてできるというのですか」
「こんどは無謀な強襲となる。戦機とはそういうものではない」
「いや、強襲とは無謀なものです。艦隊を危険にさらしてでも敵の全滅を期すのが本作戦の目的です」
「違うッ、戦機は去ったとみるべきである」
「戦果は徹底すべきであります。叩きに叩く、叩いて叩いて叩きまくる」
「敵飛行機の損害程度が不明のまま突っ込ませれば、かならず大きな痛手をこうむる。将棋にも指しすぎということがあるではないか」
「しかし、米太平洋艦隊が実際に行動不能におちいったかどうか、今後の作戦上、その疑いをとりのぞくためにも、再攻撃を加えてみるべきであります」
「空母が残っているんだぞ、空母が」
「その敵空母をこのさい撃破しておくためにも、もう一度攻撃を……」
山本五十六長官は腕を組んだまま論戦を見守って、ひとことも発することはありませんでした。その山本に最後の決を求めるかのように、宇垣が口を開きます。
「やはり、見送るよりほかないと思いますが」
五十六さんは苦渋の色をありありと浮かべながら、深くうなずき、こう言いました。
「もちろん、再撃につぐ再撃をやれば満点である。自分もそれを希望するが、南雲部隊の被害状況が少しもわからぬから、ここは現場の機動部隊長官の判断にまかせておくことにしよう。それに、いまとなっては、もう再攻撃は遅すぎる」
この決定で、機動部隊にたいする「再度攻撃」の電報命令は、ついに打たれることはありませんでした。勝利の一日は完全に去っていきます。国民を狂喜させた真珠湾奇襲という破天荒な作戦は、ピリオドを打ったのです。
「いわなくとも、やれるものにはやれる。遠くからどんなに突っついても、やれぬものにはやれぬ。……どろぼうだって帰りは怖いよ」
さらにもうひと言、
「戦(いく)さはこれからだ。さあ、どうするか。いい考えはあるか」
そう言い残して山本さんは作戦室を出ていきました。
在米外務官僚、世紀の怠慢
十二月十日、フランス領インドシナに基地をもつ海軍陸上攻撃機隊は、マレー沖でイギリス東洋艦隊の最新鋭プリンス・オブ・ウェールズとレパルスの両戦艦を撃沈します。司令官フィリップスは幕僚の強い退艦の要請を斥(しりぞ)け、「ノーサンキュー」と言って少しもあわてず、艦と運命をともにしました。
この攻撃を指揮した南遣(なんけん)艦隊司令長官小沢治三郎中将は、その翌日、わざわざ二機の陸攻機に命じ、激闘の潮騒なお消えやらぬ海に、機上から花束を投じました。山本長官がそのことを聞いたとき、開戦いらいきつく嚙みしめていた唇をひらいて、はじめて莞爾として微笑んだといいます。
とにかく相次ぐ大戦果です。ラジオは大きな戦勝ニュースを報ずるときには、陸軍の場合には分列行進曲、海軍の場合は軍艦マーチ、陸海共同では「敵は幾万ありとても」の軍歌や行進曲を前後につけて勇壮に報道し景気づけました。大本営発表を、陸海は競い合っているありさまとなり、街の電気店のラジオの前には黒山のひとだかりのできる毎日となっていました。戦争が祭り気分の陽気さですすめられていきます。こうなっては早期講和など夢のまた夢、というよりも、口にすることが愚の骨頂となりました。
そうした有頂天の国民的熱狂を、山本五十六は苦々しい思いで見ています。それとともに、戦闘が日常と化したあとになっても、ほんとうに開戦通告が予定どおりに手交されなかったのかどうかを口にもだして憂慮していました。ルーズベルトが議会演説やラジオの談話で、「騙し討ち」(sneak attack)と、低いが声量のある声でまくしたてているのを短波放送で聞いていらい、その疑いを消せないでいるのです。その後も、たえず短波放送は、真珠湾の無通告攻撃に激昂し、アメリカ国民はいまだかつてないくらい団結を示し、報復を誓う声が澎湃(ほうはい)として起こっている、という意味のことをしきりに報じています。そのたびに、山本さんは将棋を指す手をとめて、じっと耳を傾け、そして表情をみるみる暗くしたのです。
謀略の疑いをもって聞いていたアメリカの放送でしたが、どうやら最後通牒が遅れたことは間違いないようだと山本長官が知ったのは、その年の暮れか、昭和十七年に入ってから間もなくであったといいます。
開戦の通告文は四千語以上に及ぶ長文となったため十四部に分けられ、アメリカ時間の六日から七日午前零時二十分までに英文で発信されています。東郷外相は、その受領後の取り扱いは注意を要しかつ極秘であること、そして、訓示がありしだいいつでもアメリカ側に手交できるように万端の手配をしておくようにとのメッセージを在米大使館に送っています。ところが、大使館員たちは、これ以上のお粗末はほかにないであろう無能ぶりを発揮したのです。
この日(六日)アメリカは土曜日。その夜はふたつに分かれて小宴がはられていました。残された電信課員の六人も、日が落ちるとあっさりと仕事をやめ夕食をとるべく大使館をでています。午後九時半すぎ、食事をすませ電信課員たちはようやく戻り、ぶつぶつ言いながらもふたたび翻訳作業にとりくみ午後十一時すぎに、対米覚書十三部の解読を終了しました。
そして、このあとに到着するいちばん肝腎な第十四部を解読し、アメリカ政府へ通告するまでの経過が無残この上ないものとなります。タイプ打ちが間に合わず、ついには、開戦通知がアメリカ国務長官のもとにもたらされたのは、日本の機動部隊が真珠湾を爆撃してから一時間後という失態となってしまったのです。それは誤判断と気のゆるみ、そして怠慢によるとされているのですが、じつは日本外交の本質にかかわる問題でもありました。
なんとなれば、日米交渉は野村吉三郎と来栖(くるす)三郎の仕事として、大使館員たちのほとんどは無関心を装いつづけていたというのです。これぞ官僚的といえそうなセクショナリズムでした。憎っくき野村の手助けなど御免蒙(ごめんこうむ)るというケチな料簡(りょうけん)があったにちがいない。親身ならざるがゆえに、東京から送信されてきた長文の対米覚書が最後通牒となる可能性など、かれらは思ってもみなかった。となれば、最後の第十四部がなにを意味しているかを理解することなく、どうせ今夜は来そうもないから、明日の仕事にしようと勝手に判断して土曜の夜を楽しむことに、あいなったのです。
その結果は、東郷外相がその著書に悲憤をもって記しました。「通告時の怠慢は国家の非常なる損失、万死に値する」と。まさにそのような失態でした。
山本さんは、心を許した幕僚にだけはしみじみ語りました。
「残念だなあ。僕が死んだら、陛下と日本国民には、聯合艦隊は決して初めからそういう計画をしておりませんと、そうはっきりと伝えてほしい」
亡国へと導くとわかっている戦争を、なんとしても止めたかった。そのために最大の努力はしたが、努力むなしく、無謀な戦いを先頭に立って粉骨砕心せざるを得なくなった。ならばせめて、国際法規の定めるところに従い、事前通告をしてから正々堂々と戦いたかった。無念であったと思います。
作戦参謀三和義勇中佐が山本さんの言葉を聞いています。
「日本のさむらいは、たとえ夜討ちをかけるときでも、ぐっすり寝こんでいるやつに斬りつけることはしない。少なくとも、枕だけは蹴って、それから斬りつけるものだ。最後通牒を手渡す前に攻撃したとあっては、日本海軍の名が廃(すた)る」
切ない最後の信念。山本五十六はついに武人としての美学をとおすことさえも阻まれたのです。

















