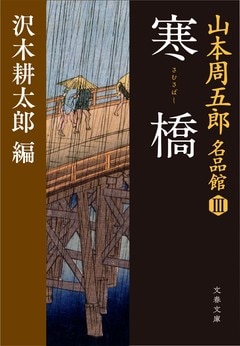I
こんど谷崎潤一郎の評伝並びに作品解説の筆を執るに当って、氏の半世紀の長きに亙わたる作家生活が生み出した夥おびただしい数の小説、随筆類の主なものを読み返してみる機会を持った。「少将滋幹の母」「細雪」「鍵」「瘋癲老人日記」等、終戦後に発表されたものは、それぞれそれを読んだ時の記憶もまだ鮮やかで、再読してさして前の印象を改めることもなかったが、それ以前の作品は若い時読んだままになっているものが多く、記憶も曖昧で、中には初めて読むような思いを懐かせられるものもあって、こうした通読の機会を持ったことは大変いいことだったと思う。その代り、長く宝石箱の中に仕舞い込んでおいたものが、取り出してみると意外に輝きを失ったものに変じている場合もあって、そうした時は損をしたような気持にもなったが、またその反対の場合もあった。私は今まで大切に仕舞い込んでいた幾つかの宝石を失い、その代り新しい幾つかの宝石を得た。
新しく得た宝石の中で最も大きいものは「瘋癲老人日記」である。これは発表当時読んで、氏の代表作の一つに算えるべきものであるとは思っていたが、こんど再読して、と言うよりは氏の八十年の生涯の果てに置かれている作品として改めて読んで、前とは比較にならぬ程の強い感動をこの作品から受けた。この作品に於てみる谷崎潤一郎という作家の老成の仕方というか、解脱の仕方というか、ある到達点への到達の仕方は非凡であると思った。このように不逞不逞しく、同時にまた気楽に死の前に居坐った人間のあるのを私は知らない。
「瘋癲老人日記」は言うまでもなく、死と性を取り扱った小説で、主人公は老人である。作者は老人の持つあらゆる要素を抽出して、それで一人の人造老人を作り上げ、その老人に死と格闘させ、性と格闘させている。
「瘋癲老人日記」は、氏がそれまで書いた作品の系譜に於てはどこにも席がない。前期のいわゆる悪魔主義の作品と称せられる一聯の作品とも、また「蘆刈」「吉野葛」等に見る古典美の世界とも、「陰翳礼讃」に見る美意識とも、上方文化への傾倒を美しい絨毯模様に織ってみせた「細雪」の世界とも、それらの孰れとも異ったところに坐っている。それでいて、この作品はそれまでの氏の作品と全く無関係かというとそうではない。女性崇拝や被虐症的なものは、氏がどの作品に於ても護符のように離さなかったと同様に、この作品に於てもまた離してはいない。西洋趣味も古いものへの憧憬も、それぞれ今までとは違った頗ぶる無造作な形ではあるが、そこにちゃんと投げ込まれている。大体作品の主題そのものが氏にとって決して新しいものではないのである。
それでいて出来上がった作品は全く従来のどの作品とも違っている。一種の抽象小説とでも呼ぶべきものである。氏は自分が持っているすべてのものを投入して、全く異った作品を最後の作品として遺したのである。それならどこが違っているのであろうか。それははっきりしていると思う。この作品における氏は何ものにも酔おうとしていないし、酔ってもいないのである。私は氏が自分のものをすべて投げ込んで、自分が訳した「源氏物語」からも取り得るものは取って書き上げたものが、「少将滋幹の母」であり、これこそ作家としての氏の完成を示すものであると信じていたが、氏はそのあとにもう一つの行き着いた世界を作品に遺しているのである。「少将滋幹の母」は私たちが知っている谷崎文学の集大成であり、それのみごとな完成であるが、「瘋癲老人日記」の方はいささか趣を異にしている。これは作家としての氏が八十年生きた果てに小説の形に書いた人生の決算書とでも言うべきものではないかと思う。氏はこの作品で初めて何ものにも酔っていない醒さめた自分を示している。主人公の老人を美女の足型を刻んだ重石の下に眠らせようとする作者の思いつきは、確かに作者らしくはあるが、もう氏のすべての作品にあった陶酔はない。氏はこの作品に於て少しも変貌はしていない。あくまで谷崎潤一郎である。ただ氏は氏を一生支配したものから、谷崎文学を形造ったそれこそ沢山の谷崎的なものから、解放されてはいないが、自由になっているのである。