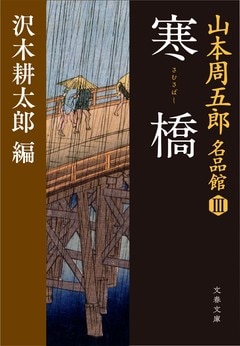「春琴抄」も「盲目物語」も「蘆刈」も多くの谷崎ファンを作った。それを作るだけの読者を魅するものがあった。エロチシズムのむんむんとする初期の作品にも、亦同じものがあった。「瘋癲老人日記」にはもはやそうしたものはない。ある作品を読んで、それに魅せられ、作者に会わずにいられないような思いを持つ、そうした型の読者とは、「瘋癲老人日記」は無縁である。また作者の人生感や人生哲学に傾倒する、そうした読者をも亦、この「瘋癲老人日記」は受けつけないだろう。身につまされるものなどみじんもないのである。文学が読者に何らかの感動を与えるものだとすれば「瘋癲老人日記」も亦そうしたものであるに違いないが、ただその感動はかなり厄介な困ったものである。人生いかに生くべきかとは無関係な感動である。人生はさして尊くもないし、生きる価値のあるものかどうかは判らない。併し、死と顔をつき合せた人間の行きついた姿は、よかろうと悪かろうとこのようなものである。作者はこの作品でこのように言っているように見える。しかも、それを難しい顔はしないで投げ出しているのである。見たい人は見ろ、見たくない人は見るな。作者はそういう態度をとっている。
と言って、片意地になったり、ひねくれたりしているところは少しもない。自分が生れつき持っているものは、相変らず後生大事に持っているし、自分以外の何者にもなっていないのである。ここにいるのはやはり「刺青」を書いた作家であるし、「春琴抄」を書いた作家である。ただ同じ作家であるが、すっかり醒めて円満具足の表情をとっていることだけが違っている。氏もいつ醒めたか自分でも知らないかも知れない。書いてみたら、ひどく身も蓋もない形でそこに醒めている自分を見出したのかも知れない。
私は氏は不思議な老成、解脱の仕方をしたと思う。いかなる作家もしなかった独自な人間完成である。氏は人間として高く完成したか低く完成したか知らない。併し、これだけははっきり言えると思う。氏が書いた「瘋癲老人日記」の主人公こそ、氏が書いた人物の中で、誰にでもすぐ人造人間と判りながら、しかも一番生き生きと生きているのである。
氏は第一作を発表して以来、誰も知っている通りずっと天才作家の名をほしいままにして来ている。併し、私は氏を天才と感じたこと、この作品に於けるほど強かったことはない。
谷崎文学の大きな流れは、「刺青」に源を発して、「瘋癲老人日記」にまで達したのである。「瘋癲老人日記」を到達点に置いてみると、私には大きな俯瞰を持った谷崎文学はまた違ったものに見えてくる。豊かな水量で移動していた水の流れがついに河口を見付けて、流れの途中にあった瀬や淵が急に波立ち騒いでくるような、そんな思いを懐かせられる。
続きは本書にてご覧ください。