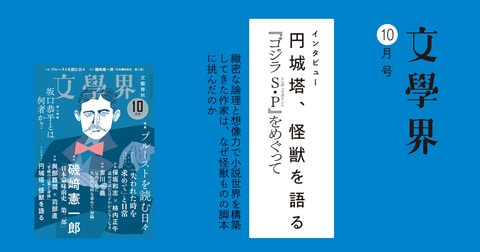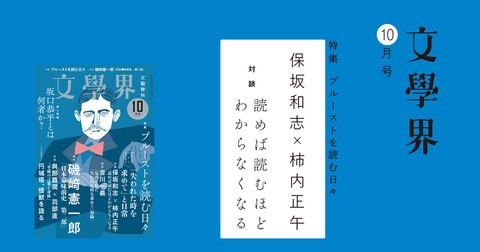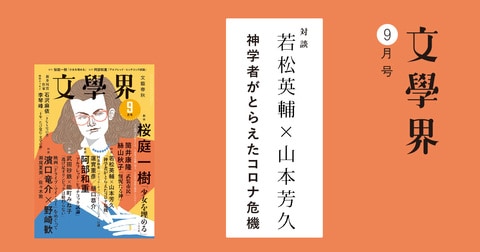着いてみるとやっぱり空港は陸の孤島、まるっきり無政府地帯で、わたしは飢えて、昼にたべたラーメンの汁を残してしまったことを悔やむ日が来るのだろうか。そんなことをぼんやり考え、でも頭上の物入れには職場のお土産に買った白い恋人というお菓子も入っているし、いざとなったら白い恋人を少しずつ齧りながら生き延びてみよう、と密かに心を決めた。思い出してみると、八年前のあの事故の後も、周りのみんなは第二、第三の惨事を恐れてすぐに食料と飲料の買占めに走り、スーパーマーケットもコンビニエンスストアもしばらくの間は商品が払底してしまっていた。でも、郊外の団地の一室に住むわたしの恋人ときたら、
「自分の部屋の周りにどんどん物資が蓄えられていくと思うと心強いよ、俺は」
と言って、つるりとはげた頭をほてらせ、ほのぼのと笑っている始末だった。そんな考えの甘い恋人を前に、ゆで卵一個をめぐって親兄弟が殺し合いをすることだってあるんだから、と舌打ちをしたわたしだったのに、いま、無謀にも、甘いお菓子の恋人一箱と飲みかけのお茶のペットボトルだけで、一万三千人が閉じ込められているという陸の孤島へ飛び込んで行こうとしている。
「あの」
と声がして目を開けると、声の主は隣の席の若い女で、泥の中に咲く花のように美しく、彼女を蓮姫と勝手に名付けることにし、ひとまず、
「はい」
と返事をすると、
「これから大宮の二つ手前の与野本町という駅まで帰るのですが、今晩中に帰れるでしょうか」
と不安そうな声が返ってきた。
蓮姫もあのことを知っているのだと思うと孤立感もいくらか和らいだが、そういう安心感よりも、なぜかこれは罠かもしれないという直感的な不信がまさってしまう。
「無理に決まっていますよ」
そっけなく答えてから急に後悔し、あわてて、
「そこは、遠すぎます」
と付け足した。
「そうですよね」
蓮姫はしょんぼりとうつむいて、きれいにマニキュアを塗った指をいじっていたが、しばらくすると、「どうしてこの便の航空会社は何も案内しないんでしょうか、無責任ですよね」とちょっと怒ったように言った。
わたしは責任という言葉を聞くと鼻の穴の中や目の周りの粘膜が赤く腫れてかゆくなるたちで、その時もかゆくなりそうだったので、「何も、って、何のことです?」とひとまずとぼけた。
「あなたも、知ってるんでしょう?」
「えっ。何のことでしょう」
蓮姫はあたりを見回し、ためらうように声を低めて、
「現地のことですよ」
と低く言った。
「わたしは何も知りません。到着地の状況について案内がないのは、カクヤス航空券だからじゃないですかね」
とわたしは言った。いつの間にか旅客機は雲の上に出ていて、わたしたちは闇のなかにぷかりと浮んでいた。分厚い小窓から外を見ると、西の空はほのかに明るく、遠くに長い雲が、魚屋の店先のように並んでいる。
「ああ、暑い」
と不意に蓮姫が言い、そう言われてみると機内は空気が乾燥している。わたしは目の前の糊のきいたかたい布きれの上に突き出す脂っぽい頭髪を見つめ、眠気が波のように襲ってくるのを感じていたが、隣で蓮姫は「暑い、暑い」とつぶやき続け、とうとう耐えきれなくなったのか、「ちょっとすみません」というなり、わたしの足元にある、座席の背についたポケットに手を伸ばした。
そのポケットに、わたしはジャスミンティーのラベルの貼られた500mlサイズのペットボトルを入れていたが、蓮姫はそれを勝手につかみ出し、許可も得ずに中身をのみほしにかかった。とろりと重く揺れる液体はボトルのなかばあたりまで入っていて、飲み終わったとたん彼女は激しくむせた。蓮姫が苦しい咳の下から、
「これ、お茶じゃないですよね」
と非難がましい目を向ける。そういうところを見ると、まだまだ銘柄までは当てられないウブさが残っているらしいなと自然に察せられるのだったけど、まずは、
「ボトルのまま、機内に持ち込めるはずないでしょう」
と呆れた。それでも納得しない様子なので、
「勝手に人の飲みものを飲むからですよ」
と付け足した。
次に目を覚ましたときには蓮姫の姿はすでになく、代わりに子馬のような印象の肌の浅黒い、目つきの鋭い少女が座っていた。少女の服から焦げくさいような煙のにおいがして、それで目が覚めたらしかった。
蓮姫はどこへ行ったのだろう、各駅停車の、途中の駅で降りてしまったのか。新千歳空港の出発ロビーで聞いた「陸の孤島」という言葉が不意に蘇り、また少し不安になったけれど、わたしは昔から自分よりも弱く、世話をしてやらなければならない存在があると俄然はり切るタイプだった。
「空港に着いたら、どこまで行くの?」
とさっそく、少女に話しかけ、しゃべりながら何気なく指を伸ばして開いた膝の上の黄ばんだ文庫本には、しおり代わりの名刺が挟まっていた。
「Editor kumiko」
一体、いつもらった名刺だろう。このときわたしは、煙のにおいを漂わせた少女を、「クミコ」と呼ぶことに決めたのだった。
この続きは、「文學界」10月号に全文掲載されています。