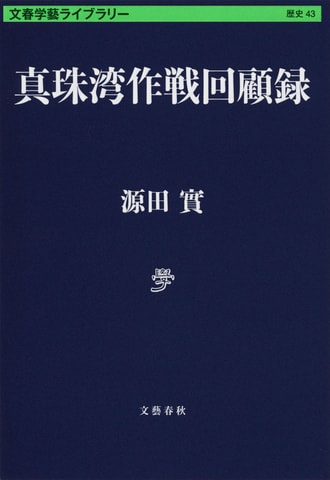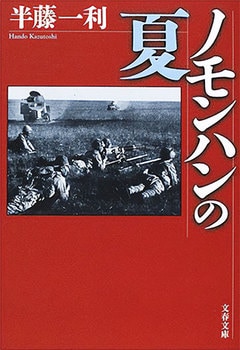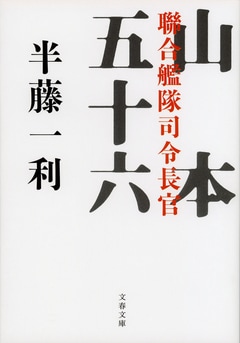著者の源田實氏が亡くなって十年になる(注:文庫旧版刊行時)が、私は参議院議員時代の氏に何回か会う機会があった。小柄だがひきしまった体軀、鷹のような鋭い目、若き日の海軍戦闘機乗り時代の風姿は最後まで変らなかった。
寡黙の人ではあったが、文章家でもあった。しかし講談調のベストセラーを次々に書いた陸軍の辻政信大佐とはひと味ちがう。海軍と陸軍の差かもしれないが、人柄の違いでもある。源田氏には、飛行機というメカに密着する職人的な律義さと謙虚さが漂っていた。
大尉時代に今の「ブルーインパルス」の前身ともいえる「源田サーカス」をひきいて華麗な空のページェントを見せた源田は、戦後航空自衛隊のジェット・パイロットに転身した。そして六十歳に近い航空幕僚長時代に機種決定のため渡米したとき、候補機のロッキードを自身でテスト操縦して、国民をアッと言わせる。その名声を背に彼は参議院議員へと転身するのだが、源田實の劇的な生涯のハイライトは、何と言っても本書の主題となった真珠湾攻撃であろう。
「真珠湾」は、世界戦史の一ページを占めるモニュメントの域にとどまらない。その日から五十数年が経過したが、依然として日米間にわだかまる政治的・心理的トラウマでありつづける。「ノーモア広島」と「リメンバー・パールハーバー」の対句が相殺された形で微妙なバランスを保っているが、第三者からゆさぶられれば、いつ噴出するか見きわめがつかぬ「不発弾」的存在でもあるのだ。
その歴史的舞台に、源田は海軍中佐、第一航空艦隊航空(甲)参謀という資格で参画した。司令長官は南雲忠一中将、三百六十機の飛行隊をひきいたのは、海軍兵学校同期生の淵田美津雄中佐だから、源田はシナリオ・ライターとは言えても、あくまで「黒子」の役だった。だがこの「黒子」は単なる「黒子」ではない。
よく知られているように、真珠湾奇襲という壮大なプロジェクトは、山本五十六連合艦隊司令長官の脳裡から生れた。着想はすでに一九二七年頃からとの説もあるが、具体化したのは四〇年秋頃である。
だが日露戦争以降、西太平洋における迎撃決戦を想定してきた日本海軍にとって、山本の提案は常識の範囲を逸脱していたから、海軍省や軍令部をふくむ上司、同僚、部下の多くは拒絶反応を見せた。南雲に至っては、ハワイへ向う途上でさえ動揺していたほどである。
それは山本の予期するところでもあったから、彼は正式提案に先だち大西瀧治郎少将(基地空軍の第十一航空艦隊参謀長)へ意見を求め、大西は源田を呼んで検討を依頼する。真珠湾攻撃の十カ月前に当る一九四一(昭和十六)年二月のことである。
山本はあえて連合艦隊司令部の幕僚を避け、指揮系統を無視して変則の人脈で原案作りをやらせたわけで、大西は山本の「腹心」、源田は大西の「腹心」という関係だが、この「同志的結合」関係はやがて参加チームの編成にも応用される。淵田や村田雷撃隊長の指名引き抜きもそうだったし、水平爆撃の名手をえらぶときには下士官パイロットにまで及ぶ。
さて源田は大西から山本の手紙を見せられたときの印象を、「うーん、偉いことを考えたものだ、一本とられた」と回想している。おそらく大西も同じ思いだったのではあるまいか。
三人の間柄をあらためて説明すると、五十六歳の山本は海軍の主流だった砲術の出身だが、一九二四年大佐時代に霞ヶ浦航空隊副長に補せられたときから航空界に足を踏み入れ、空母「赤城」艦長、航空本部技術部長、第一航空戦隊司令官、航空本部長、海軍次官を歴任している。
この世代には生え抜きの飛行機乗りはいないから、いわば途中転身組だが、「海軍航空育ての親」と言われるほど力を入れ、マイノリティにすぎなかった航空を大艦巨砲と並ぶ位置にまで押しあげた。しかし七歳若く、生え抜きのパイロット出身だった大西や、さらに十三歳年下の源田のように急進的な航空主兵論者とは言えなかった。
連合艦隊は十数万人の士官・下士官・兵をかかえる大世帯である。砲術、水雷、航海、通信、機関、陸戦……と職域は広く、一九四一年の段階でも人数の上で航空はマイノリティにすぎなかった。
日米戦争は戦艦という大艦、それも搭載する巨砲で決着をつけると確信する砲術屋は、人事的にも海軍の主流の座を占めていた。次には酸素魚雷をかかえて得意の夜戦で勝利のきっかけを作ろうとする水雷戦隊、漸減戦略の主役を自負する潜水艦乗りも我こそ、と競いあう。
それを束ねる政治家的資質の山本は、あちこちに気を配りながら、時に「戦艦には政治的価値がある」式の名言をポツリと語る。聞き伝えた航空屋は「山本さんの本心は航空主兵論だ」と思いこむ仕組みなのだが、真珠湾攻撃ともなれば、主役は否応なしに航空すなわち空母搭載の艦載機である。
源田によると、山本の原案は「(四隻の空母で)目標は米国戦艦群、攻撃は雷撃隊による片道攻撃」で、山本が直率する構想だった。
大西と源田は「米国民にとっても政治的価値の高い」戦艦を山本が主目標にしたのか、と推測したが、やはり空母に切り変えるべきだと結論する。
それから十カ月、紆余曲折を経てこの壮大なプロジェクトは実現するが、各方面の反対や抵抗を押し切ったのは、山本長官の強烈な意志力だった。途中で基地空軍の立場を代表する大西は反対派にまわり、一中佐の源田が文字どおりチーフ・デザイナーの位置につく。中長期にわたる大戦略は苦手だが、短期で明確な目標と期限が設定されたとき、それを完全主義に近い形で仕あげるのは日本人の国民性に似合うようだ。
戦後では東京オリンピックや東海道新幹線を代表格に各種の国際イベントなどで、得意技は遺憾なく発揮されたが、真珠湾プロジェクトはそれらを上まわる芸術的作品と評していいだろう。しかも、東京オリンピックとちがって、機密が洩れれば真珠湾作戦は即座に中止するか、返り討ちに会うリスクを背負っていた。
真珠湾に地形が似た内地港湾を使っての演習、十二メートルの水深にあわせた碇泊艦船に対する浅海面雷撃の訓練、魚雷の届かぬ内側の戦艦を狙う水平爆撃訓練、どれをとっても、目標は想像できた。一水兵の洩らす何気ない噂でも鋭いスパイには探知可能だったにちがいない。そうと分れば、アメリカは直前に艦隊主力を出港させ、空打ちする日本の飛行隊を、戦闘機の大群と強烈な対空砲火で迎え撃てばよい。
それだけではすまない。ミッドウエー海戦(四二年六月)と同様に、米空母部隊が待ち伏せして叩けば、六隻の日本空母群は全滅したかもしれない。