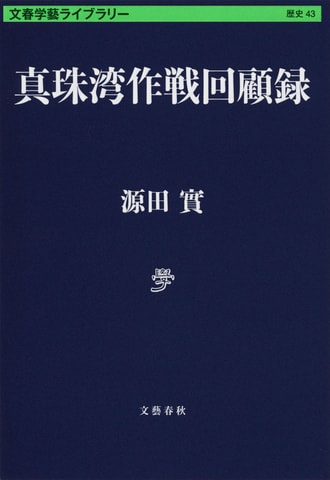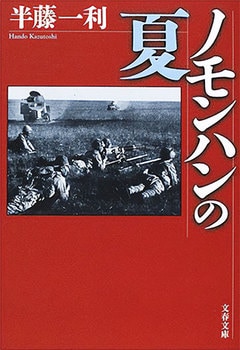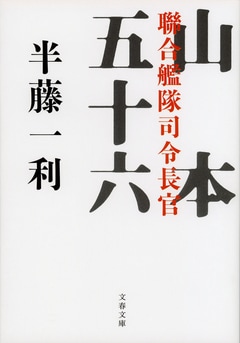今になって考えてみると、この大プロジェクトの片鱗さえ洩れなかったのは奇蹟的と言ってよい。そして奇蹟は幸運を呼んだ。
千島列島のヒトカップ湾から出撃して北太平洋をハワイへ向う十数日の航海で、行きあった商船も軍艦もなく、飛行艇の索敵網にもかからなかったのである。直前偵察で飛んだ水上機も見つからず、接近中の大編隊を新設のレーダーで発見したにもかかわらず、当直士官が握りつぶすという米側のミスまで重なった。
反対論の主たる根拠は、事前に発見され、返り討ちにあう投機的性格にあったのだが、結果的にはすべてをクリアーしたのだ。
南雲艦隊司令部で生え抜きの航空屋は源田と航空(乙)参謀吉岡忠一少佐の二人だけであった。長官の南雲は水雷屋、参謀長の草鹿龍之介は山本と似た転身組だから、源田の原案はスラスラと通った。いつしか口さがない若手士官たちが「源田艦隊」と呼ぶようになったが、源田は「そら恐しくなってきた。幕僚が奔放なプランを作っても、司令官や参謀長がチェックしてくれる安心感を欲しかったのだが」と告白している。
あらゆる点で真珠湾と対照的なミッドウエーの敗戦は、源田にすべてを任せたゆえの失敗でもあった。もちろん源田だけでは歯車は回転しない。上級の連合艦隊司令部や軍令部(作戦課)には、二、三人の航空屋がいて、源田プランの具体化に力を貸したが、それも山本の後楯があってのことだったかもしれない。
ともあれ、山本の着想に発した真珠湾攻撃の実施構想は、飛行機隊との接点に座った源田の綿密な作業によって最終計画にまとまった。山本原案との対比を念頭におきながら要点を次にかかげておこう。
1参加兵力は空母六隻
2主目標は米空母、次に戦艦
3外側の戦艦列を艦攻で雷撃(浅海面用魚雷を使用)
4内側の戦艦列を艦攻で水平爆撃
5小艦と飛行場を艦爆で急降下爆撃
6戦闘機隊(ゼロ戦)による制空
7接近航路は洋上給油しつつ北太平洋コースをとる
最終構想が固まるまでには克服せねばならぬ難点がいくつもあった。当初は冬の荒海での洋上給油は不可能と思われ、空母は航続力の長い四隻しか参加できぬとされた。しかし給油が可能と判明、帰路は漂流してでもと粘った山口二航戦司令官の突きあげもあって、六隻参加におちつく。
命中率の悪い水平爆撃は一時断念したが、名人クラスを集めた特訓で精度が大幅に向上したので復活する。技術突破のなかでもっとも手こずったのは、発射後に魚雷が海底に刺さらないよう安定ヒレを付した浅海面用魚雷の開発と製造だった。何しろ最後の魚雷は、すでにヒトカップ湾に集結していた南雲艦隊へ特別便で運びこまれたぐらいだから、きわどいところだった。
寝こみを襲った据物斬りとはいえ、雷撃九〇%、水平爆撃二七%、急降下爆撃五九%という驚異的命中率で真珠湾の全戦艦(八隻)を倒し、飛行機の大部分を地上で爆破炎上させてわが方の損失二十九機という日本海海戦に匹敵する大勝利も、こうした関係者のチームワークと熱意の成果だった。
惜しまれるのは、米空母の全部が偶然にも真珠湾を出払って不在だったことである。もう少し綿密な索敵をやっていたら、近海にいた二隻を葬れた可能性はあるが、大勝利に酔った南雲艦隊も海軍中央部も気づかなかったばかりか、「世界最強」を自負する驕慢気分におちいってしまう。
本書は書名が示すように、真珠湾作戦、それも準備過程に主眼を置いている。著者には別に『海軍航空隊始末記』の「発進篇」と「戦闘篇」の二冊(いずれも文春文庫として既刊)、『風鳴り止まず』(サンケイ出版)があり、海兵生徒時代から終戦までの体験が自伝風に書かれている。併読をおすすめしたいが、「戦闘篇」では真珠湾作戦は概略だけにとどめ、源田にとって痛恨の敗北体験となったミッドウエー海戦に多くのページを割いている。
読み比べて感じるのは、長官も参謀長もパイロットも変らず、しかも圧倒的な優勢兵力を誇った南雲艦隊が完敗してしまったふしぎさである。源田は責任をいさぎよく認めているが、組織全体があちこちで致命的なミスを重ねているところを見ると、やはり国民性ではないか、との思いを捨て切れない。
勝者の進歩がとまり、戦訓をかみしめた敗者に報復されるという歴史にありがちな結果だったともいえようが、それにしても落差はあまりにも大きかった。
開戦時における日米両海軍の戦術思想、なかでも空母戦術に大差はなかったと源田は言う。大艦巨砲主義が主流だった点でも似たようなものだった。ところが、真珠湾で全戦艦を失った米海軍は、敗北の戦訓から航空主兵主義へとすばやく転換した、というよりそうせざるをえなくなったのに対し、勝者の日本はかえって転換がおくれるという皮肉な結果となる。
ミッドウエー海戦では、無傷の日本戦艦部隊が山本とともに主力部隊の名称をもらって出動する。「無敵」の南雲艦隊(実は源田艦隊)は、相手に読まれているはずの発想と戦法を何も変えず、今度は主力部隊の露払い役に甘んじた。
暗号解読情報で待ち伏せしていた三隻の米空母を、源田は索敵の不備から見落し、米急降下爆撃隊に奇襲され、四隻の全空母を失って敗退する。
その後、軍令部の作戦課(航空担当)に転じた源田は一九四四年十月、大西中将(一航艦長官)が比島で始めたとされる神風特攻隊の編成にも関わったが、その内情について終生沈黙を守った。慰霊祭の席で、「あなたが発案者じゃないのか」とつめよられたこともあるが、源田は答えていない。
本書で著者は山本、南雲と並んで大西の人物論を試みているが、「既成の尺度で測れぬ智将」と評したあと、大西が特攻を決断した事情にからめ「われわれ後輩のものは、何か思案に余るようなことが起こると大西さんのところへ行って、相談に乗ってもらったもの……親分の親分たるにふさわしい」と意味深長な表現をしている。
私は「特攻」を大西と源田の合作と推測している。二人は、真珠湾作戦で発案者が山本、実施プランを源田が引き受けた例に似た関係だったのかもしれない。
戦史的観点から真珠湾攻撃を観察しようとする人々にとって、本書は不可欠の文献であるが、あわせて戦史叢書『ハワイ作戦』(朝雲新聞社、一九六七)、淵田美津雄『真珠湾作戦の真相』(大和タイムス社、一九四九)、福留繁『史観・真珠湾攻撃』(自由アジア社、一九五五)、G・プランゲ『真珠湾は眠っていたか』1~3(講談社、一九八六―八七)をおすすめしたい。