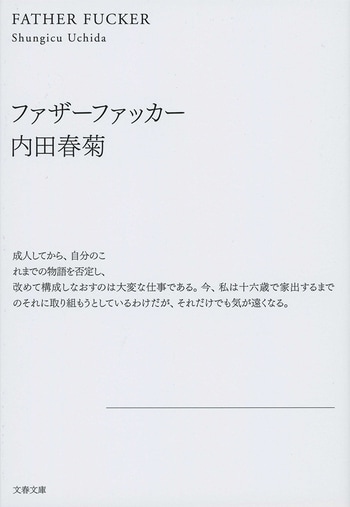『ファザーファッカー』を読んだ私たちはすでに、このあとにどれほどひどい現実が待ち受けているか知っている。どうかしているとしか思えない孝のふるまいも、静子の妊娠が発覚してからの目を背けたくなる暴力も、そして、それに加担した逸子のことも、いくら時が経とうと忘れられるものではない。
これまで静徳、孝へと渡って行った逸子の幸せは、最終的に静子へ託されたと言える。逸子から受け継いだその才能で、静子が医者か弁護士になってくれさえすれば、かつて自分の足を引っ張った家族や時代や静徳を見返すことができる、と逸子は信じていた。しかし、本当にそうだろうか。もしも静子が逸子の願いを叶えたとしても、逸子自身は何にもなれないままである。逸子は静子と自分は「タイプが違う」とよく言っているが、『ファザーファッカー』と照らし合わせてみると、ふたりが同じ場面で同じことを思っているのが目に留まる。特に、孝の理不尽な理論や命令を前にしたとき、ふたりの心は通じ合っていると言える。それでもふたりが対照的なのは、その理不尽な現実に対する態度が異なるからだ。静子はあからさまに嫌そうな顔をし、逸子はそんな静子を心の中で叱りながら、自分を飲み込んでゆく暗闇にじっと耐えている。静徳との生活だって、逸子は9年間も我慢したのだ。例の孝の地獄のようなセリフを聞き、
私は試されているのだ。でも何から? 孝? 運命?
と考えたときのように、逸子はこれまで幾度となくこういう試練にぶち当たっては、そのすべてに耐えてきた。でも耐えることは、受け入れることでもある。逸子は自分に降りかかるひどい言葉や状況を、受け入れてきてしまったのだ。それは、逸子が“見返す”ことに熱意を注いでいたことからもうかがえる。なぜなら“見返す”ことは、自分をひどい目に遭わせてきた人たちに、褒められたいと思うことだから。逸子はいつまでもまわりの評価に縛られ続け、そうして自分のステージをじわじわと失っていき、しまいには「もうあなたの好きにしてください」と孝の手のひらの上で踊ることを選んだ。けれど褒められようとしない静子は、自分を陥れようとする現実を全身全霊で拒み、自らの意思で暗闇から飛び出していく。ラストシーン、逸子は静子の死体を探し歩くが、雨の降る山の中を彷徨う逸子の方がまるで死者の霊のようである。そして最後まで、“もう少しの我慢”なのだと逸子は自分に言い聞かせたまま、物語の幕は下りる。そんな逸子の姿に、「求めよ、さらば与へられん。尋ねよ、さらば見出さん。門を叩け、さらば開かれん。すべて求むる者は得、たづぬる者は見いだし、門をたたく者は開かるるなり」という新約聖書の一節(日本聖書協会『旧新約聖書』マタイ伝福音書第七章第七~八節)が頭を過ぎった。
聖書といえば、ある映画好きの友人が「ヒットする映画にはだいたい聖書の引用がある」と教えてくれたことがあった。日本生まれにはピンとこないが、キリスト教国家では聖書のストーリーは頭に入っているものだから、一部を引用しただけでも膨大な情報がそこに含まれて、一気に運命的な奥行きが物語にもたらされるためらしい。その話を聞いたとき「まるで、私にとっての母みたいだ」と私は思った。なぜならば、人は私を見るとき、その後ろに母の人生をも見るからだ。そうしてまったく自動的に、自分の姿や言動などに奥行きが加えられていく経験を、私はこれまで数えられないほどしてきた。私に限らず、娘はみな母という名の聖書を抱えて生きるものなのかもしれない。私の母だってそうだ。けれどもしかし、母はこの物語を書くことで、その執筆までも自分の手でやってのけた。「なにがなんでも運命を自分のものにしてみせる」という、とんでもなく強い母の意思を前に、ただただ頭が下がる思いである。