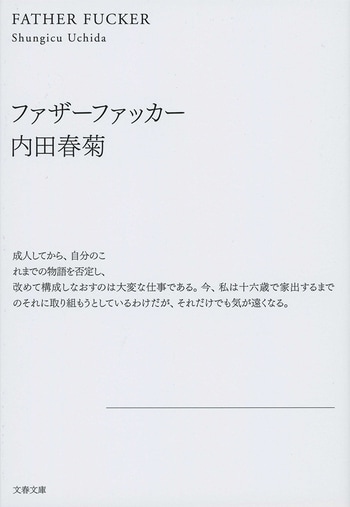私がはじめて『ファザーファッカー』を読んだのは、高校3年生のときだ。退屈な授業中、悪びれもせず堂々と文庫本のページをめくっていると、「うわっ、おまえ親の読んでんのかよ」と前の席の男の子に言われた。彼のからかいの意味が、私はいまだによくわからないのだが、このたび親の小説の解説を書く運びとなった。しかも、『ファザーファッカー』の母親目線版『ダンシング・マザー』の、である。ちなみに件の男子からはこのあいだ「あの頃、彼女ができてから避けて悪かった」という、まったく身に覚えのないメッセージが届いたのだけれど、どうしようもないので彼の話はこのくらいにしておく。
母は胃を痛めながらこの小説を書いていた。そりゃそうだ、と改めて読み私は思った。58万部のベストセラーとなったブレイディみかこさんの『ぼくはイエローでホワイトで、ちょっとブルー』では、他人の感情や経験などを理解する能力を指す“エンパシー”という言葉を、“他人の靴を履く”と表現していた。母は、この小説を書くにあたって自分の母親の靴を履き、そうして自分の胃をぐりぐりと踏みつけていたのである。大変な仕事だったと思う。まずは母に、心からのおつかれさまを送りたい。
もうこれだけで十分な気がするが、しかし、私はこのとんでもない物語を解説するという、これまた大変な仕事を請け負ってしまったのだ。物語の主人公は母の母、すなわち私の祖母にあたる。私はこれまで彼女に会ったことはなく、また会いたいと思ったこともない。母の生い立ちは幼い頃から聞いていたし、「私が死んだら絶対お金を取りに来るからね。ものすごく優しそうな顔をしてるけど、騙されちゃだめよ」と母に言われていたので、いつもおそろしい魔女のような人物を頭に浮かべていた。たとえば優しくたゆむ笑顔が、あるときいっぺんに吊りあがってケタケタと笑い出し、その頬をナイフで切りつければ緑の血が流れるような……けれど、そんな生まれながらの悪者なんてこの世には存在しないのだ、と私はこの小説を読み痛いほどわかった。毒親という生き物などはいなくて、そこにはだれにも認めてもらえなかった、ひとりの悲しい女がいた。
彼女の名前は逸子という。11歳で終戦を経験した逸子の人生が動き出すのは23歳、故郷を飛び出し長崎へ向かったときである。逸子は裁縫もとても上手だったが、なによりダンスの才能が飛び抜けていて、行きつけのダンスホールではお得意様扱い。だって逸子が踊れば、フロアに大輪の花が咲くのだ。そこにボーイフレンドの静徳がやってきて、見つめ合い、手を取り合えばもう、だれもふたりを無視できなかった。静徳の腕の中で素晴らしい踊りを披露しているあいだ、逸子の体じゅうにバチバチと弾けるような全能感が駆け巡った。ふたりでだったら何にでもなれる。そうして“ただの恋人たちでなく、同じ目標を持った「同志」”として、逸子と静徳は駆け出したのだった。が、その先でふたりがなったものは、賭博場の下働きだ。輝かしい夢の前にはいつも、地味でつまらない現実が立ちはだかる。それどころか、静徳はだんだんと逸子に冷たくなり、ついには暴力まで振るうようになって、なんどもなんども逸子に子どもを堕ろさせた。戦後すぐ、不適切な言葉に次々と線を引きまっくろになった教科書みたいに、逸子の人生もどろりと黒く塗りつぶされていく。何度目かの妊娠がわかったとき、逸子は決意して賭博場のマスターにお金を借りた。子どもを産めば、静徳も変わってくれるかもしれない、とわずかな希望にかけたのだ。そうして生まれたのが静子、私の母である。