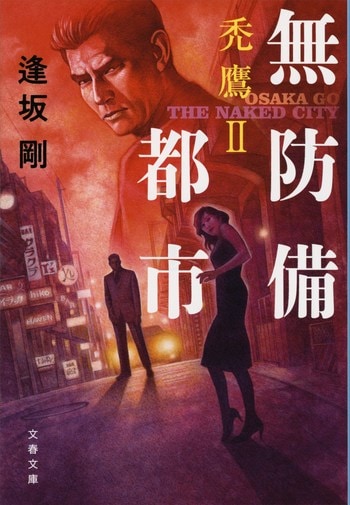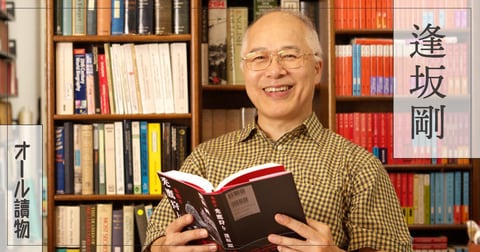一方逢坂さんも同じくシングル・アクション・アーミーをお持ちになったのだが、グリップが木製の特注品で、やはり特注の豪華な革製ホルスターに収められた『逢坂スペシャル』とでも称すべき逸品であった。
「月村さんにお見せしようと思って持ってきたんですよ」と逢坂さんはどこか嬉しそうだった。そういうときの逢坂さんの笑顔は、テレビドラマ版〈百舌シリーズ〉の『MOZU』における西島秀俊のそれを軽く凌駕すると言っても過言ではあるまい(ここで思い切り持ち上げるのは後段のための伏線である)。
悲劇はトークショーの後の会食時に起こった。編集者を交えてわいわいやっているうちはよかったが、そのうち逢坂さんが「持って御覧なさいよ」と件の逢坂スペシャルを出してきた。
受け取った私が「凄いですねえ」とホルスターから抜いてためつすがめつしていると、周囲の編集者達が口々にはやし立てるではないか――「月村さん、いい物もらいましたねえ」と。
えっ? と思った私は、慌てて言った。
「いや、これはちょっと持たせてくれただけで、逢坂さんは別にあげるなんて一言も……」
だがそこは大人物の逢坂さんである。「うん、どうぞどうぞ」とすかさずおっしゃるではないか。
「えっ、いや、待って下さい、頂けませんよ、こんな大切なもの……」「いやいや、いいから」「しかし、いくらなんでも」「いやいやいや、いいからいいから」「そんなこと言われましても」「いいっていいって」
とそんな調子で、逢坂さんは終始笑みを絶やさず、私は結局逢坂スペシャルをホルスターごと持ち帰る羽目になってしまった。
かくして拙宅に家宝が一つ増えたわけだが、後日逢坂さんに「あのときあげるなんておっしゃってませんでしたよね?」と伺ったところ、「まあ、ああいうときはしょうがないよ」と苦笑しておられた。
(また十数秒むせび泣く。私が)
こんなこともあった。前述のテレビドラマ版『MOZU』がヒットした頃、逢坂さんの文庫版〈百舌シリーズ〉は増刷に次ぐ増刷を重ねていたため、同じハードボイルド派の大沢在昌さんが逢坂さんを称して「百舌長者」と言った。盟友ならではの愛ある揶揄である。それを伝え聞いた(伝えたのは私ですけど)逢坂さんは、「大沢なんか鮫長者だから」と笑っておられた。そういうときの逢坂さんの顔! 逢坂さんと面識のある方にはお分かり頂けるのではないかと思うが、冗談を言うとき、減らず口を叩くときの悪戯っぽい表情は絶品である。
百舌長者に鮫長者。その並びが可笑しくて、時折思い出してはにんまりと笑っている。お二人に接し得た後輩の特権である。
(ここでまた十数秒むせび泣く。我身の不甲斐なさをかえりみて)
さて、逢坂さんの人間的魅力の一端でも、私は伝えることができただろうか。
とてもそんな自信はないのでもう少し書く。
逢坂さんが神保町に仕事場を構えておられるのは有名で、私にとっては憧れるばかりなのだが、神保町は古書店だけでなく、出版社が多いことでも知られている。そのため打ち合わせなどの後、神保町の鮨屋(今はもうない)に行くことが何度かあったのだが、そこで逢坂さんの話になった途端、御本人がまるで外で待っていたかのようなタイミングで入ってくる。そういうことが二、三回あった。
暖簾をかき分けて入ってくるその姿に、逢坂さんが愛してやまぬ西部劇の、スイングドアを押し開けて酒場に入ってくるガンマンを思い浮かべるのは私だけであろうか。私だけですね。
何が言いたいかというと、そういう「偶然」を呼び寄せるのもまた、ヒーローの証しであるということだ。
そんな風格ある逢坂さんと、ヒーローどころか撃たれる前に落馬して死にそうな私にも共通点はある。
それは、「『荒野の七人』のリメイクの『マグニフィセント・セブン』、てめえだけは許せねえ」という見解の一致だ。
こういう趣味の問題は、実は創作において存外重要なことであったりするのですよ。