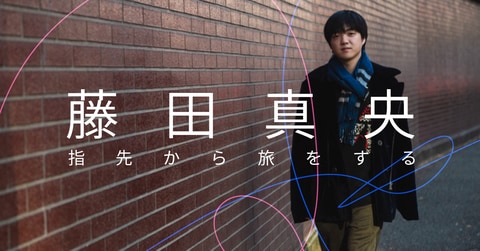第1章 Wild strain(野生株)
1 2020年1月6日
「一帆、そろそろご飯だから、タブレットは終わりにしなさい」
椎名梓がキッチンから声をかけると、絨毯にぺたりと座って動画配信サイトで動物番組を見ていた一人息子の一帆は、「もうちょっとだけ」と答える。
「そんなに顔に近づけたら目が悪くなるでしょ。それに、三十分だけの約束。いまは何時かな?」
梓が掛け時計を指さすと、一帆は小さい額にしわを寄せた。
「えっと、七時……四十五分?」
四歳の一帆は最近、時計の勉強をしているが、まだ完璧ではなかった。
「惜しい、六時四十五分ね。ほら、短い針が『6』と『7』の間にあるでしょ。そのときは、小さいほうの時間じゃなかったっけ?」
「あー、そっかー」
一帆は悔しそうに頭に手を当てる。その愛らしい姿に、思わず口元が緩んだ。
「いいのよ。長い方の針が何分を指しているかは当たったんだから。すごいじゃない。この前まで全然分からなかったのに」
「だって僕、いっぱい勉強したし」
一転して、一帆は誇らしげに胸を張った。
「えらいえらい。で、六時十五分から動画を見ているから、ちょうど三十分経ってるよ。カズ君はえらいから、もうやめられるよね」
「でもー、いまカピバラさんを見ているから」
下唇を突き出した一帆が指さした液晶画面には、気持ちよさそうに温泉に浸かっているカピバラの親子が映っていた。
「じゃあ、そのカピバラで終わりにするのよ。約束できる?」
「うん、分かった!」
屈託ない笑みを浮かべながら、一帆は大きく頷いた。梓は息子に微笑み返したあと、L字ソファーでせんべいを齧っている母の春子に視線を移す。
「お母さん、おせんべい食べないでよ。もうすぐご飯なんだから」
「ごめんごめん、なんか口寂しくてさ」
春子は慌ててせんべいを菓子皿に戻した。
「口寂しくてって、お母さん糖尿病でしょ。間食しちゃダメって、いつも言っているじゃない。そもそも、お菓子を買ってこないでよ。あったら食べちゃうんだからさ」
梓は大きくため息をつく。
「この前、カズ君とスーパーに行ったとき、『これ、ばぁばが好きそうじゃない?』って勧められてさ。ねえ、カズ君」
話を振られた一帆は、「え、なに?」と目をしばたたかせた。
「何でもない。カピバラ可愛いわね」
「うん。ばぁばも一緒に見る?」
寄り添って画面を覗き込みはじめた一帆と春子を見て、梓は苦笑する。しっかりと指導しなくてはと思ってはいるが、母にはどうしても強く言うことができなかった。
梓が小学生のとき、父が肺がんで命を落とした。それから、春子は様々な仕事をしながら、女手一つで必死に梓を育ててくれた。二年前、梓が銀行勤務の夫と、お互いの多忙が原因で離婚してからは、三人でマンションに住んでいる。忙しい梓の代わりに、春子が一帆の面倒を見てくれていた。
同居にあたって「カズ君のために」と、三十年以上、毎日二箱近く吸っていたタバコもやめてくれたのだ。間食ぐらいは大目に見てもいいのではと思ってしまう。
「ママ、今日のご飯もカレー?」
カピバラの動画を見終えて、タブレットの電源を切った一帆が顔を上げる。
「うん、いつもカレーでごめんね」
地下鉄氷川台駅から徒歩十五分ほどにある心泉医大附属氷川台病院に、梓は呼吸器内科の医師として勤めていた。大泉学園にあるこの自宅マンションからは車で二十分ほどと近いのだが、外来と病棟業務のどちらもこなしているため、平日は早くても帰りは午後九時以降になる。しかし、火曜日は『研究日』という名目で大学病院での勤務が免除され、医局から紹介されたクリニックで午前だけ診療をしていた。
大学病院の給料は低く、今年三十六歳になり病棟長を務める梓でも、それだけでは年収は五百万円程度しかない。多くの同僚は研究日に外勤先で一日勤務をしたり、人によってはそのまま翌朝まで当直業務をこなすなどして、収入を上げていた。しかし、梓にとっては給料よりも、家族との時間の方が遥かに大切だった。
すでに還暦を過ぎた母に負担をかけすぎないためにも、火曜と週末の夕食当番は梓が担っている。ただ、料理のレパートリーが少ないのが悩みだった。
「ううん、大丈夫。ママのカレー美味しいから一番好き」
「あれ、ばぁばのご飯は一番じゃないの?」
春子がわざとらしく口をへの字にする。一帆は少し困ったような表情で考え込んだあと、「どっちも一番好き」と両手を広げた。可愛らしいその姿に、胸の奥が温かくなっていく。そのときふと梓は、春子がつけたままにしてあるテレビに、『肺炎』の文字が躍っていることに気づいた。
視線が引きつけられ、キッチンを出てテレビに近づいていく。
『中国湖北省の武漢で去年十二月以降、原因が特定されていない肺炎の患者が五十九人確認され、重症者も出ていることが発表されました。これを受けて厚生労働省は……』
キャスターが淡々と原稿を読み上げる。画面の下方に『中国武漢で原因不明の肺炎相次ぐ』とテロップが表示されていた。
中国……、原因不明の肺炎……。
「……SARS」
唇の隙間から言葉が漏れる。
この続きは、「別冊文藝春秋」9月号に掲載されています。