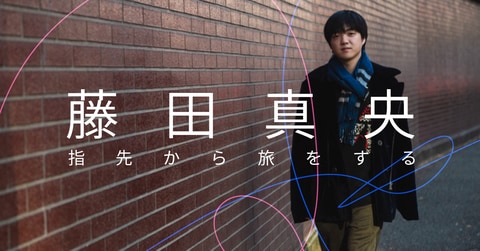〝それ〟はただ、そこにあった。
名前はなかった。意思を、意識を持たぬ〝それ〟らには必要なかった。
呼吸をせず、食べず、動かず、生殖をせず、代謝をしない。ゆえに、〝それ〟は生きてはいなかった。有機物で構成された物体でしかなかった。
ただ〝それ〟は一つのことだけをプログラミングされていた。
増殖すること。
〝それ〟がいつ生じたのかは誰にも分からない。誕生から四十六億年が経つこの惑星のどこかの時代で、偶然の積み重ね、もしくは『神』と呼ばれる概念によって創り出された。
〝それ〟は長い長い間、暗闇の中を飛び回る、翼をもつ漆黒の獣とともに存在していた。
しかしいま、〝それ〟の前には、他の獣がいた。
翼をもたず、体毛は頭部の一部に集中し、二本足で直立歩行しながら、複雑な鳴き声を発する獣。
その獣が、顔面の中心部にある二つの穴から空気を吸い込んだ。
〝それ〟とともに。
外殻に無数の突起を纏う球状の〝それ〟の姿は、まるで光冠を帯びて輝く太陽のようだった。
獣の細胞に着地した〝それ〟の突起が、細胞の膜にある複雑な形をした構造物と結合する。まるで、鍵穴に鍵が嵌まるかのように。
膜が〝それ〟の外殻と、融けた蠟のように混ざり合いはじめた。
〝それ〟の中に折りたたまれて収められていたひも状の物質が、細胞内に放出される。
狭い金魚鉢に押し込められていた海蛇が、大海に放たれたかのごとく、その物質は細胞質を泳ぎ回りながら、自らの複製体を作りはじめた。
生み出された複製体が、さらに次の複製体を生成していく。
二倍、四倍、八倍、十六倍、三十二倍……。
ネズミ算式に増えるその物質に満たされていく細胞は、もはや獣の一部ではなく、〝それ〟を化学合成し続ける、有機工場と化していた。
やがて、細胞が破裂すると同時に、無数の〝それ〟が撒き散らされ、そして周囲の細胞へと取り付いていく。
その光景はまるで、燃え上がった太陽が、眩いフレアを噴き上げるかのようだった。