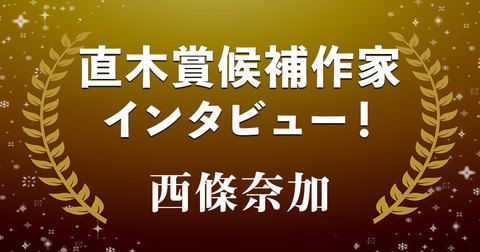厚生労働省の統計によると、二〇二〇年の日本国内での離婚件数は約十九万三千組。約三分に一組が離婚している計算になる。
その中で約八十八%を占めるのが協議離婚だ。協議離婚とは夫婦で話し合いをして合意に達し、離婚届を提出するというもの。残りの約十二%は話し合いで決着できず、調停や審判、訴訟という手段をとっている。十二%というと少なく感じるかもしれないが、離婚の総件数が二〇〇二年をピークに減少している中、逆に調停や裁判に持ち込まれる率は僅(わず)かながら増加している。つまり、モメる率が上がっているわけだ。
だが、裁判所で他者に事情を説明し、権利を主張して争うのは、素人にはなかなか難しい。そこで多くの場合は弁護士を頼ることになる。
当人同士で解決できなければ訴訟に進み、それを助けるプロがいるというシステムは、すでに江戸時代に存在していた。それが公事宿(くじやど)だ。公事宿とは訴訟のために地方から江戸に出てきた人が泊まる宿のこと。宿の従業員は訴人が奉行所に提出する書類を作ったり手続きを代行したりと、今の弁護士の役割も担っていたという。つまり宿泊所付き弁護士事務所だと考えればいい。
江戸時代、原則として離縁する権利は夫側にしか認められていなかった(詳細は後述)。妻が別れたいと思ったときは、夫から「三行半(みくだりはん)」と呼ばれる離縁状をもらうことが必要になる。だが、素直に三行半を書いてもらえない場合ももちろんあるし、別れるにせよ財産や子どもの問題がついてまわるのは今も同じ。そこに目をつけたのが本書『わかれ縁』である。
舞台は江戸日本橋にある公事宿「狸穴屋(まみあなや)」。多くの公事宿がひしめく馬喰町(ばくろちょう)の中でも離縁の調停に強い、という設定だ。夫の女癖と借金で絶望の中にあった絵乃(えの)が、この狸穴屋に辿り着くところから物語が動き出す。
離縁したいが絵乃の稼ぎに寄生している夫が別れてくれるはずもなく、頼れる実家もない。このままではわずかな給金も残りの人生もすべて夫に吸われてしまうとうちひしがれる絵乃に、公事宿の女将は十両で離縁を手伝うともちかけた。
そんな大金を持たない絵乃は、読み書きができることと気働きを買われて狸穴屋の手代見習いになることに。狸穴屋を訪れる人々のさまざまな離縁問題を目の当たりにしながら、絵乃は自分の本心と将来を少しずつ見定めていく。
物語は連作形式をとっており、それぞれ異なる夫婦事情・家庭事情が描かれるのがポイントだ。第一話の表題作は絵乃が狸穴屋の手代見習いになるまでの物語。つまり、精神的・経済的DVに追い詰められた妻のケースだ。
第二話「二三四の諍い」は商家の話。まだ十代の兄妹が両親の離縁について狸穴屋に相談に来る。母の実家が作った借金のせいで、母を離縁しようと父と長兄が画策している。いまさらそんな父にも長兄にも未練はないが、母のためにより多くの示談金をとってほしいという依頼だ。
第三話「双方離縁」は嫁姑問題。いがみあう妻と母に挟まれて疲弊した夫のため、狸穴屋がある作戦を実行する。第四話「錦蔦」は親権がテーマ。夫婦の離縁はスムーズだったが、婚家は伝統ある縫箔師(ぬいはくし)、実家は大所帯の截金師(きりかねし)で、どちらも一粒種の息子は我が家の跡取りだと譲らない。
第五話「思案橋」では絵乃の身に大きな波乱が起きるのだが、ここにはまだ書かないでおこう。自身の離縁がなるかどうか、大きな分かれ目の一話だ。それを受けた最終話「ふたたびの縁」で、絵乃はとある決断に向き合うことになる。
通して読むと、離縁に関する当時の法制度がつぶさに描かれていることにまず驚かされた。なんとなく江戸時代は夫が一方的に妻に三行半を突きつけ、妻側には何の権利もないような印象を持っていたが、本書を読めばそうではなかったことがわかる。
たとえば、三行半は離縁状であるとともに、妻の再婚許可証書でもあったこと(三行半の定型文の中にちゃんとそう書いてある)。この証書がないまま再婚すれば重婚の罪を犯したことになる。また、三行半の決まり文句である離縁事由「我等勝手ニ付」は夫の好き勝手で妻と別れるということではなく「都合により」程度の意味であり、妻に責任があったとしてもそれを明かさないための表現であるというのも驚きだった。