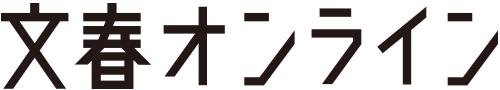大正から戦後を舞台に、二人の女性の不思議な絆が描かれた『襷がけの二人』(文藝春秋)。著者の嶋津輝さんが、作品にこめた憧れの女性への想いを綴りました――。
◆◆◆
婦人誌で出会った家事の達人・幸田文
美容師見習いと思しき若い店員から手渡されたのは、明らかに五十代以上のミセス向けの婦人誌だった。当時まだ三十代であった私は、若い美容師見習いの雑誌のチョイスにうっすら傷つきつつ、頭に巻かれたタオルのせいでよけい年嵩に見える顔をうつむけ、カラー頁ばかりで持ち重りのする雑誌に目を落とした。そしてしなやかな紙質の頁をどんどん繰った。
悔しいことに、どの記事も特集もひどく面白いのだった。どれくらい面白かったかというと、そのあと書店に寄って同じ雑誌を購入して帰ったくらいである。
特に面白かったのは「丁寧な暮らし」系の特集で、そのなかで、家事の達人の一人として紹介されていたのが幸田文だった。
少女の頃から父である幸田露伴に厳しく家事を仕込まれた、とある。掃除を教わるにもはたきを原稿の反故紙で手造りするところから始まり、箒で天井の煤を払えば女はいつも「見よい」恰好でやれと叱られる。この調子で父から家事全般を教え込まれた結果、作家となってから一時断筆して芸者屋で女中をした際には、あれはいったい何者かと近隣で噂に上るほどの有能ぶりを見せたらしい。

私は俄然興味を持った。
自分自身がぐうたらなせいか、家事が得意な人への憧れがつよい。生活系の雑誌が好きだし、スローライフを題材にした映画も好きだし、Eテレの日曜18時台にやっているような文化人の暮らしに密着する番組は必ず録画する。出演していた料理研究家やフードスタイリストが自分好みだと、最低でも10回は視聴する。憧れというより、執着に近いかもしれない。その人が出した本は余さず読むし、ウェブのインタビュー記事にも逐一目を通す。
題名「流れる」「みそっかす」「おとうと」のセンスにぼうっと
幸田文も、はじめはそんな感じに生活者として関心を抱いて、著書がとにかくたくさんあるので、端から読んでみることにした。
最初に読んだのは「流れる」だった。例の婦人誌の記事に、芸者屋で女中をした経験をもとに「流れる」を書いた、とあったからだ。有吉佐和子の花柳界ものが好きな私にとって、馴染み深い分野でもある。
読んでみると、有吉佐和子とはだいぶ違った。ストーリーにあまり起伏がなく、長編のわりに短い期間の話である。有吉佐和子はとにかく文章が上手くてぐいぐい読ませるが、こちらは格調高くて目が離せない味わいがある。筆致は結構くどくて、癖になる感じ。夢中になって読み終えたあと、この小説に「流れる」という題名を付けるセンスにぼうっとした。

それから「父・こんなこと」「みそっかす」「黒い裾」「おとうと」など、どんどん読んでいった。文章に痺れた。年を取って肉の落ちた親父の肩を「素枯れた」と表現したり、みそっかすという言葉が大言海に載っていないことを知ったときの心境を「鐘の尾に聴きいるときに似ていた」なんて喩えたりする。
岩波書店の全集も揃えて、頭から読んだ。こんなに小説をたくさん読んだのは人生で初めてのことだった。
全集を読み進めているころ、私は小説教室に通い始めた。初回の授業での自己紹介で、「好きな作家は幸田文です」と話した。何度目かの授業で小説ともいえない短い雑文を提出し、講師に「幸田文が好きというだけあって文章がしっかりしている」と褒められた。初心者はだいたい褒めてもらえるということを知ったのはだいぶ後のこと、気をよくした私は幸田文のくどい筆致を意識しながらいくつかの短篇を書いた。
「幸田文=私の運命のひと説」は妄想だったか!?
そのうち百枚を超えるものを書けたので、新人賞に応募してみた。すると最終選考に残りましたという電話がきた。
選考の日までの間、私は大いに妄想をたくましくした。このときの私は四十歳をちょっと過ぎたところ。幸田文が露伴の死後文章を発表したのも四十を過ぎてからだ。新人賞を穫れたら、幸田文と同じ年代に世に出ることになる。ひょっとして私は、幸田文の系譜をたどる作家になるのではないだろうか。幸田文は私の師、運命のひとなのではないだろうか……、などなど。
結果は落選で、膨らんだ妄想ははかなく霧散した。私は「幸田文=私の運命のひと説」をすぐに捨て去ることができず、幸田文と私との共通項を見出すことで失意をなぐさめた。
ともに父親が厳しい。ともに離婚歴がある。出来のよい姉と末っ子長男に挟まれた真ん中っ子というところも同じ。なによりどちらも四十を過ぎてから筆をとった――。それ以外の共通していない数々の点には目をつぶり、このまま何も起こらないはずはないという寄る辺ない予感をよすがに、その後も細々と投稿生活を続けた。

最初の落選から数年が経ち、私はオール讀物新人賞を受賞した。
受賞作「姉といもうと」は、幸田文「流れる」の主人公・梨花に憧れて女中になる姉と、その妹の話である。手の指に欠損がある妹の、なくしたものを嘆かない大らかな人間性が話の主題で、幸田文には作中のアクセントとして、いわば小道具的に登場してもらった。大きな事件の起こらない短い小説の中で、話に深みのようなものを持たせる効果はあったように思う。タイトルを「いもうと」と平仮名にしたのも、幸田文の「おとうと」を意識してのことだ。
さすがにもう私は、自分が幸田文の系譜を継ぐなどという大それた妄想をすることはない。ただ、幸田文の存在なくして、自分の人生に小説を書いて発表するなどという妙な出来事は起こらなかったように思う。川べりの草地や河底の石が水の流れを変えるように、すれちがいざま肩がぶつかっただけの人に身体の向きを変えられることがある。あの日私にミセス向け婦人誌を手渡した美容師見習いや、その雑誌の編集者も、運命のひとなどと大袈裟なことは言うまいが、運命の流木のような存在だったと思う。