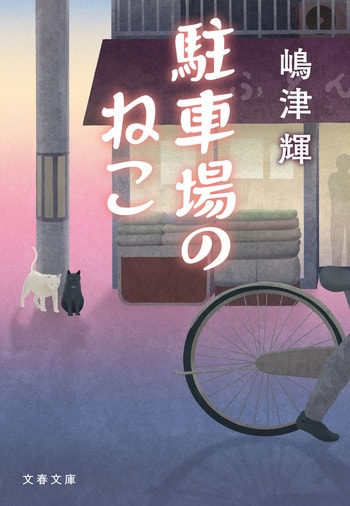<文庫解説より>
本書『駐車場のねこ』(『スナック墓場』を改題)に収録されている「姉といもうと」を初めて読んだのは、第九十六回オール讀物新人賞の候補作としてだった。得も言われぬ不思議な魅力のある一作、というのが最初の印象で、選考会でも選考委員の多くがこの作品独自の持ち味を支持した。読み返すごとに訴えかけてくる仄(ほの)かな、しかし確かなオリジナリティ。小説世界に染み透るこの作者ならではのカラーがそこには既に芽生えていた。
両親を失った姉妹の静かな日常――「姉といもうと」の姉である里香は勤め先の会社が倒産して以来、家政婦を生業(なりわい)として暮らし、手の指が少ない妹の多美子は知人が経営するラブホテルに勤めている。本書全体を通して言えることだが、作中人物たちの身空は決して明るくない。どちらかといえば薄暗い境遇にある人々に、しかし、作者はユニークな角度から光を当てていく。あるいは、その内側にある光を引き出していく。
幸田文の「流れる」に刺激されて家政婦になった里香は、仕事中、憧れの「女中」になりきることで、他者からは計り知れない充実感を獲得する。「あるもので何とかする」が口癖の多美子も、ラブホテル勤務を後ろ暗く思うどころか、ゆくゆくはその経営をも受け継ごうという意欲で満々だ。二人に共通するのは世間体など構わず内なる充足に軸足を置いていることで、両親の逝去も、会社の倒産も、指の欠落も、なにものもこの姉妹のどっかりとした平穏を揺るがしはしない。そこにあるのは過去を嘆くでも、未来を憂えるでもなく、ただ軽やかに現実を丸呑みする人間の姿だ。しかも、二人は決して肩肘を張っているわけではなく、至極自然にそうやって生きている。その天然のタフネスこそがこの作者が描く人物の身上ではなかろうか。
「ラインのふたり」に登場する霧子もなかなか強い。新卒で大手スーパーに就職した彼女は、二十五年に亘って経験とスキルを積んだ末、会社のいやがらせを受けて自主退職に追いこまれる。別のスーパーに勤めようにも求人がない。やむをえず倉庫内軽作業のアルバイトを始めるのだが、たとえそれがラインを流れる商品の単調な箱詰め作業であっても、彼女はそこに自分なりのやり甲斐を見出す。〈きまった時間のなかでひとつでも多くの完成品をつくろう〉と努め、うまくいけば満足し、うまくいかなければ落ちこみ、就業後は勤務先で親しくなった亜耶と社員の悪口を言って笑い合う。そこにも労働の手応えを他者に求めず、自分自身の中に求めることで、爽やかに日々を送る人間のたのもしい姿がある。
「スナック墓場」の克子は夫の死後、専業主婦から一転して水商売の世界へ飛び込み、〈流行らない商店街の最果てにあるスナック〉に雇われる。オーナーの死によってその店は畳まれることになるが、共に働いていた二人とはその後も毎年同窓会をしている。競馬が好きな克子の財布には常に折り畳まれた八千円が入っている。それは彼女が引きずるある後悔を物語るものだが、己の弱さから目を背(そむ)けることなく、戒(いまし)めとして常時携帯することで、克子はその紙幣をお守りのような存在にまで昇華させる。人生は大波小波をかいくぐる航海のようなものであり、一寸先に何があるのかは誰にもわからないけれど、そのようなお守りを持つことで、人は自分の中に厳とした錨を下ろすことができるのかもしれない、と感じさせてくれるエピソードだ。