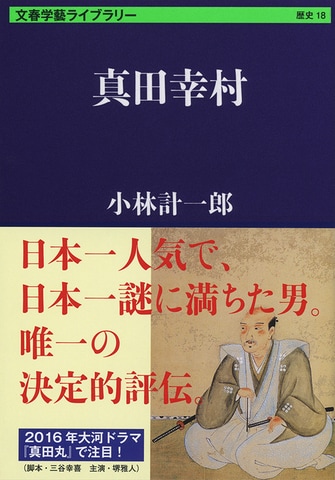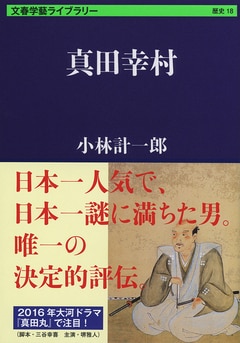幸村の軍師化はそういう時代の要請によってなされた。前述の忠義説同様、実際の幸村がそうであったかどうかとは無関係に、実録作者側の事情によって、軍師として描き出されたのである。その際、幸村には父昌幸の面影が重ね合わせられた可能性がある。上田城において二度まで徳川の大軍を防いだ昌幸の武略は、広く天下に知られていただろうから。
『厭蝕太平楽記』には真田十勇士の面々も、多く登場している。猿飛佐助・霧隠(才蔵という名はない)は、それぞれ一度ずつ登場する。(二人は『厭蝕太平楽記』の増補作『本朝盛衰記』になると、卓越した忍者として大活躍する。)他にも、穴山小助・根津甚八・三好清海入道・弟同伊三入道・由利鎌之助が、幸村の家来として重要な役目を果たしている。
『厭蝕太平楽記』は、近代の講談や立川文庫等のルーツとも言うべき文学作品である。現在の上方講談『難波戦記(なんばせんき)』の種本でもある。
前述の『真田三代記』は、大坂の陣については『厭蝕太平楽記』に基づいて増補しており、『厭蝕太平楽記』よりやや遅れて成立した作である。早く明治期から活字化されたため、現在もよく知られているが、江戸時代には『厭蝕太平楽記』の方が遥かに流布していた。
○
最後にまた、小林氏の『真田幸村』に戻ろう。「幸村は死に場所を得るために大坂に入城したとしか考えられない。九度山で浪人のまま窮死するより、大坂城の将としてはなやかに討ち死する道を幸村は選んだのである。(はじめに)」ここを初出として、小林氏は本書でたびたび幸村は死に花を咲かせるために入城したと言われている。対して、大阪城天守閣館長北川央(ひろし)氏は最近こういう発言をされている。
一般に幸村については、豊臣家から賜った厚恩に報いるため、負けるとわかっていながら大坂城に入ったとされる。…… では、幸村は「負けるとわかっていながら」豊臣方に味方したのであろうか。…… 慶長20年5月7日、幸村は大坂夏の陣最後の決戦で、3度にわたって徳川家康本陣に突撃。家康をあと一歩のところまで追い詰めた。家康さえ倒せば、徳川軍は総崩れになると考えての行動だったのであろう。 幸村の戦いぶりからは、最後まで勝利をあきらめない生き方をこそ読み取るべきではなかろうか。(『朝日新聞』大阪版夕刊 二〇一四年十二月二十二日「つれづれ彩時記」)
「死に花を咲かせる」と「最後まで勝利をあきらめない」と、幸村像にかなりの開きがある。私はどちらが正しいか、穿鑿するつもりはない。読者はお好きな方、あるいはさらに違う説を選択してもよい。ただ、私は思うのである。幸村が冬夏の陣に大坂方の武将として戦い、討ち死にしたことは史実である。しかし、幸村の心情がいかなるものであったかというのは、結局のところ想像でしかないのではなかろうか。小林氏と北川氏、お二人とも歴史家であるが、上記の見解に限って言えば、すこぶる文学的な印象を受けるのであるが、いかがであろうか。別にそのことを咎め立てるつもりはない。私の本音は、「皆さん、文学の世界へようこそ」である。