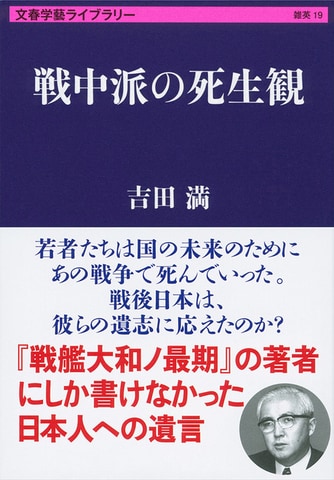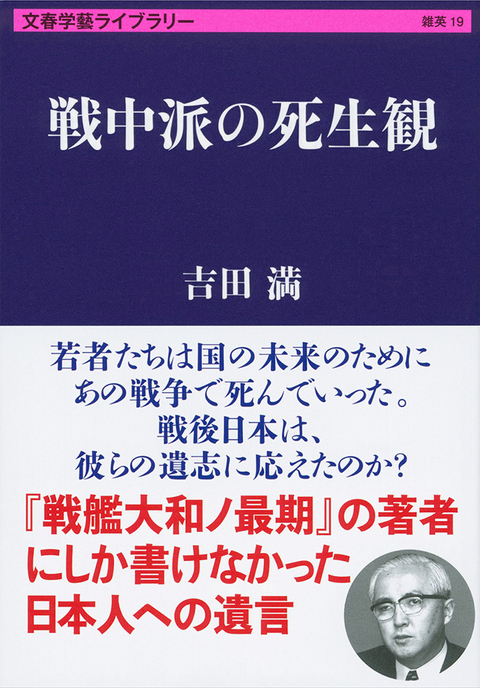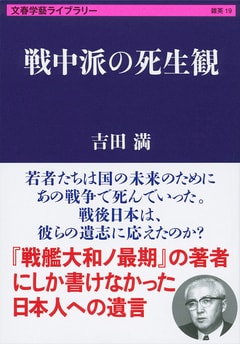このときの吉田の驚きは想像に余る。文章家としては無名の人物の草稿を、当時、もっとも優れた文学者の一人が手にしながら立っているのである。
先に引いた一文「めぐりあい」の冒頭で吉田は、小林の近くにいた白洲正子の一文「鶴川日記」を引きながら、自作の辿った数奇な運命を語りはじめた。小林は、正子の夫であり吉田茂の側近だった白洲次郎に、この作品の意味を語り、発表と刊行をめぐってGHQ(連合国総司令部)との交渉を願い出ていたのだった。
だが、吉田の文章からうかがい知ることができるよりも小林の、吉田の作品への思いはずっと烈しかったようなのである。吉田の没後に発表された『白洲正子自伝』には、吉田の著作をめぐる小林の姿がより生々しく活写されている。
終戦の翌年、「それは秋の夕暮れ」のことだった。彼女の家の周りは田んぼで、最寄りの駅の鶴川駅との間には、ほとんど家はなかった。田んぼの「一本道をせかせかと歩いて来る」一人の男がいる。小林だとすぐに分かったと書いたあと、正子はこう続けた。このときが次郎だけでなく、正子と小林が初めて出会ったときでもあった。
「玄関(土間)へ入って外套をぬぐ間もなく、暖炉の前に座っていた白洲〔次郎〕と、ろくに挨拶もせず早口に喋べりはじめた。まわりにいる河上〔徹太郎〕さんも私も子供たちも完全に無視され、進駐軍から貰ったとっときのウィスキィにも手をふれなかった。
これこれしかじかで、……今、どうしても出版しなければならない本なのだ。よろしく頼む。──会談はそれだけで終った。
小林さんの単刀直入の話しぶりは気持よく、初対面の人間を全面的に信用している風に見えた。白洲もそういう人間が好きだったから、話は一発できまり、必ず通してみせると胸を叩いた。あとは酒宴となり、世間話に打ち興じたが、著者の吉田満のことを小林さんが『そりゃもうダイアモンドみたいな眼をした男だ』と、ひと言で評したのを覚えている」
「求道する文人の悲願(2)」に続く