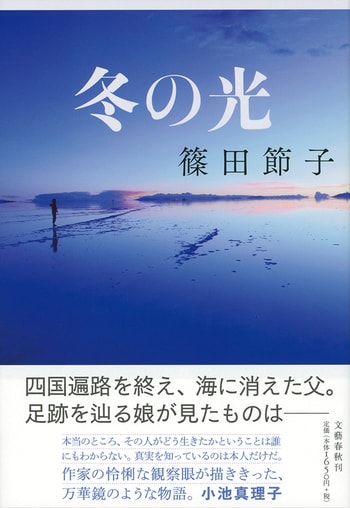篠田 災害が起こると、まず支局があるテレビと新聞が現地に入って、インターネットでも速報が流されますが、一つ遅れて取材した週刊誌の記事は今、そのときということでなく、ややスパンの長い、まとまった情報になる。「実はこうだった」とわかるという点で、貴重ですね。
石垣 災害時は、テレビとか新聞、僕たちは車で移動していたのでラジオを一番重宝しましたが、大手メディアを通して、安否情報や自治体の発信する情報などを速報で知る。一方、週刊誌は、国の対応のような、大きな流れの中で見落とされているものを探して報道するというのが、基本的なスタンスです。
篠田 なるほど、被害者の身近で起こる、小さいけれど切実なことがらは見落とされるでしょうからね。私が拝読した石垣さんの取材メモは、震災から一カ月間の記録でA4四十枚にも上ります。その中には、私たちがテレビやインターネットニュースで窺いしれなかったエピソードや実態というのがたくさん出てきました。一つ一つ自分の目で確かめて人に寄り添う取材が、行われたのだなと感じました。
石垣 そう思っていたんですが……。記者としてそれまでにも人が亡くなる事件を扱ってきたというところで、そもそも死体を見ることはないわけです。ところが現地入りした直後は本当に死体がゴロゴロあって、こんなこと今まで経験がない。どこまで行っても全部沿岸部は町がなくなってしまっていて、聞けば聞くほど、生き残った人、死んだ人が紙一重なんです。膨大なみなさんの体験を全て正確に伝えようというのは、どだい無理なんじゃないかと思いながら取材していました。
篠田 家族を失い、家、土地、財産を失い、仕事を失い、すべてを失うという経験ですものね。
石垣 生き残ったことに関して、最初は皆さん、言葉は悪いかもしれませんが、興奮状態でした。身内や友人、同僚など知り合いが亡くなった中で自分が生き残っている意味みたいなものを本能的に考えると思うんです。ところが、時間が経つにつれてどんどん現実に打ちのめされていく。「生き残ったからこそ死んだ人の分も頑張って生きるんだ」と言っていた人が、一年後に会うと「仮設で一人、気が付いたら死ぬことを考えているんだ」と言ったりしているんです。今もずっとあの日の地続きに生きている方たちがたくさん居る。
篠田 私は一九九八年、内戦後分断されているキプロスの非武装緩衝地帯に入ったことがあります。その時に、住人の方々に会うたびに、「ここでこういうことが起きているというのをとにかく世界に発信してくれ」と言われるんです。帰国後、旅行記や小説で紛争を取り上げた際も、キプロス観光局の方までが、「あの場所でああいうことが起きていることをとにかく世界の人々に知ってほしかった」とおっしゃっていたのが印象的で、報道の役割をあらためて考えさせられました。災害取材に丁寧に答えてくださる方々の心の内には、とにかくこの事実を知らせてほしいんだという痛切な気持ちがあるんじゃないでしょうか。
石垣 その通りだと思います。ただ、あれほどの規模の災害が起きた時に、週刊誌記者として何ができるのか、ほかにやりようがなかったのか、今でも考えることがありますが、答えは出ていません。こうやってお話を聞いてもらえるだけでも少しは昇華できたんだと思いますが。