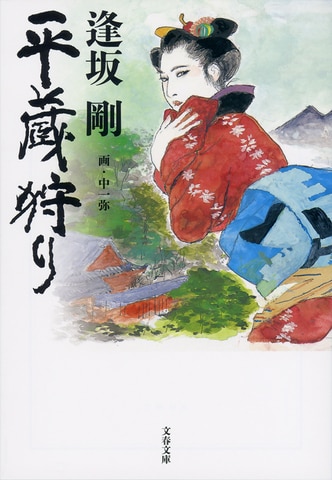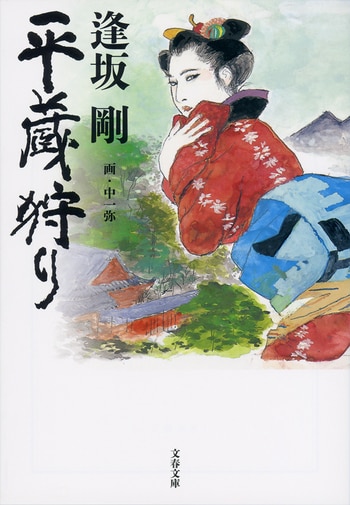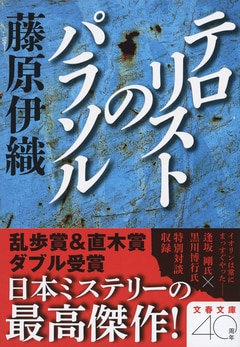鬼平の江戸料理
逢坂 鬼平のもう一つの魅力といえば、食事のシーンだと思います。我々が暮らす現代で食されている料理が出てくるのは、ちょうど寛政のころからです。
諸田 池波さんは、季節感を出すためにいろんな食べ物を書いていらっしゃいますが、このころから鰻や天婦羅がはやるなど、味覚を楽しみ始めたようですね。
逢坂 ところが、食べ物で季節感を出す、という池波さんの手法を聞いたとき、ちょっと不安を感じたんです。つまり、現代の我々が食材や料理で季節感を感じられるのかどうか、と。
諸田 確かに、現代は、年がら年中いろんなものを食べられますからね。
逢坂 今回は鬼平の対談ということで、かつて私が携わった「鬼平の江戸料理を再現する」という企画に、一緒に取り組んだ「なべ家」さんにきているんだけど、今日楽しみにしてきた鮎が六月のものだとか、もしくは、鰻の辻売りの場面が出てきたときに、これが何月だというのは、なかなか伝わりにくいんじゃないかと。
諸田 そういうズレはだんだん出てきますよね。
逢坂 池波さんはね、分かる人に分かればいい、あるいは読者はそれぐらいのことは承知の上だというふうに、読み手を非常に高く買った小説を書いていらっしゃった。
諸田 とはいえ、池波さんの小説を読むことで、自然と食材と季節の関係性を学ぶことができる、という楽しみもあると思います。
逢坂 もう一つ驚くことがあるんです。鬼平の連載が始まったのは昭和四十年代前半です。当時は、長谷川平蔵という人物も、火付盗賊改という役職もほとんど知られていなかった。そしてずっと後に、松平定信の側近が書いた『よしの冊子』という本が活字になったんです。当時の噂話を集めたものなんですが、そこに、長谷川平蔵にまつわるエピソードがちょこちょこ出てくるんです。
ところが、池波さんは執筆当初、この資料を読んでいないはずなんです。
例えば、当時の火盗改というのは、ある男を勝手に捕まえて、厳しく調べて犯人じゃないことがわかったら、もう帰れと放り出してそれっきりだった。ところが、長谷川平蔵という男は、捕まえた男が無実だったとすると、「すまなかった」と言って、お金を持たせたりしたと書かれている。
また、死刑が実行される直前に、「おまえもいっぱしの大泥棒ならば、ちゃんと着替えて、きれいな格好をして死にたいだろうから」って、着物をつくってやったりしただとか。
どうせ捕まるなら、町奉行よりは長谷川平蔵に捕まりたいと泥棒たちが言っている、そんな逸話が『よしの冊子』に書かれている。
諸田 ええっ。その逸話は、まさに池波さんが描いた鬼平そのものじゃないですか。池波さんはどうして、鬼平の実像を知ることができたんでしょうか。
逢坂 作家としての勘としかいいようがない。鬼平という人物像を考えつくしたからこそ、見えてきたのではないでしょうか。
ただ、池波さんと江國滋さんとの対談を読み返すと、池波さんも、鬼平を楽々と書いてきたわけではないことがよく分かります。
諸田 とにかく池波さんは、毎号の締め切りまでに何かを書かなくちゃいけない。書けないときにベニィ・グッドマンのレコードを聞いたり、映画を見たり、散歩をしたりしていたというインタビューを読んだときには、「あっ池波さんもそうなんだ」と気が楽になりました。
逢坂 苦しみながらも池波さんは、シチュエーションから書き始めるんですね。
平蔵が市中見廻りの途中に大根河岸にある料理屋に入って、名物の兎汁で酒を飲むという場面を考える、そうすると、誰かの聞きなれた声が聞こえてくる、やがて連想が連想を生んでしだいにペンがすらすらと進んでいく――と。
私は作家になって二十七、八年が経ちますが、ようやく、池波さんがいうところの人物が勝手に動き出すという境地を知ることができた。
諸田 すごくよくわかります、なんていうと大先輩に恐縮なんですけれど、二、三枚書いて本当に筆が進まないんだけれども、あるところを超えたときに、すーっと書ける……という感覚はありますよね。
逢坂 池波さんが、五枚書けたっていうことは、次の五枚、十枚の内容が頭に浮かんでいるということなんだと、おっしゃってますが、なるほどと思う。これを読んで、そうだそうだ、と思わない作家はいないんじゃないかね。まあ、それができるかどうかは別問題なんだけれども(笑)。