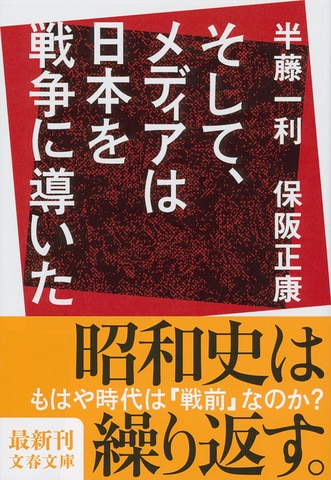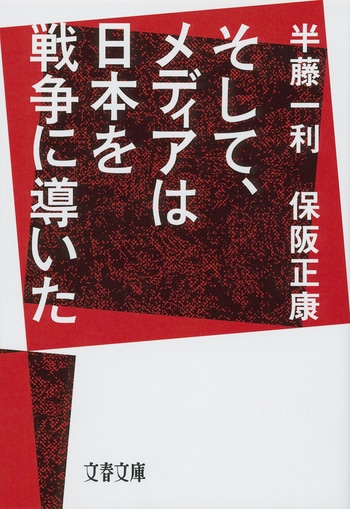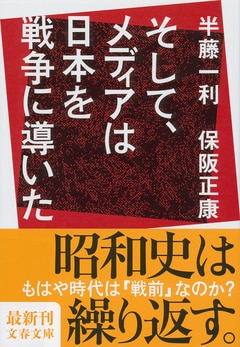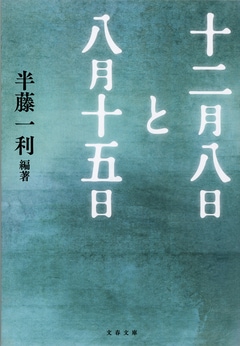文庫版に寄せて
二〇一五年は「戦後七〇年」であった。この「戦後」とは、太平洋戦争終結から七〇年ということになるのだが、もっと具体的にいえば八月一五日を七〇回迎えたともいい換えうる。
従ってあの太平洋戦争とその後の七〇回の空間をどのように見るか、は私自身大いに興味をもって見つめていた。〈同時代史〉から〈歴史〉へ、史実の解釈はどう変わっていくのかが楽しみだったといってもいい。そのような興味をもっていたので、二〇一五年は私も講演やシンポジウムなどの依頼をできるだけ引き受けることにした。政治色、宗教色の強すぎる団体の講演や日程の都合のつかない講演は断ったが、それでも定期的な講演(たとえば朝日カルチャーセンターや中日文化センター、道新文化センターなど)を加えて合計で一二三回の講演を行った。
この書を著していたためか、新聞社、放送局、それに民報連、出版労連などのメディア関係も幾つか引き受けた。一般的な講演と異なってメディア関係の講演会には三つのタイプがあり、それぞれ出席者が異なっている。三つとは、メディア従業員向けと、そのメディアが主催する一般講演会、そしてその地域の政財界、官界などのリーダーが出席する昼食会である。メディア従業員の出席する講演は、各メディアの現状がもっともよく理解できる。そういう折りの私の感じた空気は、正直なところ少々「権力」に鈍感ではあるまいかということだった。経営陣の中からは、若い記者諸君は与えられた仕事はきちんとこなすが、もう一歩前に出て報道するという気構えがない、との不満を漏らす声も聞かれた。逆に若い世代には、もう少し腰を落ちつけて仕事がしたい、日常が忙しすぎるとの不満もあった。
あえて私見を言っておけば、各メディアはもっかコストカッター(必要経費の削減、あるいは徹底した予算主義というべきか)の時代といえるのではないかということと、安倍政権の硬軟とりまぜてのメディア対策に困惑、ないし怒りを持っていることが感じられた。権力対メディア、という図式が明確になっているかのようで、いわばこの書でも指摘した図式が露骨になっている。政権側が気にいらない報道内容に、「客観性」や「公平中立」という語を自らに都合よく解釈して、クレームをつけるというのは弾圧の第一歩である。
これにメディアは抗しきれるのか、とくに史実解釈ではどうなのか、同時代史の解釈を侮辱するかのような歴史解釈が公然化するのではないかとの危惧が私には感じられた一年であった。
「戦後七〇年」ということで幾つかのメディアの七〇年企画に直接、間接に関わることになったが、そこで印象に残った企画を二つ挙げておきたい。
その第一はこの年一月一日の北海道新聞の七〇年企画記事のスクープである。昭和一八(一九四三)年五月アッツ島玉砕のあと、アメリカ軍は北方コースでの日本本土上陸作戦を具体的に考えていたとのアメリカの公文書をワシントンの国立公文書館から探しだしてきたのである。この企画に関わった三〇代、四〇代の記者たちと接しながら、このような地道な努力を続けうるその仕事ぶりに、私は強い感銘を受けた。
この世代の中で誠実に史実に向き合う姿とは、こういう仕事ぶりをいうのであろうと実感した。
第二は南日本新聞の特攻に関する連載記事である。二人の記者が一年余にわたり、この記事を担当し、鹿児島県に限らず全国的な視点で取材を続け、かつての特攻作戦の全体図を具体的に描いている。全国各地に取材に赴き、関係者やその遺族を探しだし、その正直な声を紙面に反映させている。こうした企画に取り組んだ編集幹部と二人の記者に、私は敬意を表したいと思う。
このほかにもまだ印象に残る企画はあるが、この二つはとくに特筆すべきと考えて、本書でも紹介しておきたい。将来のメディアの役割をこうした記者たちは着実に実践しているように思う。
平成二八(二〇一六)年 一月
(「おわりに」より)