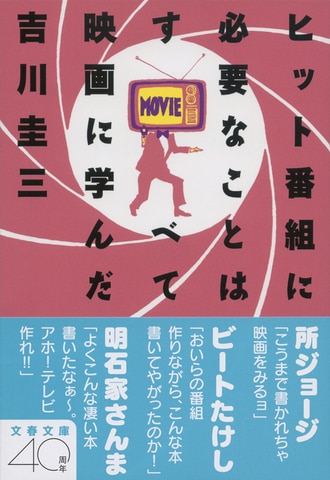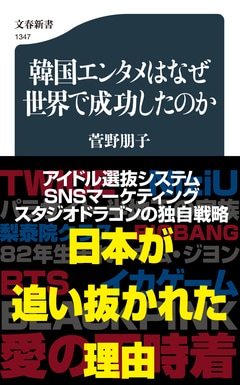本書の内容を一言でいえば、古今東西、膨大な数の映画をあえて「ジャンル論」という網目の大きな“ふるい”にかけて、選り分けられたものを、ためつすがめつ、さらに徹底的に解剖・分解し、「面白さ」のエッセンスを煮詰めだした本、といえるかもしれない。そのエッセンスを端的に示しているのが、各ジャンル論の本文の最後に添えられた「テレビ屋の考える『〇〇映画』のツボ」と題した三箇条だ。例えば、ホラー映画の章の「ツボ」はこうある。
(1)無人島、山小屋、宇宙空間……どこにも逃げ場のない「閉鎖空間」という設定。
(2)実際に起きた事件は最高の素材だが、フィクションの混ぜ方に妙技あり。
(3)何が怖いといって、本当に一番怖いのは、実は生きた人間である。
ぼくもエンタテイメントの業界で仕事をしてきた人間だから、観客がどういう部分に反応して「面白い」と感じるかについては、並々ならぬ興味と関心を抱いてきたが、こうやって示されてみると、なるほど、と頷ける部分が多々ある。さらに、当然のことながら、ホラー映画にはホラー映画の、戦争映画には戦争映画の、恋愛映画には恋愛映画の「面白さ」があるわけだが、それぞれについて「ツボ」をあぶりだしてみると、人間が「面白さ」を感じるときというのは、理屈よりもどこか生理的な感覚に訴えかけられたときなのだな、ということもうっすらと見えてくる。
映画もテレビも、人間が五感を駆使して鑑賞するメディアとして共通項が多くあることは言うまでもない。違いがあるとすれば、映画はとりあえず劇場まで足を運んでもらえれば、よほどつまらなく作らない限り、観客は最後まで作品につきあってくれる(しかも暗闇で)が、テレビは吉川さんも書いている通り、視聴者はチャンネルひとつで、番組に「死刑」判決を下す。その意味では、よりダイレクトに瞬間的に、人間が「面白さ」を感じる“スイッチ”を押す必要があるのだろうと思う。
吉川さんがテレビの世界で名だたるヒットメーカーであることは既に述べたが、彼がその“スイッチ”を探すために、映画や本に淫することはもちろん、街で他人のおしゃべりに耳を傾けたり、外国の番組を研究したり、あらゆる手を尽くしてきたことは想像に難くない。
そう、テレビに、それもヒット番組をつくるのに必要なことは、すべて彼の日常にあるのだ。日々の精進、365日、休みはない。とはいえ、それは彼にとっては趣味であり、楽しいことでもあるのだが、重要なことはインプットすべきものとそうでないものを選別し、必要でないものは容赦なく切り捨てることだ。だから、容量がいっぱいになって困るということがない。
そうした一連の作業を通じて、吉川さんはバラエティに向く知識と才能を知らず識らずのうちに作り上げて行ったのだろう。本書には、彼が見つけ出した“スイッチ”が惜しげもなく披露されている。映画好きの方はもちろんだが、テレビや映画などエンタテイメントの世界で、何かを創ってみたいと考えている若い人たちは、ぜひ本書を手にとってみることをお薦めしたい。