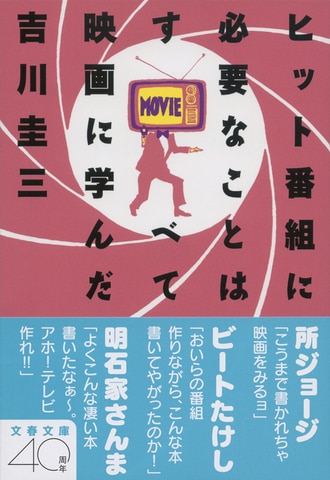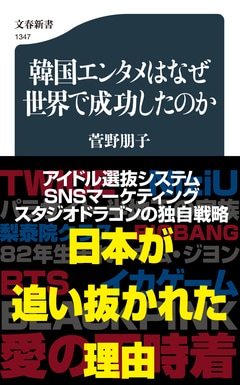「茫洋の人」
それが、ぼくの吉川圭三なる人物への“第一印象”だった。本書の24ページで、吉川さんは今を遡ること20年前に初めてぼくと出会ったときの印象を、「歩く達磨ストーブ?」と評しているが、ぼくの方は、旧知の奥田誠治プロデューサーが連れてきたテレビマンの正体を掴みかねていたのだ。
風貌は、若くして大人(たいじん)の風があるようにも見えなくもないが、単にボーッとしているだけのようにも見える。いかにも敏腕テレビマンというような才気走ったところがないのが、逆に新鮮だった。その吉川さんが、挨拶や世間話もそこそこに、おもむろにやけに大きなカバンの中をゴソゴソ漁(あさ)って、「こんなものを描いてきたんですけど」と取り出してきたのが、本書でも書かれたとおり、例の「紅の豚バス」のイラストだった(その出来については、ノーコメント、ということでお察しください)。その間、ほとんどこちらと目を合わせることもなく、「どうでしょうか」と言ったきり黙っているものだから、こちらも何となくOKするより仕方ない雰囲気になったのを覚えている。
「変なヤツだなあ」と思いながらも、それ以来、何となく「日本テレビの吉川」という名前が、ぼくの中に刷り込まれてしまった。次にその名前を目にするのは、ぼくが好きで見ていたテレビ番組のクレジットに「企画 吉川圭三」とあるのを見つけたときだった。ぼくは元来テレビを見ない人間なのだが、その番組「特命リサーチ200X」は、ぼくとしては異例なことに、毎週リアルタイムで見ていたのだ。SF映画を思わせるセットで俳優たちが調査機関の調査員の役を演じるフィクションの舞台装置でありながら、とりあげる題材はあくまでノンフィクションという画期的な知的エンタテイメントだった。テレビ史上に残る傑作だと思う。日曜日のゴールデンタイムに、よくぞああいう知的好奇心に満ちた娯楽番組を作ることが出来たもんだ、と密かに感服していた。
そうやって気づいてみると、多くのヒット番組に「吉川圭三」が関わっていることを知るようになる。「あの人は、日テレでビートたけしさんや明石家さんまさんに最も信頼されている人なんですよ」という風に教えてくれる知人もいた。
極め付けのエピソードとしては、故・氏家齊一郎会長にこんな話を聴いた。日テレが10年間、視聴率四冠をとり続けた頃の話だ。
「テレビというのは、実際にはごく少数の優秀な才能で作られている。プロ野球と同じで、エースは毎日投げるものだ」
その代表選手として、氏家さんが挙げたのが他ならぬ吉川さんの名前だった。
それから吉川さんとは、面白い映画や本の情報をお互いに交換したり、ぼくが何気なく話したエピソードを吉川さんが早速番組の中でとりあげたり、とかで今では日に一度はメールを交換するようになった。
といった20年来の経緯もあって、スタジオジブリの雑誌『熱風』に「新・仮説・エンターテイメント進化論」と題して吉川さんに連載していただいたのが、本書『ヒット番組に必要なことはすべて映画に学んだ』のモトとなっている(だから、ぼくに「製造者責任」がある、ということで「解説」の御鉢がまわってきたのだろう)。