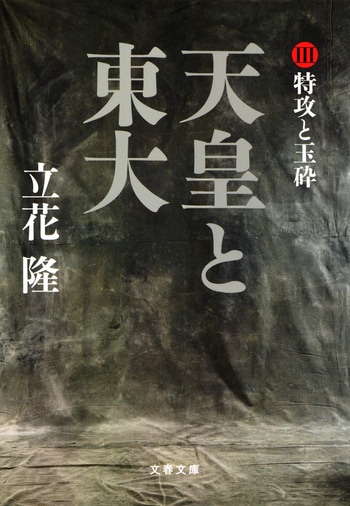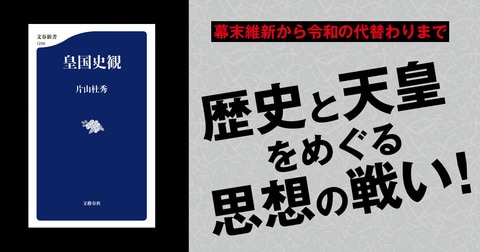経済学部の戦後大転換
数ある学部のなかでも、経済学部は最も入営者の比率が高かった学部である。
柴田徳衛(東京都立大学名誉教授・東京経済大学名誉教授・元東京都企画調整局局長/経済学部経済学科/昭和22年9月卒)は大分の特攻基地で終戦を迎えた。
「終戦時、私は学徒動員で海軍第五艦隊司令部におりました。8月15日は、鹿屋から大分に移動したところで、詳しいことは城山三郎さんが『指揮官たちの特攻』でお書きになっているような次第でした。
終戦の詔勅はラジオで聞いたのですが、よく聞こえず、負けたのかどうかもわかりませんでした。
『本土決戦になる。関係書類は燃やせ』
と、命令があって、それに従っておりましたが、4~5日してから、ようやく武装解除となりました。それでも、残務整理に追われたものです。
私は東京出身なので、自宅へ帰り、東大へ様子を観に行ったのは、10月頃だったと思います。驚きましたね、御茶ノ水の駅から安田講堂が見えるんです。だが、かつての通学路周辺がすべて焼けているので、どうやったらその安田講堂へ辿りつけるのか、道順がわからず当惑しました。
私たちの同期は、昭和18年の徴兵猶予廃止によって、動員されました。この学徒出陣で、文系の学生はほとんどいなくなった。私は早生まれだったので、翌19年の召集でした。18年の暮れあたりから、19年春にかけて、経済学部の講義は先生ひとりに対して学生が1人か2人。そんな状態でした。おかげで、講義は丁寧でしたけど。ただし、勤労動員があり、千葉・検見川へ芋掘りに行ったり、海軍工廠へ魚雷を磨きに行ったりもしていましたね。戦前、ハーバード大に留学していた某先生が、私たちが魚雷を磨いている姿を見て、
『なんでアメリカと』
と、それ以上は口にせず、涙していた姿が今も印象に残っています」
海軍経理学校の試練
諸井勝之助(東大名誉教授/経済学部商業学科/昭和21年卒)は宮崎の海軍施設部にいた。
「私は終戦ではなく敗戦と呼んでいるのですが、海軍で鹿児島にいたときに敗戦となりました。
私が大学に入ったのは昭和17年10月です。翌18年12月1日に学徒出陣がありました。このときは、大正12年12月1日までに生まれた満20歳以上の人が取られたのですが、私は13年2月3日生まれで、2カ月違いで免れたんです。その後、19年9月に築地にあった海軍経理学校を志願して試験を受け、主計課短期現役の見習尉官として入学しました。陸軍に入って二等兵からやるのはいやでしたからね。東大からは法学部の学生が多く、京大や一橋、高専の学生もいました。
経理学校に入るまでの2年間は、大学でちゃんと授業を受けていました。学徒出陣の後は、私のように20歳未満だった若い人や、軍の検査で不適格とされ即日帰郷となった人たちが、少人数で授業を受けていました。人数が少なかったのでとてもよかったです。大塚久雄先生の経済史などの授業は印象深く記憶に残っています。どの先生の講義にしても、軍国主義を感じることは、あまりありませんでした。
学校の指示で勤労動員にも行っていました。19年3月には韮山付近で暗渠排水の土木作業をやりました。このときは農家に泊まったのですが、牛乳や卵など、当時としてはご馳走を食べさせてもらいました。千葉に麦刈りに行ったこともありましたが、千葉の方は食糧事情が悪かったですね。
経理学校に入ってからの6カ月間は、猛烈な訓練を受けました。前半はまず駆け足です。勝鬨橋のたもとから、相生橋、門前仲町、永代橋、日本橋、聖路加病院付近を通って、学校に戻る約8キロを、35分ぐらいで走りました。時には、このコースを1日2回、3回と走らされることもありました。学校には900人ほどいて、10人1組で走っていましたが、おばあさんが私たちに向かって手を合わせていて驚いたことがあり、そのことを日誌に書きました。
後半はカッターです。短艇のことですが、隅田川を何往復もしました。当時の隅田川は魚がいるほどきれいでした。冬には、朝にオールに霜が降り、冷たくて大変でした。
さらに、昭和20年2月には陸戦の訓練がありました。藤沢の先の辻堂に海軍演習場がありました。近くの民家に3~5泊し、戦闘の基本を学びました。運悪く、大雪になりましてね。雪がじゃんじゃん、30センチも降り、その中で朝6時から真夜中まで、乾パンと水だけで訓練を受けました。これはとてもきつかった。倒れる人が続出し、最後は教官もやむなく中止しました。
経理学校では、経理の座学もありました。金銭経理や物品会計などは大尉クラスの人が教えていました。しかし、戦時統制法を教えていた石井照久先生や、科目は忘れましたが田辺忠男先生など、東大から教えに来ていた先生もいました。体力を消耗しないので、座学はうれしかったですね。
経理学校の食事は、民間よりはいいとされていて、確かにはじめのころは夜食に甘いものが出るなどよかったのですが、空襲が激しくなり軍の倉庫が焼けてしまってからは、とたんに悪くなりました」
着任した日に200人が死傷
戦局はますます厳しくなっていった。
「昭和20年4月に経理学校を卒業しました。そのころ軍艦はほとんど沈められてしまって、軍艦に配属されたのはわずかで、ほとんどは陸上でした。私は、呉の海軍施設部に配属され、そこから宮崎に行かされました。宮崎は当時、呉の管轄だったのです。
宮崎には飛行場があり、特攻機が出撃する基地になっていました。その基地施設の面倒をみる内務主任というのが私の肩書きでした。私が着任した当日、滑走路を狙ったB-29の爆撃がありまして、年輩の徴用者を中心に200人以上が死傷しました。初日の仕事が死骸の片づけだったのを覚えています。その爆撃であいた滑走路の穴を埋めるのが私の部隊の仕事で、セメントや砂利などの物資を部隊に調達しました。落とされた爆弾のなかには爆発していないのがあったのですが、それらは不発弾ではなくてタイマーが付けられた時限爆弾なのです。部隊の人は、いつ爆発するかわからない恐怖を感じながら、穴に埋めました。
やがてそうした作業もできなくなりました。敵の空母が近づき、艦載機が飛んでくるようになったのです。昭和20年の6月ごろです。機銃掃射が激しくなり、パイロットたちは美保関に移っていきました。いまの宮崎県日向市や日南市が『回天』などの水中特攻の基地になっていましたから、私はそちらの仕事で宮崎に残りました。
このころには、制空権が奪われたため、宮崎は呉から佐世保の管轄に移っていました。佐世保の支部が鹿屋にあり、その支部の経理部が鹿児島市にあったのですが、8月になって、支部の人から『8月15日正午にトラックを用意して集合せよ。いま保管している物資を分配する』という指示がありました。そこで、8月14日の夜に宮崎を出て鹿児島に向かいました。到着したら、みんなの様子が何か変なので聞いてみると、玉音放送があったということだったんです。だから、私は玉音放送は直接は聞いていません。
みんな頭をどう整理していいかわからないという唖然とした状態で、混乱し、興奮してもいました。私もムシャクシャしたので、特攻基地にいた友人のところへ行き、敗戦について論じ明かしました。翌16日には、防空ごうの中に入って、興奮状態で飲めない酒をがぶ飲みしました。大事にとってあったウィスキーや焼酎などを、海軍の湯飲みで飲み干しました。
10月末までは、残務整理で宮崎に残っていました。書類を焼けという指示が来たかと思うと、焼くなと指示が来たり、大混乱でした。私は、戦時中に軍が民間から買ったり借りたりしていたものの清算や支払いをやりました。かばんに大金を詰め込んで、鹿児島の経理部から宮崎に持ち帰り、支払いに行ったこともありました。
大学に復学したのは20年11月です。敗戦だから、先生や講義内容が変わるのは当然です。ただ私は不思議と、そうした変化にとまどったり、おかしいと思ったりすることはありませんでした」
大内、矢内原、有沢ら復職
経済学部は、敗戦と同時に学部内が一変した。昭和20年9月には橋爪明男経済学部長が退任し、舞出長五郎学部長のもと教授会を開き、11月4日に確定した。これにより、戦前に追放されたマルクス系経済学者の大内兵衛教授、有沢広巳助教授、矢内原忠雄・土屋喬雄元教授、山田盛太郎・脇村義太郎元助教授が経済学部に復職し、これらに批判的だった橋爪明男・荒木光太郎・中川友長教授、難波田春夫助教授が追放された。これは、学生にとっても大きな出来事だった。
「戦後の経済学部は大きく変わりました。以前に大学を去った教授たちが帰ってきて、戦争のために協力した教授たちが追い出された。追い出されたというより、自分たちで辞めていったと言った方が正確かもしれませんが。
学生もいろいろな考えの人がいましたが、こうした教授たちの入れ替わりを、学生の大部分が喜んでいたのは事実です。
戦時体制のおかげで教授になったファシストの教授たちが辞めていき、大内教授、有沢教授といった優秀な人たちが帰ってきたわけですからね。
私は陸軍に入って見習い士官として姫路にいたのですが、けがをして入院しているときに終戦となりました」(尾上久雄/京大名誉教授/経済学部経済学科/昭和22年卒)
「大学では先生の顔触れがガラッと変わりましてね。講義の内容もすっかり変わり、私個人としても張り切っていましたし、経済学部全体としても張り切った雰囲気がありました。財政論の大内先生や農業政策の山田先生など、クビになった先生たちが戻って来ていて、そういう先生たちの授業はいつも学生でいっぱいでした。
私は昭和17年に入学したのですが、そのころの授業というのは軍国主義の講義ばかりで面白くありませんでした。しかし戦後は、大内先生が『戦争は儲かるか』というテーマで講義をし、戦争批判をしていた。河合先生や大河内先生の本を読んで頭に描いていた『本来の経済学部』に戻るんだという感じを受けました。
昭和18年に学徒動員となり、終戦は愛知県豊田の海軍航空隊で迎えました。私が大学に戻ったのは、9月の末ごろでした。残務整理で軍に残らされた人もいましたから、比較的早い復員でした。2年生で復学したわけですが、その年からゼミが始まりました。試験を受けて大河内先生のゼミに入りました。戦中の大学では感じられなかったような学究的な雰囲気がありました」(浜誠/元兼松専務/経済学部経済学科/昭和22年卒)
教室が足りない
前出の柴田徳衛はこう語る。
「20年11月、大内兵衛さん、矢内原忠雄さん、有沢広巳さんら経済学部教授が復職された。私が復学したのは、同年12月。当時の学部長は、矢内原忠雄さんでした。
食料難で、靴1足が米1升とか、物々交換をして飢えを凌いでいましたが、本が割りといい値段で売れるものですから、その時、ずいぶん食料と交換して、手放してしまいました。困ったのが、学内に暖房がない。寒さで指がかじかんでノートをとることができず、苦労しました。それと、先生が、右翼疑惑でGHQのパージにあい、しょっちゅういなくなる。逆に、かつてパージされた大内兵衛さんなどが解放されて復職していたわけです。
大内兵衛さんは、岩波から『財政学大綱』を上梓しているのですが、上巻と中巻しか出版されていなかった。下巻を書き終えたところで、昭和13年2月の教授グループ事件で検挙され、下巻はお蔵入りとなっていた。当時の私は、下巻の存在に気づいていませんでしたが、下巻は、地方財政だった。その後、私の研究分野となる領域です。私は大内先生の財政学を熱心に受講していたのですが、先生も人が悪いというか、聞かなかったこっちもいけないけど、下巻の存在などまったく口にされなかった。私は当時から地方財政に関心があって、その重要性を友人に説いていたのですが、
『地方財政なんて、主流じゃない。大内先生だって論じていないじゃないか』
なんて、言われると反論できませんでした。東大の教授のなかには、
『地方財政なんて下卑たものは触らないよ』
なんて、見下す先生もいました。でも、大内先生はすでに昭和13年の時点で、『財政学大綱』下巻に農村財政と地方財政を論じて、その重要性を指摘しておられたのです。
大内先生の講義は経済学部の二十五番教室でおこなわれたものですが、私もそうですが、有難くて涙した学生が何人もいるほどで、いつも満員の人気でした。
私たち復学してきた学生の成績に関しては、講義に顔を出しただけで、『よく生きて帰った』と、ポン、と『優』をもらえた。昭和21年から22年にかけて、試験に合格して入学してくる学生と、復員して復学する学生とで人数が増え、教室が足りない状態に陥りました。事務局に呼ばれまして、『単位はいくらでもやるから出て行ってくれ』と、言われたものです。だから私の成績なんて、いいかげんなものです。大学を出てから、もう一度しっかり勉強したい、と願っていたところ、うまい具合に都立大学が新設された。そこで助手をしながら都市財政の研究をしていたところ、フルブライト奨学金でアメリカへ行けることになった。留学先は、コロンビア大学。そこでシャウプ勧告のシャウプさんと出会い、その下でニューヨークの都市財政を研究することができました。その研究を都立大で発表したところ、それを都政にも活かしたい、と鈴木元都知事をはじめとして東京都関係者に誘われ、企画調整局の仕事などをすることになります」
東大生はアホではなかった
この一大転換を諸井勝之助(前出)はこう語る。
「矢内原忠雄先生のような立派な先生が大学に帰ってきたことはとてもよかったと思います。私は矢内原先生の帰ってきてからの最初の講義を聞き、これは素晴らしい先生だと思って、先生のゼミに入りました。
戦中から戦後で、右翼から左翼へと大学ががらりと変わったように言う人もいますが、私はそんなものではなかったと思っています。確かに先生が変わりましたが、その一方で、私の研究室の先生だった会計学の上野道輔先生をはじめ大河内先生や大塚先生のように、戦中からずっとおられた先生もいたわけで、そういう先生はいい講義を続けていました。敗戦で大きく変わった部分はありますが、世の中とはそういうもので、そのとき東大がうろたえていたということはありませんでした。
そもそも、昭和17、18年ごろも、軍国主義を感じるようなことはそんなにありませんでしたし、神がかった授業があったわけでもありませんでした。西洋経済史の大塚先生の授業などは、かなり自由だったように思います。天皇機関説の美濃部先生の弟子だった宮沢俊義先生は、憲法について神がかったことは一切言われませんでした。講義はごく形式的なものでしたが、学生はそれほど不満に思っていませんでした。時代が時代ですから、言えないこともあるという背景をちゃんと理解していたからです。
学生だって、戦時中もひそかに資本論を読むなどしていました。昭和18年のことですが、私が持っていた資本論の本を友人に貸したところ、その友人が憲兵につかまってしまいました。どうやって入手したのかと問い詰められて私の名前を出してしまい、私は朝から晩まで取り調べられました。そうやってマルキシズムを学んでいた人も結構いたんです。東大生は、単純に軍国主義に染まるようなアホではありませんよ。
マルクスが自由に読めない時代には、先生たちもマルキシズムを背後に隠し込むようなかたちで論文を書き、読む人が読むと理解できる、レベルの高いものを生み出していました。戦争が終わると、マルクスを自由に読めるという変化はありましたが、マルキシズムをむき出しで書くようになり、内容のレベルが下がりました。
世の中が大きく変わっている点では、ここ数年来の変化も大きいのではないでしょうか。いままで官主導で復興してきたのを、民間ベースでやらなくてはいけないという風に変わってきています。郵政民営化もそうですし、大蔵省の間接金融方式で復興してきた経済が直接金融方式に移っていかなければならないというのも、そういうことでしょう。発展途上国のようなやり方ではだめだということになっているのです。
戦後の復興期には、学生たちはエリート意識があり、復興においては『我立たずんば』という意識がありました。だからこそ、復興ができたのですが、いまはどうでしょうか」