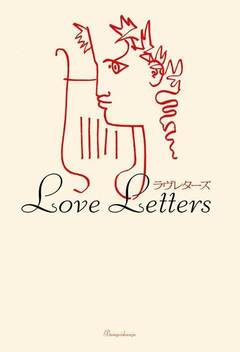二〇〇九年、二月も終わりかけた或る日のこと。横浜にある病院に入院中だった父に会いに行った。
病室の窓からは、少し離れた通り沿いに立ち並ぶ桜の木々を眺めることができた。まだ芽吹きは先だったが、少しずつ温かくなってきたころでもあり、あたりの風景は尖ったものから優しいものに変わりつつあるようだった。
私は父の寝ているリクライニング式ベッドの背を少し起こしてやった。窓の外を指さし、「ねえ、見て」と話しかけた。「あの桜が満開になったら、毎日、ここからお花見ができるわね。このベッドは一等席ね。あ、でも、パパはそのころはもう、とっくに退院しちゃってるからだめか」
父は少しやわらいだ表情になった。痩せ衰え、重度の貧血のせいで顔の色つやも悪く、ひとまわり小さくなってはいたが、目には生きているものの光、生きよう、生きたい、として戦っている人間のかすかな力が感じられた。
自らの意志で胃ろうをつける手術を受けたのが、一週間ほど前。その後の状態はよく、嚥下のためのリハビリも始めており、この分でいけば、口からアイスクリームくらいは食べられるようになるだろう、と主治医から言われていた。
ベッド脇のチェストに置いた小さなCDデッキからは、キース・ジャレットの静かなピアノ曲が流れていた。備えつけのテレビをつければ、騒々しいバラエティ番組やCMばかり。老いて病の床についている者が観て、心慰められるようなものは何ひとつない。何か美しい音楽を聴かせてやりたいと思い、その日、私が急いで持ってきてやったCDだった。
気持ちが澄み渡ってくるような音色に耳を傾けながら、私は時間をかけて父といろいろな「話」をした。珍しいことだった。
ふだん、いつも時間に追われていた。施設に暮らす父に会いに行っても、そばにいられるのはせいぜい一時間ほど。上京のたびに何かと用事が重なるからだが、それは言い訳であり、本当のことを言えば、一時間が限界だったからだ。まったくコミュニケーションがとれなくなった父を相手にし続けるためには、おそろしいほどのエネルギーを必要とした。
父に会いに行き、「会話」を続けようとすると、尋常ではない疲労を覚えた。帰りがけ、頭痛薬を飲み、どこかでいったん横にならないと、次の行動に移れなくなることもあった。
だが、その日だけは違っていた。予定や誰かとの約束や、急いでやらなければならない用事は何もなかった。何より、私自身が父と何か話したい、長く話し続けていたい、という気分にかられていた。
父は長く患ったパーキンソン病のせいで、何か話そうとすると、口腔や喉が烈しく震え、ことばにすることができなかった。そのころはもう、ワープロのキイボードを打つことも、私が作ってやった文字表の「あいうえお」を指さすこともできなくなっていた。