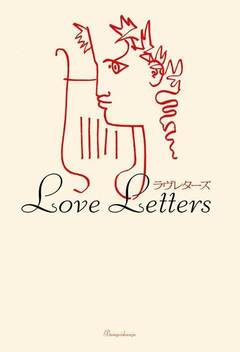ぱぱもまりちゃんに、ぷうします
二十代のころ、私は『知的悪女のすすめ』という煽情的なタイトルのエッセイ集を出版した。作家志望だった娘が、もしかするとついに、そのスタートを切ることができたのかもしれない、として父はたいそう喜んでくれた。
だが、勇んで本を読み始めたはいいが、想像していたであろう内容とのあまりの違いにショックを受けたらしい。数日間、父がふさぎこんでいた、という話は後になって母から聞かされた。
日頃、勇ましいことを言って仕事をし、男友達と飲み歩いていても、自分の娘だけは、キスはおろか、異性と手を握り合ったこともないと信じていたようだ。なんという時代錯誤か、と呆れたが、父が長女である私に抱き続けたらしいロマンティックな夢まぼろしは、概ねそのたぐいのものであり、それは終生、変わらなかった。
私には妹がひとりいて、彼女との間には八歳の年の開きがある。つまり、八歳になるまで私は一人っ子だったわけで、生まれてから八年間、私と父との間に流れていた時間は、ある意味において、蜜月に近いものだったようにも思う。私は父に愛されて育った。
昭和石油(現在の昭和シェル石油)に勤めていた父は出張が多く、出張先からよく、私と母に絵はがきを送ってよこした。
私が、平仮名をかろうじて全部読める年齢になったころには、行く先々の風景がカラー印刷された絵はがきのあて名はすべて私になった。
「ぱぱはいま、きゅうしゅうの、いぶすきというところにきています。まりちゃんと“まま”のいるとうきょうとちがって、とてもあたたかいです。あさってになったら、かえるから、それまで“まま”と、いいこにしてまっていてね」などとあり、最後には必ず、「まりちゃん、ぱぱに、ぷうして。ぱぱもまりちゃんに、ぷうします」と付け加えられていた。
「ぷう」とは「キス」のことである。親子の間で、アメリカンホームドラマのごとく、キスし合っていた、などという覚えはないのだが、「ぷう」という言い方にはかすかな記憶が呼び覚まされる。
出勤しようとする父や、帰宅した父に、私は「ぷう」をしていた。玄関先で腰をかがめ、私に向かって頬を突き出し、「ただいま」と言う父の顔にくちびるを押しつけ、私は湿ったキスをしてやる。父は喜び、満面笑みで私を抱き上げる。そんな光景も、記憶の底に残されている。
日曜の朝には、目覚めるとすぐに父の寝床にもぐりこんでいくのが習慣だった。先に起きて朝食の支度をしている母の気配を感じながら、私は父の寝床の奥深くに、温かく溜まっている未知のにおい、たばこのにおいのような、整髪料のにおいのような、男の体臭のような、そんなにおいを胸いっぱいに吸いこんでは父に抱きついていった。
時には、駄菓子を入れてある四角い缶を枕元に持っていって、父とふたり、うつぶせになったまま、金平糖やカリントウ、色とりどりのゼリービーンズなどをつまんで食べた。二人で歌を歌い、笑い、父の話す物語を聞いた。父はうつぶせになったまま、たばこを吸った。時にはラジオをつけて、音楽を聴いた。
そうしているうちに、母が私たちを起こしに来る。母はにこにこしていて、父も笑っていて、ふたりともとても機嫌がよくて、開け放された雨戸の向こうからは、朝の光が射し込んでくる。
不安なことが何もない、現在も未来もすべてが満ち足りて見えていた。私は父に守られ、愛されていた。父はなんでも知っていて、子煩悩でやさしくて、おしゃれで、電蓄でパティ・ペイジやダイナ・ショアの音楽を流し、むずかしそうな本を読み、幼い私の目から見ても常に第一級のロマンティストだった。
母はそんな父に夢中だった。父も母に惚れ抜いていた。そのはずだ、と長い間、信じてきた。
だが、子供の目に映った情景と真実とが食い違っていたというのは、よくある話だ。
私がまだ赤ん坊だったころ、父は外に女性を作った。その女性は父の子を宿した。
両親の間で、どのようないざこざがあったのかは知らない。赤ん坊だった私には知る由もない。母は私をおぶい紐を使っておんぶし、上野から汽車に乗って女性が身を寄せていた東北の町まで出向いた。
女性というのは、そこそこの旧家の令嬢だったらしい。突然の訪問に驚く彼女を前にして、大きな家の大きな玄関先に立ち、母は自分の背中で眠っている私を指さしながら、「うちにはこんな小さな子がいるんです。主人はこの子をとても可愛がっているんです。お願いですから、あなたのお腹の子をおろしてください」と言って頭を下げた。
その女性は母の気迫に負けたのか、あるいは思うところがあったのか、ただちに腹の子を中絶して父と別れたという。
そういえば、と思い出されてくることは数多くある。母は時々、深夜、眠っている私(三、四歳くらいだったか)を静かに揺り起こし、ねんねこのような暖かなものでくるむと、おぶって家の外に出た。
昭和三十年代の初めころのことだ。あたりは真っ暗で、裸電球だけがぼんやりと灯っている。その明かりの下に立ち、母は私をおぶったまま、長い間、じっと遠くを見つめていた。
電車を降り、長い長い、麦畑の脇の道を歩いて父が帰ってくるのを、母が今か今かと待っていたのだ、ということを知ったのは、ずっと後になってからのことになる。私には母の背の暖かさ、安物の乳液や化粧水のにおいのする、すべすべした首筋の感触しか記憶に残っていないのだが、そんなふうに子を背負い、裸電球の下に立って、父を待ち続けた母の心中は想像するにあまりある。
しかし、母は、父に常に女性の影がつきまとっていたこと、そのことに対する不安、悲しみ、怒り、絶望を娘にぶつけることは決してしない人だった。不機嫌な顔や泣き顔を見せることもなかった。母はいつも機嫌よくふるまっていた。明るかった。私は何も知らずに育った。本当に何も知らなかったし、自分の両親の関係が実は危ういのではないか、と疑ったこともなかった。
私が自分の両親の間に根深い問題がひそんでいたことを知ったのは、私自身が所帯をもってからのことになる。すべては母が教えてくれた。
だが、そうした話を打ち明けた時の母は、ふだんと何の変わりもなかった。怒りも恨みも嫉妬も見せなかった。あくまでも淡々と、まるで知らない時代の昔話でもするかのようだった。
老齢になってからはその穏やかだった性格は豹変したが、初老期を迎えるまでの母は決して父を悪く言わなかった。考えてみれば、ふしぎな人だった。
そして、父の死後、はからずも私は父の、娘たちには決して見せなかった人生の一端を知ることになったのである。
施設の、父の居室に遺されていたのは性具だけではない。父が書き残した膨大な記録の数々、友人知人らとやりとりした手紙類、何かの下書き、備忘録……それらが几帳面にファイルされたものが何冊も出てきた。
そこには彼が人生の中で封印してきた想い、嘆き、熱情、ロマンティックな思考の数々が詰めこまれていた。「ことば」を愛していた彼が遺した無数の「ことば」は、時にペダンティックだったり、過剰に感傷的だったりしながらも、彼の人生そのものを表していた。おそらくは本人も無意識の内だったろうが、自分自身の「記録」という形をとって書かれたもののようにも感じられた。
結婚し、二人の娘をもった、ありふれた、どこにでもいる会社員ではない、別の顔、別の男の姿がそこにあった。それこそが自分の父であったのだ、と知った瞬間、時間が音をたてて巻き戻されていった。それは父の中を流れた時間であり、同時に、私自身の中を流れ過ぎた時間でもあった。