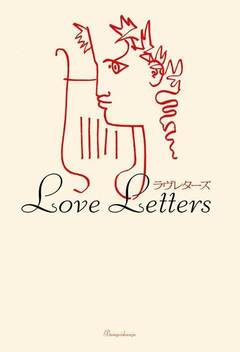ダンボール箱に詰められた遺品
『沈黙のひと』という、父をモデルにした小説の中に、私はいったい、何を書きたいと思っていたのだろう。
大正十二年に、満州大連で生まれた父の人生。引き揚げて来てから学徒出陣を経験し、幾人もの友を失って終戦を迎え、焦土と化した祖国に戻り、絶望のさなか東北帝国大学の法科に進学して学問の道を歩んだ一人の男の、平凡だが、なかなか秘密の多かった人生。そうしたものを描きたかったのか。
それとも、人が等しく迎える老い、衰弱、病……とりわけ、病気のために意志や想いを伝えることができなくなった人間の、心の内側に渦巻くものに迫ってみたかったのか。老いて、病んで、人の手を借りながらやっとの思いで生きている人の、語られずにいる何かを掬い取りたかったのか。あるいはまた、父と娘、夫婦、家族、という、宿命的な関係にメスを入れてみたかったのか。
書きたかったのは、それらをひっくるめたすべてである。それは間違いない。だが一方で、それだけではなかったような気もする。
もっともっと、別の何か……あまりにも抽象的すぎて、なかなかことばで表現することができなかった感覚……まとめたり分析したりすることが容易ではないことをこそ、小説にしてみたかったのではないか。私自身、そのことで長く苦しんだり、切なくなったり、絶望したり、いたたまれないような気持ちにかられてきたことをこそ、書きたかったのではないか。これまでに何度もわきあがってきて、対処に困り果てた幾多の複雑な感情の群れを、ここにきてやっと、整理してみる気になり、その衝動のようなものを父の物語に託してみたかったのではないか……。そんなふうにも思う。
父亡き後、彼が晩年、暮らした施設の部屋の遺品整理に妹と共に出向いた時、私たちは目を疑うものを発見した。
ベッドの裏側の目立たぬ場所に、ガムテープで簡単に封をされたダンボール箱が置かれてあった。開けてみると、中には何種類もの性具が入っていた。幾種類ものバイブと何本かの裏ビデオ。梱包が解かれていない新しいものも、明らかに古いものもあった。
後で知ったことだが、いよいよ父の状態が悪くなって、人の手を借りないと排泄はおろか、口をゆすぐことすら不可能になった時、施設の職員がひとつにまとめて封をしてくれたのだという。
即座に処分しなかったのは、父を慮ってのことだったのか。そんなものでも、父の所有物であることには変わりはなく、勝手に処分するわけにはいかないから、という理由があったのか。それとも、父の娘である私たち姉妹の日頃の様子から、こういったものを発見しても、さして衝撃は受けないだろう、と判断されていたからなのか。
ともかく、私たちは箱の中身を知り、思わず顔を見合せ、その場で笑って笑って、笑いころげて、父が使っていたベッドに顔を押しつけながら、苦しくなるほど笑い続けた。遺品整理をしようとする時の切ない想いは、瞬く間に吹き飛んでいった。
あれほど気取って生きていた父。文学好きで、自らも文章を書き綴ることを愛していた父。ロマンティストな学者肌だった父。時に家族の前で朗々と漢詩を詠みあげ、短歌を作っては投稿し、気の合う人間との文通をこまめに続け、会社関係の人間とのゴルフやマージャンは好きだったものの、賭け事は一切せず、飲みに行った先でみんなのまねをしてホステスのお尻を触れば、手慣れていないのが逆効果になったのか、「いやらしい!」と本気で怒られた、という話を憮然として語っていた父。
たばこは吸っていたが、酒には弱く、胃腸も弱く、私が子供のころは、「温灸器」を買い込んできては、毎晩、テレビの前で仰向けになり、臍の上に温灸器を載せて腹部を温めていた父。
早い時期に満鉄職員だった父親と生き別れになり、引き揚げてきた直後、誰よりも愛していた母親が苦労の末、病死した。そのせいか、「家族」というものに対して、私には到底、信じがたいほどの幻想を抱いていた父。若いころはカメラが趣味で、娘や妻をモデルにし、日曜になるたびに、私と母を着飾らせては狭い社宅の庭に立たせ、シャッターを切って「作品」作りに励んでいた父。
帝大出、ということを生涯の誇りにしていた、あのおそろしく気取り屋の、実際、知性と教養に関してはまぎれもなく他者にひけをとらなかった父。
安月給のサラリーマンだったのに、人一倍、見栄っぱりで、母の実家に挨拶に行く時は、まだ幼かった私に、当時としては目の玉が飛び出るほど高価な「舶来人形」を買ってきては抱かせていた父。
「嘘字」を書くことは何よりも恥ずかしいことと私に教え、正しい漢字を使って、正しい日本語を書きなさい、と厳しく躾けてきた父。
そんな父が、こんなものを使っていた……実際に使っていたかどうかは定かではなくても、少なくとも所有していた、と思うと、可笑しくて可笑しくて、しまいにはもう、腹の皮がよじれ、笑いすぎたために涙がにじみ、鼻水まであふれ、息ができなくなる始末だった。
そして、その笑いの底の底には、久し振りに感じる深い安堵があった。もっと若いころに、同じものを発見していたら、不潔だと思ったかもしれない。それが娘としての健全な反応だろう。
だが、当時の私はもう、五十も半ばを過ぎていた。不潔も何も感じなかった。私は本当に、掛け値なしにそれらを発見できて嬉しかったのだ。