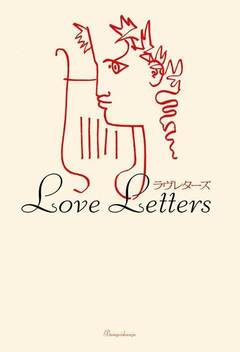最後まで生きようとした男
ある日、酒の席で、長く親しくしてきた文藝春秋『オール讀物』の編集者にそんな話を打ち明けた。父の死後、半年ほどたっていたと思う。
遺品から性具が出てきた話をし、彼を笑わせ、「ついては、亡き父をテーマにしたエッセイを『オール讀物』で書かせてもらえないだろうか」と頼んでみた。それはごく軽い気持ちから言ったことだった。
だが、その編集者は間髪を入れず、膝を乗り出し、大まじめな顔をして言った。「エッセイなんてもったいない。小説にすべきです。小説にしてください」と。
彼のそのひと言がなかったら、私は『沈黙のひと』という作品は書かなかったと思う。小説など、はなから考えていなかった。エッセイにすることしか、念頭になかった。実在の人物……しかも、自分の父親をモデルにした小説を書くなど、気恥ずかしさを通り越して、そらおそろしくもあった。
だが、何かが強く私を突き動かしていた。時間を作っては、父が遺した文章や手紙の下書き、手帳、備忘録のようなものを読み進めていった。
試練に次ぐ試練、襲いかかる苦悩、つまらぬプライド、つまらぬ自己弁護、つまらぬ欲望の数々……しかしそこには、生きるということの根源的な意味、時代を超えた人間の姿があった。
最後まで生きようとしていたひとりの男を、私は、自分の父に託して書いたつもりである。むろん、これは私小説ではない。フィクションだ。
だが、事実をそのまま小説化した部分も少なくない。実在の女性、羽場百合子さんと父との間でやりとりされた手紙の一部、そして、父と羽場さんがそれぞれ詠んだ短歌を引用させていただいたのは、その最たるものだろう。
羽場百合子さんは、以前、教職についておられ、朝日歌壇の常連でもあった。父は、朝日歌壇に掲載された羽場さんの歌にいたく感銘を受け、それがきっかけでふたりは知り合う。羽場さんは父にとっての、文字通りの「歌友」であった。
父の死後、初めて私は羽場さんとお会いした。小説に「小松日出子」として描写した通りの女性であった。父の苦しかった最晩年に、美しい月明かりのような静かな光を投げかけてくださった女性でもある。
ひとたびも君のみ声を聞けぬままに言語障害すすむは哀し
みこころに言葉溢れむ息のごとききみのみ声を全身で聴く
人生の最後に、これほどやさしい、美しい短歌を詠み、贈ってくれる女性がいたとは。父の生涯はあの時代を生きた人の例にもれず、必ずしも穏やかなものではなかったと思うが、彼はいつだって、自らが発する「ことば」、他者から受け取る「ことば」に救われてきたようにも思う。
『オール讀物』連載中、毎回、締め切りが近づくたびに私は涙を流した。恥ずかしいことに、父が書き遺したもの、小さなメモ……たとえば、○月○日、午後二時、歯医者、とか、×月×日、真理子にサイン本依頼……などと力のない筆跡で書かれた手帳の予定表を目にしただけでも、涙があふれてきて往生した。家族の団欒が好きではなく、早くから巣立ち、勝手に生き、ろくに実家にも帰らずにいたというのに、なぜ、そんなものを見て涙が出てくるのか、その「なぜ」が知りたくて、父の小説を書いていたようにも思う。
そんな父を愛し、嫉妬し続けるあまり、憎んですらいたであろう母は、今、重度の認知症の上、閉塞性動脈硬化症という厄介な病気で入院している。すでに二年前、壊死した左足を切断する手術を受けた。残った右足も血管が詰まり、壊死が始まっている。
四月の誕生日を迎えると九十歳。生命とりになるような切断はせず、炎症部位の消毒を続けて経過観察しながら余生を送らせる、という結論が出た。まもなく退院して、再び施設での暮らしが始まる。
先日、見舞った際、ベッドの母の手を握りながら、『沈黙のひと』が吉川英治文学賞を受賞したことを報告した。むろん、母には通じない。私が娘であることもわからなくなっている。
だが、その時、母の手を握っている自分が、四年前、同じように死を間近にした父の手を握りしめ、昔懐かしい話を続けていた自分と重なった。
ふしぎだった。愛憎相半ばするばかりで、幸福な結婚生活とは言いがたかったが、父と母は娘である私の手を通し、今もひとつにつながっている、と思った。