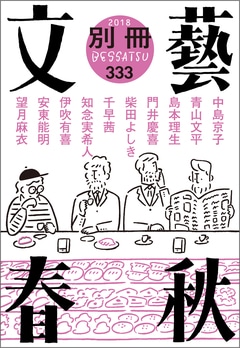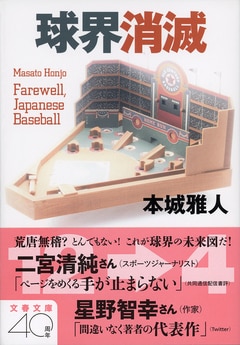社会部時代の同僚だった桑島からエアメールが届いた。
〈前略 俺は連日、ココム違反事件の取材で飛び回ってる。どこを取材してもソ連はまだこんな汚いことをやっていたのかとみんな呆れてるぞ。こんなことでゴルバチョフは民主化と経済の発展を成し遂げられるのかな。俺は土井垣が無茶な取材をして危険な目に遭っていないか心配だ。十分に気を付けろ。そうは言っても俺はおまえが送ってくる記事を毎日読むのを楽しみにしてるぞ〉
太字の水性ペンで荒々しくそう書いてあった。手紙は検閲されることもあるが、桑島はその危険も承知の上で、無茶するなと伝えたかったのだろう。
この国で新聞記者が動き回ることには危険が付きまとう。しかし当局が許可した場所で取材するだけでは、ソ連の宣伝活動に手を貸していることにしかならない。ネタ元まではいかなくても、いざという時に話を聞けるロシア人の友人を作っておきたい。そう思った土井垣は、朝刊用の送稿が終わった夕方になると、街へと出る。
まずは、夜な夜な行われていたロシア人のパーティーに潜り込むことを日課にした。主催者が政治家や官僚だと、挨拶しても警護に止められるが、招待客は土井垣が日本の新聞記者だと名乗っても追い返さず、世間話には応じた。中には積極的に酒を勧める者もいた。ロシアでは一人で飲むのはアル中のすることだと思われているらしく、彼らは常に飲み相手を探していた。そこに金を持っていそうな外国特派員が来るのだから、飲み代を浮かそうと向こうから誘ってくる。土井垣も好都合だと喜んで応じたが、酒をたかられるだけで、ろくな話は聞き出せないことがほとんどだった。
その夜はラトビア出身の退役軍人の誕生日パーティーだった。近くにいた人間に片っ端から声をかけていくのだが、ロシア人は米国人のようにファーストネームを使わず、「ガスパヂーン・ドイガキ」と呼び、敬称をつけて堅苦しく話すため、なかなか打ち解けられない。
ところがそのパーティーで「きみの名前はタスクというのか」と土井垣の下の名前に興味を持つ男が現れた。
土井垣より小柄で、一七〇センチくらいしかないその男は異彩を放っていた。なにせブロンドの髪をマッシュルームカットにし、光沢があるベージュのジャケットを着て、綿のズボンを穿いていたのだ。周りはみんなグレーのスーツで、額が見えるようにきちんと整髪していて、日本のサラリーマンよりも地味な恰好をしているというのに。
「ボリス・カルピンだ、『青年と文学』という雑誌で記者をしている」涼しげな目で彼の方から握手を求められた。握手を求められるのもこの国では珍しい。