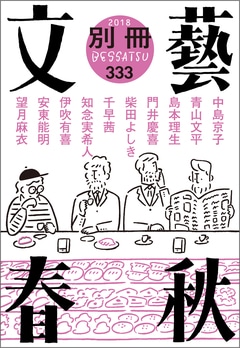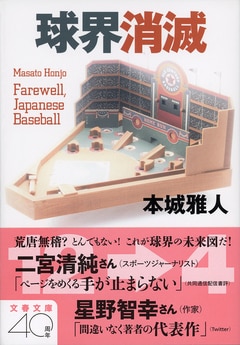「なんて呼べばいい」
「ボリスでいい。未来のヒーロー、ボリス・エリツィンと同じだ」彼の方からファーストネームで呼ぶように言ってきた。
「じゃあ、そう呼ばせてもらうよ」
「タスクはフリートウッド・マックのレコードと同じ名前だな」
そう言われても土井垣には意味が分からなかった。レコードというからには曲名なのだろうか。
「残念ながらそのレコードは聴いたことがない。それにそのタイトルにしても、僕の名前とは意味が違うと思う」
TASKなら「仕事」や「任務」。TUSKなら「牙」だ。周りには軍人や共産党員もいたため、真面目に答えたのだが、彼は屈託のない笑顔で、さらに音楽の話を続けてくる。
「それならきみはどんなミュージシャンが好きなんだ。ピンク・フロイドはどうだい」
「それなら聴いたことがある」それはまったくの嘘で、数年前に何カ月も全米一位となったと新聞の文化面に載っていたのを思い出した程度だ。
「それはいい趣味だ。『アナザー・ブリック・イン・ザ・ウォール』は大人の古い考えを押しつける教育制度へのアンチテーゼだからな」
彼はそこで、おそらくその曲だと思われる「我々には教育は必要ではない」というフレーズを英語で歌い始めた。近くにいた初老の男が訝しげな顔で見る。
「だけど良かったよ、西側の特派員にこういった質問をすると、大概、自分は音楽なんて聴かないと嘘をつく。たまに『バック・イン・ザ・USSR』とつまらない冗談を言う記者はいたけどな」
鼻歌が終わると口に手を当てて笑った。そう言えばこの男、ロシア人にしては表情が豊かだ。
「もしやタスクは心配してるのか。公共の場で退廃したロックの話をしていいのかと」
「そういうのはよくないと聞いていた」正直に答える。
「きみは誤解してるぞ。ソ連の若者だってロックも聴けば、ジャズだって聴く。街中で大音量でかかっているか、それとも部屋でこっそり聴くかの違いだけさ。もしきみが『ソ連でかかっているレコードは、クラシックかカチューシャだ』という記事を日本に送っているとしたら、僕は腹を抱えて笑ってしまうよ」
本当にこの男はソ連の記者なのか。何かの罠ではないかと怪しんだが、それより興味の方が上回った。