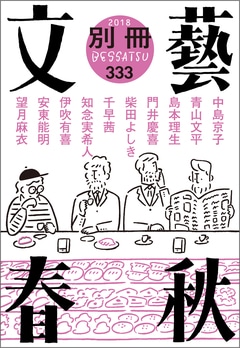「もう留守番電話の役割はうんざりなので、このまま留まってくれるといいんですけどね。せめて一週間は。まあ社長なんてそんなものなんでしょうけど」
「おつかれさん」
リウは受付係を励ますようにテーブルの縁をぽんぽんと叩き、私たちについてくるよう目配せする。黄色いカーペット張りのフロアの真ん中には軽いミーティングがこなせそうなソファとテーブルが並び、その先に巨大な巻き貝のような螺旋状のスロープがあった。どうやら社長室はこの上にあるらしい。
「なぜ階段じゃなくてスロープなんです?」
運動が苦手らしいメグミが早くも息を切らせながら訊ねると、リウは手すりに掴まって重そうな体をゆっくり動かしながら答えた。
「レクタングルの社長が車椅子利用者だからさ」
「レクタングルって、つまりここの親会社の社長でしょう? なおのことエレベーターをつければいいのに」
「さあな。ワンフロア分だけのエレベーターを設置する費用をケチったんじゃないか? さ、もうひと踏ん張り。女王陛下が待ってるぞ」
全部で一巻き半と、まるで巻きのゆるい貝を思わせる傾斜の浅いスロープ通路に出て、ようやく社長室にたどり着いた。女王陛下への謁見というよりは、007の悪役の部屋に向かうような気持ちで、私はリウが叩いたノックの返答を待った。
「ハイ、みんな!」
当然ブロフェルドでもドクター・ノオでもなく、現れたのは陽気な女性だった。白髪交じりで灰色になった長い髪をポニーテールにし、耳に血のように赤い大きなイヤリングをつけ、上はざっくりした黒いニット、下はブルージーンズといういでたち。見た目も口調も溌剌とした、モー・エイブリー本人だった。
「久しぶりねリウ。それから後のふたりは新しい人? はじめてお会いするわ!」
驚いた、社員の顔を覚えているのだ。
「はじめまして、ヴィヴィアン・メリルです。モデラーとアニメーターを担当してます」
「メグミ・オガサワラです」
メグミは緊張してとっさに言葉が出てこなくなったのか、顔を真っ赤にして口をぽかんと開けたまま固まっている。するとモー社長はにっこりと微笑み、メグミの肩に手を回しつつ部屋に入るよう促した。うらやましい。私も緊張すれば良かった。
社長室は広々として、手前に応接間、右手奥に社長のデスクがある。床は大理石で、隅々までよく磨かれ、うっかりすると足を滑らせそうだ。観葉植物の鉢植えが並ぶ向こうには広い窓があり、ちょうど周辺の建物から頭ひとつ抜き出ているので、ロンドンの景色がよく見える。まるで空中に浮かぶ温室といったところだ。