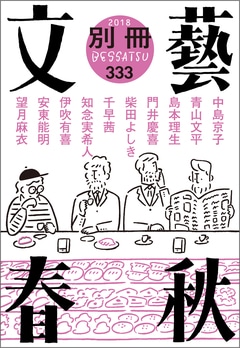私たちが部屋に入ったところで、誰かのiPhone独特の着信音が鳴った。モーは「ちょっと失礼」と言って電話に出た。
応接間にはすでにジェイソンが到着していて、私たちと目が合うと、すぐ座るように手で合図した。ソファの形もユニークな、Cの形をしていて、真ん中に透明なローテーブルが置いてある。そして、ちょうど輪が欠けている部分に、ひとりがけのソファがあり、そこが女王の玉座なのだと察した。
「例の件についてはすでに話を通してある。今はモーの反応待ちだ」
例の件とはつまり、ポサダ監督がこだわり続けている映像作品のことだろう。ついに本物が観られるかもしれないと思うと、つい半月前までは知りもしなかった作品なのに、わくわくしてしまう。
「社長は覚えてらっしゃるんですか?」
メグミが私の膝に乗りそうな勢いで身を乗り出し、ジェイソンに訊ねると、ジェイソンは顔をしかめた。
「どうかな・・・・・・曖昧な感じで濁されてさ。覚えてないか、あるいはフィルムを喪失した可能性は高い。とりあえずポサダ監督にはまだ・・・・・・」
「ごめんなさい、急ぎの用事で。それで、何の話だったっけ?」
モーは気さくな調子でジェイソンの肩をぽんと叩いてから、ひとつだけ飛び地となっている玉座に腰掛けると、細く長い足を組んで、華やかな笑顔を浮かべた。話の進行は、スーパーバイザーに丸投げするのが最善手だ。
「ポサダ監督の件です。彼が幼少時にメキシコでご覧になったという映像作品に、モーが関係しているという話だったのですが」
「ああ、そうだった。タイトルもわからないのよね? 狼の類いが登場するものなら『狼男アメリカン』だけど、ポサダ監督は当然知ってるし、そもそも私を頼る必要はないし」
ジェイソンはカラベラが描いたデザイン画をモーに見せてみたが、モーは首を傾げる。
「・・・・・・ごめんなさい、やっぱり覚えてない。そもそもこのモンスターってパペットでしょう。私はパペットに関わったことがないのに、なぜ私の名前が挙がったのかな」
私はおやと思った。元ピザ店店員の彼がリンクスの新しい受付になるきっかけになった日、彼がレクタングルの社長からの電話を取った。代わったユージーンが、さっきのメグミのように緊張して受け答えしていたのをよく覚えている。その社長が「確かにモー社長はよく知っている」と言ったのだ。ユージーンが嘘をついていなければ。しかしユージーンにそんな嘘をつく必要はどこにもない。とすれば、モーが何か隠している。