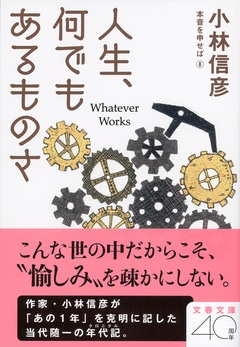そういえば、この映画は俳優も豪華だった。主演のジョエル・マクレイは、このすぐあとアルフレッド・ヒッチコックのサスペンス『海外特派員』(一九四〇)や、プレストン・スタージェスの傑作コメディ『サリヴァンの旅』(一九四一)、『パームビーチ・ストーリー』(一九四二)に出ているし、下って六二年には、サム・ペキンパーの西部劇『昼下りの決斗』で老雄ランドルフ・スコットと共演した。
一方、どこかコミカルなグッド・バッドガイに扮したロバート・プレストンは、フィルム・ノワールの佳篇『拳銃貸します』(一九四二)で名を残している。さらに驚かされたのは、その三十年後の一九七二年、ペキンパー監督の『ジュニア・ボナー/華麗なる挑戦』で、スティーヴ・マクイーンの父親役に扮したときだ。父と子の間柄のむずかしさやせつなさがじわりと滲み出る抒情的な映画だった。
だが、ここから大きく伸びたのは、ヒロインを演じたバーバラ・スタンウィックではないか。このあとにつづくプレストン・スタージェスの『レディ・イヴ』やハワード・ホークスの『教授と美女』(ともに一九四一)、あるいはビリー・ワイルダーの『深夜の告白』(一九四四)などは、どれも映画史に残る傑作だ。さらにはアンソニー・マンの『復讐の荒野』(一九五〇)やサミュエル・フラーの『四十挺の拳銃』(一九五七)といった異色の西部劇も見逃せない。
思わず脱線してしまったが、これも小林さんの映画評を読む楽しみのひとつだ。足のツボを的確に押されると、消化器や循環器が活発になるのと同様、小林さんの指が急所を指し示すと、一本の映画からさまざまな道や階段が枝分かれしていく。名著『日本の喜劇人』や『世界の喜劇人』を初めて読んだ四十五年前からずっと、私はこの恩恵に浴している。
そうだ、この本では一風変わった映画も取り上げられている。先に触れた『空の大怪獣 ラドン』(一九五六)がその映画だ。
『ゴジラ』(一九五四)を封切で見て怪獣映画に目覚めた私は、『ラドン』も公開直後に金沢の劇場で見た。併映は鶴田浩二と青山京子(小林さんはこの女優がひいきだったようだ)が主演した『眠狂四郎無頼控』(日高繁明監督)。それにしても、小林さんが『ラドン』に反応したとは、ちょっと意外だった。しかも驚いたことに、ぎくりとした箇所が私とほぼ同じらしいのだ。
《東宝怪獣映画初のカラー映画であるが、ラドン登場までのプロセスがすさまじい。いきなりラドンが現れずに、メガヌロンという巨大化したヤゴが、キリキリと音を立てて、貧しい炭鉱夫の家の畳の上を這いよってくる。/佐原健二と白川由美がふすまを閉めて逃げまわるというドメスティックな発端がまずこわい》(ゴジラの咆哮 II)
そのとおり、メガヌロンはラドンよりも怖かった。私が背筋を凍らせたのは、炭鉱のなかで三人の男がメガヌロンの餌食になる前に、大きな影が坑道の壁に映る場面だ。映画を見た日の夜、自宅二階の部屋でひとり横になっていた私は、月あかりに照らされて障子に映った木の枝の影におびえ、うわっと叫んで寝床の上に起き直った記憶がある。
《メガヌロンはこわいというより、気味が悪い。この幼虫でおどかしておいて、巨大なラドンが叫び声とともに現れる。大きさは不明、飛べば超音速という怪鳥だが、このくらい大きくないと博多の町が荒らされるというスペクタクル・シーンが納得できない》(同前)
ここも同感である。ラドンと空中戦を繰り広げる自衛隊機が西海橋の下をくぐり抜けるシーンもよく憶えている。六十年ほど前に見た映画をありありと思い出せたのは、小林さんのおかげだ。幼稚なのかな、私は。近いうちにDVDで見直してみようと思う。 とまあそんなわけで、小林さんの本には相変わらず教わることが多い。もうひとつ、読んでいて視界がさっと開けた箇所を引いておこう。
《〈東宝クレージー映画〉のベストワンは第一作の「ニッポン無責任時代」(一九六二年)であるのは、いまや、誰もが認めることであるが、ストーリー、人物もさることながら、植木さんの名曲がすさまじい勢いで、ドラマを転がしてゆくのである。その歌も、作詞・青島幸男、作曲・萩原哲晶(てつしよう)でないとダメなのだ。クレージー・キャッツの七人がどうがんばっても、植木さんが一連の植木節をうたわないと無理なのである》(いまはむかし 東宝クレージー映画のかずかず)
こういう文を読むと、否応なく大瀧詠一氏の名が頭に浮かぶ。小林さんは、大瀧氏の訃報をこの年の一月に聞いている。本書の前半に嘆きの色が濃いのは、ふたりの親密な友情の反映だろう。心の通い合った友を失うのは、本当につらいことだからだ。
大瀧詠一氏以外にも、小林さんは、この年に亡くなった斎藤晴彦、ローレン・バコール、山口淑子、曽根中生、井原高忠、ロビン・ウィリアムズ、高倉健、菅原文太といった人々を追悼している。じかに交流のあった方たちが多いようだが、どれも感傷に流れず、しかも心のこもった追悼だ。個人的な思い出が、そのまま時代を示す貴重な証言となるのは小林さんのエッセイの特徴だろう。穏健だが筋の一本通った社会批判も含めて、この本が多くの方に読まれることを願う。